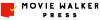生田斗真、白石和彌との対談で明かす『渇水』で感じた“熱量”「こんなにワクワクすることはない」
■「この企画が動き出したのは、生田さんが『やります』と言ってくれたおかげ」(白石)
――白石さんが『渇水』に企画・プロデュースで参加されることになった経緯から教えていただけますか?
白石「10年前に書かれたすばらしいホン(=脚本)があることや、その映画化がなかなか成立しないという話はいろいろなところで聞いていて。それにプロデューサーの長谷川晴彦さんには、『ひとよ』(19)でご一緒した時に『プロデューサーにいつかチャレンジしてみたい』という話をしていたんです。なので、長谷川さんから『ちょっと読んでもらいたいホンがあるんだけど』って言われた時は『知ってるよ、このホン!いいタイミングだし、僕にお手伝いできることがあったらやらせてください』という流れに自然になりましたね」
――白石さんは脚本のどこに魅力を感じられたんですか?
白石「主人公の岩切が幼い姉妹の窮地を肌で感じて、自分もパーソナルな問題をいろいろ抱えているというのに、彼女たちのためにラストで“しょぼいテロ”を起こします。そのテロを起こす瞬間の作劇がいいなと思ったし、たぶん僕はそれを映画にしたかったんでしょうね」
――生田さんは脚本を読んですぐに出演を快諾したそうですね。
生田「内容もすばらしかったですけど、それ以上に、いろいろな人の愛情や熱が込められたホンだなと思いましたし、ただならぬエネルギーを感じました。それこそ白石さんや長谷川さん、高橋正弥監督と初めてお会いした時も、みなさんがこの映画について熱く語られていたのが印象的で。映画化を絶対に成立させるんだ!という思いで長年にわたって努力されてきたことが伝わってきました。その人たちから『この作品をあなたに託したい』って言われるわけですよ。そんなにうれしいことはないので、『ぜひ、ご一緒させてください』というお返事をしましたね」
白石「それだけ僕らの熱も高かったと思うんだけど、生田さんはそんな僕らの願いを懐深く受け入れてくれた。10年間も成立しなかったこの企画が動き出したのは、間違いなく生田さんが『やります』と言ってくれたおかげです。主演の生田さんが決まって、門脇麦さんや尾野真千子さん、磯村勇斗さんといったほかのキャストも集まってくれましたからね」
――生田さんは水道局員の岩切にどのように臨まれたのでしょう?
生田「映画やドラマの撮影に入っていない時は、どんな役にでもなれるように髪をボサボサにしているんですけど、今回は水道局員の役なので、こざっぱりとした短めの髪にして撮影に入りました」
白石「衣裳合わせの段階でも、水道局員の服を着ただけで、これまでに見たことのない生田さんになるんだということは確認できました。生田さんに限らず、俳優さんは作品のことを考えながら役のキャラクターを探っていくと思うんですけど、衣裳合わせでは役をとらえた瞬間をちょっと見せてくれる。それを確認できた時に僕らは映画に向かう勇気をもらえるんですけど、今回も生田さんが岩切の立ち姿をちゃんと見せてくれたから心強かったです」
生田「ただ、磯村くんが演じた同僚の木田と水道料金滞納者の家を回る作業車のシーンを撮っている時に、岩切の心の渇きを実感したりもして。車の中に充満する滞った空気をふたりで共有しながら、一歩一歩、歩んでいった感覚がありますね」
――水道料金が払えない家の水を停める岩切を演じるうえで苦労した点は?
生田「仕事に没頭するあまり、岩切のもとから奥さんや子どもが離れていき、彼自身の心も渇ききってしまった。いつしかそれが、自分が渇いていることも忘れるぐらいの虚無感になっていったんだと思います。だから、家に帰って何を飲んでも味がしない。ご飯も美味しくない。そんな毎日をやり過ごしている無気力な状態の中で、なにかが足りないと思いながら揺れている彼の想いを表現するのは大変でした」
白石「さっき話した岩切が起こす“しょぼいテロ”は、行為だけを文字にすると半分笑えるYahoo!ニュース案件(笑)。『こういう変な奴いるよね』とか『これだけ暑かったら仕方ないよね』といった感想で終わっちゃうけど、そこには岩切なりの事情がある。ホンでその事情が垣間見えた時に、僕には岩切がヒーローに思えたから、彼を体現する生田さんがあのシーンでどんな顔をするのか見てみたかったんです」
――母親(門脇麦)が帰ってこない家に二人きりで取り残された幼い姉妹とのシーンでは、そんな岩切の非情さや優しさなど、様々な感情が交錯しますが、あの一連ではどんなことを大切にされましたか?
生田「彼女たちにはホンを渡してないんです。高橋監督がその場その場で状況を説明してセリフを伝えていくスタイルだったので、彼女たちからすると、僕らのような知らない男が来て、いきなり『水を停めるね』って言われても“え?”って感じだったんじゃないかな(笑)。それぐらい生っぽく撮っていたから、僕も磯村くんも彼女たちとの芝居だけが浮かないように生っぽい芝居を求められていたような気がします。監督から『彼女たちとあまりコミュニケーションをとらないで』とも言われていましたしね。だけど、すごく無邪気な子たちだから、現場で捕まえた昆虫とかを見せてくれるんですよ(笑)。その時はさすがに『可愛いね』とか言ったりするんですけど、『喋らないように』という監督の指示には従わなければいけないので、そこで距離をとるのは心苦しかったですね。でも、その揺れる感じが、情が移らないように姉妹と距離をとり、『規則だから』って言いながら水を停める岩切と上手く重なったと思います」
■「本当の映画好きたちが撮る現場にいられることが幸せでした」(生田)
――そんな生田さんの表情や言動は、白石さんにはどんなふうに見えました?
白石「実は僕、クランクインの直前にコロナになっちゃって、現場にあまり行けなかったんです。でも、現場から『毎日雨が降ってます』という報告は受けていて、晴れが続かなければいけない内容なのに可哀想だな〜って思っていたんです。生田さんも晴れていなければいけないシーンを雨天の日にごまかし、ごまかし撮影して、大丈夫かな?って思いながら演じられていたんじゃないかな。でも、そこはやっぱり、高橋監督を始めプロ集団がやっているから、カラッカラに撮れていた。生田さんの不安そうな表情や天候に恵まれない憤りみたいなものが、いくつもの問題を抱えた岩切の心象にいい具合に作用しているような感じもして。映画はいろいろな要素が複雑に絡み合ってできるものですけど、マイナスな条件も映画の力に変換できる高橋さんはやっぱり持っていると思いましたね。映画を愛してきた高橋さんが映画に愛された瞬間を見たような気がしました」
生田「この作品は16mmフィルムで撮っているんですよね。僕自身、全編フィルム撮影の作品は久しぶりだったというのもあるけれど『映画好きな野郎たちが撮っている映画の現場に自分はいまいるんだ!』という特別な感覚がありました」
白石「僕がコロナから快復してようやく現場に行ったのは、絶対に晴れてなきゃいけない滝のシーンだったんですけど、晴れ男の僕が行ったその撮影は晴れたんですよ(笑)。最高のプレゼントだなって勝手に思いながら、太陽の強い陽射しと滝の激しい水しぶきを浴びる生田さんを見させてもらいましたね」
――最後に完成した映画をご覧になった感想をお願いします。
白石「厳しい現実を描いているのに、本当に優しい作品になったと思います。僕が撮ったら、小説に近い、もう少しビターな終わり方をさせていたような気がするけれど、高橋さんは今回のエンディングを頑として譲らなくて。それだけに、完成した映画を観た時には『あっ、なるほど』って感心したし、すごく嫉妬しましたね」
生田「僕は熱量を感じました。制作陣のみなさんから『岩切はこういう人間だと思います』『岩切は僕の中にいるんです』みたいなことを言われた初対面の時の熱量が、そのまま投影されているような印象がすごくあって。僕自身、白石さんが監督業ではなく、初プロデュースという新しいことにチャレンジするこの作品で声をかけていただいて、こんなにワクワクすることはないなって思いました。またいつか、今度は監督と俳優として交われたらいいですね」
※高橋正弥監督の「高」は「はしご高」が正式表記
取材・文/イソガイマサト










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN