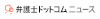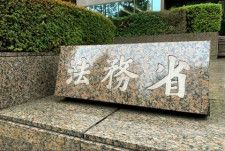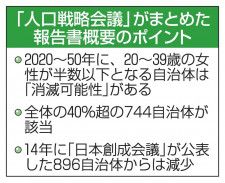「難民をほとんど見つけることができません」。こう発言した柳瀬房子・難民審査参与員の2年分の審査件数が参院法務委員会で明らかになり、入管法改正の「立法事実」に疑問符が突きつけられている。
冒頭の柳瀬氏の発言は、入管法改正の根拠とされている。ところが、柳瀬氏は2年間で、約2000件の審査請求(不服申し立て)を処理し、1年半で500人の申請者に対面審査(インタビュー)していたことがわかった。
しかし、これほどの審査件数を「適正」に実施することはできるのか。それ以前に出入国在留管理庁(入管)がごく一部の参与員を偏重することに問題はないのか。今、難民審査参与員への関心が高まっている。
5月23日の法務委員会で参考人として質疑に応じて、「柳瀬氏とは異なる認識を持っている」と話した阿部浩己さんは、人権と難民の研究を専門とする国際法学者だ。
難民審査参与員としての約10年間の経験から、制度の問題に言及された阿部さんが「日本の難民認定はなぜ少ないのか ―審査参与員として感じた問題と圧力」というテーマで、5月28日に講演をおこなった。
1982年から2022年末までの40年間に、日本で難民認定された人は1117人。難民条約に批准して以降も、なぜ日本では難民の受け入れが進まないのか。法務委員会、そして講演会の阿部さんの話から、戦後から連なる日本の難民認定の課題をまとめた。
●国による国境管理の例外として保護すべき存在
阿部さんは国家と人間の結びつきについて次のように話す。
「現在、世界には200ほどの国家が存在します。人間は生まれながらにどこかの国とつながり、国民としてその国の保護を受けられることになっていますが、実際にはそうではない状況があります。
たとえば世界に約430万人いるとされる無国籍者には、保護してくれる国が原則ありません。また、国民ではない外国人に対して不利な処遇を定めるなど、外国人の基本的人権がきちんと保障されない状況もあります」
外国人の人権保障について、阿部さんは「マクリーン事件」(*1)の判決を例にあげる。
「国には、外国人の入国と在留を管理する権限が認められていて、どのような外国人を、どのような条件で受け入れるかは国が決めていい。最高裁は1978年にそう判断しました。
外国人の処遇は、在留制度の枠内で与えられているに過ぎず、在留資格がない人は無権利状態になっても仕方ない――。
在留資格の中に外国人の処遇を閉じ込める認識は、人権を保護法益に据えた今日の国際法上、明確に否定されています」
保護してくれる自国を持たない無国籍者については、どこかの国が保護を提供しなくてはならないが、同じように、自分の国から逃れ出た「難民」も、別の国が保護の手を差し出す必要がある。国家は、外国人の入国・在留を決める権限を持つとされてきた一方で、難民については、無国籍者と並んで、国の国境管理の例外として国際法上、位置付けられてきたという。
「第2次世界大戦後、難民保護の3本柱が確立します。
・1948年の世界人権宣言14条1項 『すべての者は、迫害からの庇護を他国に求め、かつ享受する権利を有する』
・1951年の難民条約
・1951年の国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)の設立
世界人権宣言14条1項や難民条約が生み出された背景には、ユダヤ人らへの迫害という見過ごすことのできない現実がありました。条約や宣言は、頭の中だけで構想されるのではなく、現に起きている問題への対応としてつくられるものです。難民問題は国際的な性格を持つもので、それぞれの条約締約国が負担を負うことを前提としています。難民を受け入れず、他国に負担を強いるのでは、難民条約の基本的な枠組みを脅かすことになります」
●難民受け入れの背景にあった「アメリカの圧力」
1951年に採択された難民条約には『ヨーロッパの問題で自分たちの問題ではない』と距離を置き続けた日本が、その姿勢を変更したのはベトナム戦争後のことだ。
「インドシナ3国では、それまでアメリカを支持していた人たちが不利な状況になることを恐れて、大規模に国外に脱出しました。陸路の人も大勢いましたが、多くの人はボートピープルになりました。国際法上、船舶の船長は、遭難しているボートに遭遇した場合には救助する義務があります。そうして救助された人は、最初の寄港地で降ろすというのが国際的な慣行です。ところが日本は上陸を認める国内法上の根拠がないといって、最初は彼らの下船すら拒否しました。
1978年、日本は閣議了解でインドシナ難民の受け入れを始めますが、その背景にはアメリカの圧力がありました。ベトナム戦争の責任もあって難民を受け入れたアメリカが、『同盟国』日本にも外交的な圧力をかけたことで、日本は難民の受け入れに舵を切るのです。
最終的には27年間で1万1139人と、それなりの数に上りましたが、最初に渋ったことで『日本は難民の受け入れに冷淡な国』というイメージが世界に広がってしまったように思います」
インドシナ難民受け入れ開始から3年後の1981年、日本はようやく難民条約に加入する。ポツダム勅令として戦後も適用され続けた「出入国管理令」は「出入国管理及び難民認定法」と名称を変え、これによって難民認定手続きが初めて導入されることになった。
難民認定手続きは、認定数が極端に少ないままに推移し、審査過程に専門性や透明性が欠ける、といった批判を受けていく。
2002年に中国・瀋陽にある日本の総領事館に朝鮮民主主義人民共和国から逃れ出ようとした人たちが駆け込むという事件が勃発し、その対応があまりにも冷酷だったことから、日本の難民受け入れを見直す機運が高まる中、2005年に導入されたのが「難民審査参与員制度」だった。
●「難民の概念」を非常に狭く解釈している
難民認定手続きは「2段階」になっている。
「当事者は、地方入管局に申請書を提出します。その申請を難民調査官が調査し、インタビューをおこない、地方入管局の判断として、本省である入管庁の難民認定室に送ります。
実質的にはここで結論が出て、法務大臣の名の下に難民認定の可否が示されますが、難民認定室でどんな審査がされているのかはまったくわかりません。また、国会審議で、難民認定の本質についてまったく理解していない政務官が難民認否に直接関わっていることも判明するなど、ますます不透明さが増しています。
不認定の場合、当事者は地方入管局に審査請求を申し立てます。この段階で、外部の有識者として法務大臣に任命された難民審査参与員が、3人1組でインタビューなど審査をおこない、不服申立に理由があるかどうか、つまり難民該当性について意見を提出します。
参与員が提出した意見は入管庁の審判課という別の課でチェックされるのでしょうが、ここでも誰が、どんな審査をしているかわからないまま、最終的に法務大臣の名の下で可否が下されます。私自身が経験したことではありませんが、参与員は3人一致で認定すべきとなっていたのに、その意見が採用されないことがこれまでもありました。端的にいって、決定の過程は非常に不透明です」
難民条約の定める、保護すべき難民の要件は以下の5つになる。
1.迫害のおそれがあること
2.(そのおそれに)十分に理由があること
3.迫害の理由が、人種、宗教、国籍、特定の社会集団の構成員であること、政治的意見
4.国籍国の保護を受けられないこと
5.国籍国の外に逃れていること
難民の定義そのものは共通なのに、なぜ日本と欧米諸国では、認定数や認定率にこれほど大きな差があるのか。その理由として阿部さんは、日本が難民の概念をとても狭く解釈していることを挙げる。
「民族や宗教の違いを理由に武装勢力に襲われる危険性がどんなに高くても、政府が武装勢力を取り締まろうとしているなら迫害はない。日本ではそう解釈します。また、日本は国家がその申請者を個別に狙っていなければ、『迫害の十分な理由』があるとは言えないという個別把握論を採用してきました。
迫害を受けるおそれの判断は、多くが、本人の話を信じるかどうか、供述の信ぴょう性の評価にかかっています。難民条約の適用を監督する任務を与えられたUNHCRは、核心的な部分において本人の話に大筋で一貫性があれば、細部に多少の矛盾があっても難民として認めるよう要請しています。なぜなら間違っても、人を、迫害のおそれのある国に送還してはいけないからです。
難民該当性を裏づけるのが出身国情報とその分析です。出身国情報に当たらずに審査をすることはありえません。ところが日本では、客観的な証拠の提出がないといって申請者に不信の目を向け、出身国情報もきちんと精査しないまま供述の信ぴょう性を簡単に否定してしまう。私が審査してきた事案からは、そのような実情がはっきりと見て取れました」
●国境管理をする門番が難民を保護するという制度的矛盾
なぜ保護を求めてきた人たちに不信の目を向けるのか。阿部さんはこう説明する。
「入管の仕事は国境管理です。外国人の出入国を管理する門番として国境に立ちはだかる。規制と排除を本来の任務とする機関が難民の保護にあたるというのは、制度的に矛盾があるのです。
日本では、他の国では難民認定されるトルコ出身のクルド人がこれまでたった1人しか受け入れられていません。ミャンマー出身者も少ないように、難民認定に政治的・外交事情が影響しているとしか思えないような実態が広がっています。
かつて法務省の難民認定の研修教材には『(日本の)非友好国には難民認定を比較的自由におこなえるけれど、友好国から逃れてくる人には慎重にならざるをえない』という記述がありました。このことが報道されたあと、改定された版で該当記述は削除されましたが、今も同じ状況は続いていると疑われても仕方ないのではないでしょうか。
疑いを払拭したいのであれば、政府の一員である入管内で難民認定手続きを完結させず、入管庁から独立した難民認定機関を設けることが必要です。そうでなければ政治的・外交的配慮が入り込む素地が維持され、適正な審査は難しいでしょう」
もう1つ、難民審査の問題点として、阿部さんは1次審査のインタビューに代理人の立ち合いを認めていないことを挙げる。
「1次審査の供述調書は難民調査官と当事者のやりとりを記載していますが、その文章は調査官によって再構成されています。その調書は、2次の審査請求においても重要な資料として参照されます。そうである以上、1次審査にも代理人の立ち合いを認めるべきです。また、現在のような供述調書のスタイルではなく、調査官と申請者のやりとりをそのまま記述する形のほうが、文書作成者の恣意を排除できるので、適切だと思います。
ヨーロッパや韓国では、代理人の立ち合いや録音・録画が認められています。カナダやアメリカでも代理人の立会いは当然認められていますが、代理人の有無で、認定率に3倍の開きがあったという調査結果もあります」
提出資料の準備、また対面審査時における調査官の質問の意図を事前に説明してもらうなど、申請者は代理人から多くのサポートを得られることは間違いない。
●なぜ参与員に研修ができないのか
難民審査参与員については、これまでの法務委員会で下記が公表されている。
・常設班の数は東京26、名古屋5、大阪3
・2022年の不服申し立ては4740件で、そのうち「迅速な処理が可能かつ相当な事件」は3065件
・「迅速な処理が可能かつ相当な事件」を担当した臨時班の当該参与員は13名
・2022年に柳瀬参与員が関わった審査は1231件(全体の1/4)。勤務日数で計算すると、1日39.7件を担当。対面審査も1年半で500件担当
上記は入管が、柳瀬氏をはじめ特定の参与員を偏重してきたことを示唆している。
法務委員会に呼ばれた浅川晃広参与員は、担当したほとんどの案件において「出身国情報を見ずに、難民に当たらないと判断した」と公言した。繰り返しになるが、阿部さんは、出身国情報を見ずに審査するのは不可能だという。
「なぜこうした審査になるのか。悪い意味での慣れがあるのだと思います。経験と慣れによってかえって審査が荒くなり、結論を早く出すことへの抵抗感が薄れてしまう。慣れてくることにより、思い込みのようなものが働く。だから、その人の判断を誰かが何らかの形でチェックすることや、難民要件の解釈やインタビューの仕方など、実務的に意味のある研修を受け続ける体制が必要なんです。
こうした体制が取られないのは、参与員をつとめるのが『偉い先生方』ばかりだからではないかと私は常々思ってきました。『認証官』たる元高検検事長や元大使。あるいは元裁判官、弁護士、大学教授。そういう人たちに、平場の担当者のように研修を受けてくださいとは言いにくいのではないでしょうか。
難民認定については、最初は誰でも素人です。研修らしい研修がないまま、それぞれが独自のやり方で審査をするのは、どうにも問題です。それぞれの専門性を活かすためにも、実務研修は必要ということ。一度だけでなく、継続的な実務研修です。そして難民支援活動と難民認定業務は、本質的にまったく別物であることも理解してもらいたいと思います」
(取材・文/塚田恭子)
(*1)在留外国人の「政治活動の自由」と在留許可をめぐる事件
【プロフィール】 あべこうき/1958年生まれ。国際法学者。専門は国際人権法、国際難民法、平和研究。2012年1月から2022年3月まで約10年間、難民審査参与員を務めた。明治学院大学国際学部教授、同大学国際平和研究所所長。『国際法を物語る』シリーズ、『国際法の暴力を超えて』など著書多数。










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN