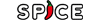「人」にフォーカスし、ミュージカル界の名バイプレイヤーや未来のスター(Star-To-Be)たち、一人ひとりの素顔の魅力に迫るSPICEの連載企画『ミュージカル・リレイヤーズ』(Musical Relayers)。「ミュージカルを継ぎ、繋ぐ者たち」という意を冠する本シリーズでは、各回、最後に「注目の人」を紹介いただきバトンを繋いでいきました。連載第十五回は、前回伊藤広祥さんが、「いわゆるプリンス風の曲も、ちょっとアレンジを入れた遊びの曲も歌える技術を持っている、自分とは対極」とその歌声を絶賛して紹介してくれた杉浦奎介(すぎうら・けいすけ)さんにご登場いただきます。(編集部)
「欲張りかもしれませんが、やれるのであれば何でも挑戦したいんです」
東京藝術大学声楽科で学んだ確かな歌唱力を武器に、ミュージカル作品で伸びやかなテノールを響かせ注目を集める俳優、杉浦奎介。2023年春には男性ヴォーカル・ユニット「REAL TRAUM」(リアル・トラウム)を結成し、9月にはミュージカル『アナスタシア』の出演が控えている。
杉浦は自身のターニングポイントとなった作品を振り返りながら、生き生きとした瞳で今後の展望を語ってくれた。
★杉浦さんの歩みを知れるインタビューは【こちら】(昨年30歳を記念して行ったアニバーサリーコンサートに絡め、デビュー以前、幼少期からを振り返っていただいています)
デビュー作でぶつかった“いい声”の葛藤

ーー東京藝術大学声楽科卒業後、大学院に通いながら俳優としての活動を始められたそうですね。デビュー作の『アップル・ツリー』(2016年)はいかがでしたか?
『アップル・ツリー』は作品そのものへの思い入れが強くあります。学生時代の恩師で、この作品の日本語版脚本も手掛けた青井陽治先生が紹介してくださった作品なんですよ。そんなご縁もあり、大学を卒業する頃にオーディションがあることを知って受けることにしました。
稽古場で感じたのは、これまでと求められるものが全然違うということ。それまでの僕は歌を武器としてやってきていたので、ガンガン歌っていくべきだと思い込んでいたんです。でも稽古場でやってみると「それじゃ全然入ってこない」と言われてしまって。自分がいいと思ってやってきたことが全く通用しなかったんです。今思えば、当時の自分はお芝居において「相手に伝えること」や「相手から受け取ること」を理解できていなかったんでしょうね。
ーー『アップル・ツリー』の演出は城田優さんでしたね。
そうです。稽古場では演出の(城田)優さんと音楽監督の西野誠さんが稽古を見てコメントしてくれました。僕は「面白くない、つまらない、入ってこない」と言われ続けていましたね(笑)。西野さん自身も声楽科を出ていらっしゃるので、僕の課題もよくわかってくださっていました。一番印象に残っているのは「“いい声だね”って言われるのがそのうち嫌になってくるよ」という言葉。この作品を機に、役者はいろんな声を出せなきゃいけないんじゃないかと思うようになりました。「いい声だね」と言われると、歌声という楽器だけを褒められているような感じがしちゃうんです。大切なのは、その“いい声”を使って何をするのかということ。むしろいい声じゃない方が良いということも少なくないんですよ。
いつのまにか“日生劇場の怪人”に!?

ーー2020年頃から一気にグランドミュージカル作品への出演が続いていらっしゃいますね。
単純に、時間的な余裕が出たということだと思うんです。2018年に大学院を卒業したので、2019年から俳優として本格的に始動し始めました。舞台の出演が決まるのは大体1年〜数年前なので、出演し始めたのがちょうど2020年頃だったのだと思います。
ーー本格的に始動してすぐにご活躍されているのはすごいことだと思います。最近、ミュージカルを観ると必ず杉浦さんがいらっしゃる気がするんです(笑)。
最近よくそう言われます(笑)。元々は僕も観る側の人間ですが、そういうときに「この人いつも出てるな〜」という人って絶対いるじゃないですか。自分に対してそう言われるのはなんだか不思議な感じがしますね(笑)。
ーー特に日生劇場によくいらっしゃいますよね?
2022年から今に至るまで、最も日生劇場にいた役者だと思います! 『INTO THE WOODS』『四月は君の嘘』『ジャージー・ボーイズ』『太平洋序曲』と4作品連続で東京公演が日生劇場でした。楽屋口の方には「おかえりなさい」と言われますし、劇場スタッフの方には「またなの!?」と三度見されるレベルです(笑)。
ーーそんな日生劇場の怪人と化していた杉浦さんが思う、日生劇場の魅力を教えてください。
建物そのものに歴史があって芸術的なところですね。直近で出演していたミュージカル『太平洋序曲』の作品テーマに“アート”というものがあったのですが、それがすごくマッチした劇場だったなと思います。『INTO THE WOODS』にも通ずるところがあったので、スティーブン・ソンドハイムの古風で芸術的な作品が合う劇場だなと感じました。
あとはリラックスできるところも魅力ですね。例えば帝国劇場は入るだけで緊張するんですよ。客席の匂いや雰囲気に“インペリアル感”があるというか(笑)。でも、日生劇場は不思議とすごく落ち着くんですよねえ。
ーー杉浦さんが1年以上もの間、日生劇場に通い続けたからでは……?
あ〜なるほど! 確かにホームになりつつあるのかもしれませんね(笑)。役者さんでも普通は知らないような裏動線も知っていて、ロビーへの近道やドアの施錠時間とかまで把握しているので。通い続けて知り尽くしちゃいました(笑)。
音楽の幅が広がった『ジャージー・ボーイズ』

ーー最近ご出演された作品の中で、『ジャージー・ボーイズ』だけ少し毛色が違いますね。
そうなんです。アンドリュー・ロイド・ウェバーやスティーブン・ソンドハイムなど比較的クラシカルな作品への出演が多かった中、『ジャージー・ボーイズ』は音楽のテイストが全然違ったんです。デビュー作の『アップル・ツリー』、憧れだった『レ・ミゼラブル』という2作品に続いて衝撃的な作品でした。
『ジャージー・ボーイズ』のような音楽の要素を僕は自分に感じていなかったので、お話しを頂いた時、最初は「まじか!」と驚きましたね。自分としてはポップスやバンド音楽も好きですし、いつか挑戦したいとは思っていたんです。そんな僕を『ジャージー・ボーイズ』という作品に呼んでくださったのは意外で嬉しかったですね。
ーー『ジャージー・ボーイズ』が衝撃的だったのはどんなところですか?
そもそも音楽がオーケストラの生音ではなくバンドの音で構成されているので、生音に慣れてしまっていた自分は音の感覚の違いに苦労しました。ハーモニーの作り方も全然違ったんです。これまではビブラートを入れて歌声を重ねていくようなやり方をしてきたのですが、ビブラートなしで歌声をバーっと出して混ぜ合わせるような感じ。そういうときに“いい声”だと逸脱しちゃって混ざらないんです。だから 『ジャージー・ボーイズ』ではきれいに出す歌声は必要とされなくて。そのとき音楽監督補・ヴォーカルデザインを務めていた福井小百合さんはすごく的確な耳も持っていらっしゃる方なんですけど、やっぱり「いい声過ぎる」と言われましたね。「そのいい声はいらない、もっと息多めで、汚く出して」とコテンパンにされました(笑)。
そんな中でも、やっぱり中川晃教さんや藤岡正明さんが本当に素晴らしかったですね! 「ああ、これか」と。一体どうしたらこういう音楽を作ることができるんだろうと、すごく研究させていただきました。『ジャージー・ボーイズ』を通して、音楽の感覚や考え方の幅をさらに広げることができたと思います。
翻訳ミュージカルでは必須の工程〜歌詞検討会〜

ーー直近まで出演されていた『太平洋序曲』はとても意欲的な作品でしたね。
なかなか攻めている作品でしたね。日本の史実とフィクションを織り交ぜていて、歴史上の出来事が語られる中で役者はその一部となって再現していくという、かなり異色の作品。僕は台詞もほとんどなかったので、歌と動きだけで表現しなければならない難しさがありました。
出演者もグランドミュージカル程多いわけでもなく、セットも削ぎ落とされてシンプルなものだったので、日生劇場の広い舞台を埋められないんじゃないかと思いました。知り合いの演出家からも「Please Hello」の冒頭について「攻めてたね!」という感想をもらって。アメリカ提督役の僕が舞台中央の0番で歌い、バックで踊るのは2人だけというシーンがあるんです。確かにこれでよく日生劇場の舞台を埋めようとしたなあって(笑)。ある意味で贅沢な大変さもありました。
ーー『太平洋序曲』では歌詞検討会にも参加されていらっしゃいました。どのように進めていくものなんでしょうか?
翻訳家の方が作った訳詞を最終判断するタイミングで役者が呼ばれるんです。例えば『太平洋序曲』の場合は曲数がそんなに多くなかったので2日間で行いました。1日目にバーっと全部を歌って問題点を洗い出し、それを訳詞家の方が持ち帰って再検討し、2日目に改めて歌って検討していくという流れです。今回は日英共同制作だったので、全て録音してイギリス側に送って確認してもらう作業もありました。歌詞検討会では「役者が実際に歌って感じたことも教えてほしい」と言ってくださるので「こっちの方が歌いやすい」とか「ここをちょっと変えるだけで役者的には嬉しいです」という意見は結構言いますね。

ーーこの作業は翻訳ミュージカルではよくあることなんですか?
絶対にやっていると思います。あくまでスタッフワークなのであまり表に出ないかもしれませんが、必ずやることですね。僕も最近呼ばれることがすごく多いんです。最初は梅田芸術劇場主催の作品でよく呼んでいただいていて、『VIOLET』『アナスタシア』『INTO THE WOODS』などで携わらせてもらいました。最近は東宝やホリプロの作品でも呼んでいただくことがあります。
ーーご自身が出演されない作品の歌詞検討会に参加することもあるんですね。
そうですね。歌詞検討会では直前に譜面を渡されることが多くて、なんなら当日に渡されることもあるんです。役者は男女1人ずつで男性パートと女性パートそれぞれ全ての歌詞を検討していく必要があります。もちろんアンサンブルの歌詞も含めて全てやるのでかなりのボリュームです。それもあって「譜面がすぐに読めて、その場で歌詞が変わってもすぐに歌える人」が求められるんです。
『太平洋序曲』の歌詞検討会では僕と可知(寛子)さんだったのですが、可知さんは歌詞検討会の経験豊富なのですごく慣れていらっしゃって。今回の『太平洋序曲』には“可知寛子訳詞”も入っているんですよ。可知さんが「例えばこういうのどうですか?」と提案すると、訳詞家の方が「それ採用!」みたいな(笑)。可知さんはこの連載の第1回に登場された方でもあるので「僕も今度、連載に出させていただきます」という報告もしました(笑)。
■役者、アーティスト、クリエイター、いろんな顔を持つ人に

ーー最近、クラシカル・クロスオーヴァーの男性ヴォーカル・ユニット「REAL TRAUM」(リアル・トラウム)を結成されたそうで、おめでとうございます!
ありがとうございます!
ーーユニット結成のきっかけは何だったのでしょうか?
メンバーの4人は全員が東京藝術大学出身で、元々面識があるんです。リーダーの高島健一郎と僕が同級生で、堺裕馬と鳥尾匠海は先輩と後輩。高島は大学卒業後にウィーンへ留学していたんですが、去年彼が日本に帰ってきたときに「こういうユニットを作ろうと思っているんだけど、一緒にやらない?」と声をかけてもらったんです。僕なりに結構いろいろ考えたのですが、結果的にやることにしました。
ーーいろいろ考えた末にやると決めた理由は?
僕は役者でもありますが、歌もすごく好きなので歌手活動も並行してやりたいと思っていて、毎年ライブを開催しているんですね。その中で、いつかホールコンサートを開催したいという夢があったんです。ひとりでホールコンサートをやるにはまだまだ難しいところがありますが、ユニットになったら可能性がちょっと広がるんじゃないかと思ったんです。
しかもリアトラ(REAL TRAUMの略称)のメンバーは僕以外みんなクラシックの領域で活躍している面が強くて、ミュージカルを主としているのは僕だけなんです。ということは、クラシックファンの方にミュージカルを知ってもらえたり、逆にミュージカルファンの方にクラシックを面白いと思ってもらえたり、いろんな面で幅が広がる可能性があるんじゃないかなと思ったんです。あえてフィールドの違う人たちと組むのって面白いかもしれないな、と。それが決め手ですね。
ーー可能性が広がりますね。杉浦さん自身はこれからどんなことをやっていきたいですか?
まだ自分に何が合っているのかわかっていないんです。最初は演劇が好きで、10代の頃は「絶対に役者になる」と思っていました。役者になるために音楽を武器にしようと音大へ進み、20代から今に至るまではミュージカルに出る側に専念してきました。でもやっぱり、脚本や演出といったクリエイター側のことも好きな自分がいるんです。
次の舞台出演は2023年9月の『アナスタシア』ですが、その前に『ピーター・パン』の演出と歌唱指導にアシスタントとして入らせていただきます。欲張りかもしれませんが、やれるのであれば何でも挑戦したいんです。将来的には作品を作りたいという夢もあります。役者としての顔、アーティストとしての顔、クリエイターとしての顔……いろんな顔がある人になりたいですね。全部やっていけば、きっといつか繋がっていくと思うんです。

――この連載では毎回最後に、注目の役者さんを教えていただきます。杉浦さんの注目の方は?
まずは、田川景一さん。役者としても人間としても尊敬しています。このご時世なのでスウィングが活躍する機会が増えていますが、彼は多くのスウィングを担っているんですよ。本当に頭が良くて何でもできて、しっかり仕事をこなす人。以前僕が演出した作品に出てもらったときも、やっぱりすごい人だなあと思いました。僕にとっては先輩なんですが、先輩な感じは全然出さずに接してくれるんです。自分が役者として稽古場にいるときに「景ちゃんだったらどうするんだろう」と、彼の目を意識しちゃうことは少なくありません。
同い年で素晴らしいなあと思うのは、町屋美咲さん。彼女は歌が抜群に上手いんです! 僕の中で歌が上手い女性をパッと挙げるとしたら、町屋さんですね。僕が演出した作品に出演してもらったときも「やっぱり上手いなあ」と改めて思いました。同い年で一緒に切磋琢磨してきた仲で、今でもお互いの出演作を観に行ったり情報共有したり。何かと彼女からは影響を受けています。
それから、単純にプライベートですごく仲が良い、木暮真一郎。木暮とはお互いに大学を浪人していたときに音大受験の予備校で知り合ったので、もう10年以上の付き合いになります。彼が今の道に進んだのはどうやら僕の影響らしいんです。大学時代に僕が声をかけて同じミュージカルサークルで活動していた過去もあり、そうしたらいつの間にか彼は役者の道で行くと言い出して。プライベートでは朝まで電話することもあって、よく「付き合ってるの?」とツッコまれます(笑)。
取材・文 = 松村 蘭(らんねえ) 撮影=福岡諒祠
〈御礼とお知らせ〉2020年からスタートした本連載は、第十五回にて定期連載を終了します。これまでご出演いただきました15名の皆様ならびに読者の皆様、さらに昨年12月には、可知寛子さん、福田えりさん、森加織さんを迎えて初のオンラインイベントを行い、多くの方に盛り上げていただきましたことも含め、応援いただいた方々に改めてお礼申し上げます! 皆様からの感想やお声が励みになりました。一旦は終了となりますが、今後は不定期更新にてお届けしてまいります。約3年に渡り、ありがとうございました!










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN