今年No.1確定『映画』「圧倒的な評価を得ている」
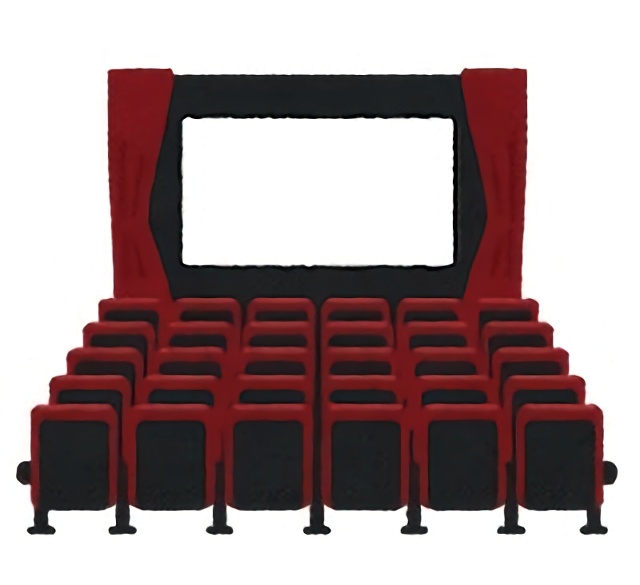
個人的な今年の映画ベストワンが決まった。邦画、洋画込みである。年末までにまだ2カ月あるが、ほぼ揺るがないだろう。
公開中のレオナルド・ディカプリオ主演「ワン・バトル・アフター・アナザー」(以下「ワン・バトル」)だ。近年で最高の作品である。映画史上に刻まれる作品だと言っても大げさではない。
単に個人の見解ではない。米国のみならず、日本でも映画の「専門家」たちの圧倒的な評価を得ている。米国では早くも、来年のアカデミー賞の大本命の呼び声が高い。何が凄いのか。
舞台は米国のようだが、時代の説明はない。政権に抵抗する革命組織が、爆弾闘争を繰り広げている。政権の過酷な移民政策への抵抗である。もちろん、理由はそれだけではない。
誰もが今のトランプ政権を重ねる。とはいえ、政府転覆を企む革命劇とは様相を異にする。政府側の軍人とも警察官ともつかぬ怪物的な権力亡者、ロックジョー(ショーン・ペン)が、異様な存在感をもって映画の中枢に立ちはだかるからだ。
革命軍の突入の際、ロックジョーの居場所に筋金入りの革命家の黒人女性、パーフィディア(テヤナ・テイラー)が踏み込んでくる。ロックジョーはパーフィディアに魅入ってしまう。彼女の性的な魅力にノックアウトされるのだ。
パーフィディアは同じ革命軍の恋人、パット(レオナルド・ディカプリオ)と生活を始めたが、政府側に捕まってしまい、介入してきたロックジョーとの取引に応じる。
ホテルに赴けば(性関係をもてば)、釈放すると言われるのだ。その後、彼女は出産するが、再逮捕された際、仲間の居場所を漏らし、裏切り者となる。
ちょっとややこしいが、以降、映画は一気に16年後へと飛ぶ。一人娘と一緒に暮らすパットは、いささか怠惰な日々を送っている。パーフィディアは行方不明になっている。
ここから本筋となるわけだが、話は起伏に富み、緊迫感あふれるアクションシーンはじめ、コミカルな要素も加わり、作品はいよいよ未知の領域に突入していく。
といって、全体像をこと細かく書いていく余裕はない。ここはペンが演じた先の男の視点から見てみることで、本作を貫いている太い1本の筋をたどってみよう。
簡潔に言ってしまえば、ロックジョーを通して、アメリカという国家の中枢部に強固に深く巣くう秘密結社にメスを入れたことである。その組織は、国家の基盤とも関係がある。
冒頭、この男が登場するシーンから異様さが際立つ。パーフィディアが近寄ると、横になっていた彼がむっくと起き上がる。ゆったりしているが、どこか隙のない立ち上がり方あたりから、映画に不気味な空気が立ち込め始める。
彼女によって挑発され、服の中で男根を膨らまされるが、その表情は屈辱を染み込ませながらも、それだけではない奇態な一端が忍び込んでいるようにも見える。
そこから一気呵成だ。ペンの演技は度を越していく。皺を刻ませた顔の、くぐもった表情。パーフィディアの尻部分を舐め回すような、ギラついた目つき。年の割に腕周りがやけに太いのが、妙な威圧感をまき散らしてくる。
彼は性的な欲望の強さとともに、差別意識と権力欲に取りつかれているが、後者の2つは奇妙に結びついていると言うべきか。内面的な指向が、彼の形相や立ち居振る舞いなど、表面に浮き出しているかのような趣がある。
彼が憧れる結社からすると、ロックジョーは「象徴」的に見えたであろう。自身たちと同じ匂いを持っているが、その欲望があまりに凶暴化、表面化しすぎている。だから、疑念の念を持つ。
結社が当初から彼を疑いの目で見ていることは、重要である。象徴的に「突出」している人物は、疑念を持たれる。組織の鉄則ではないか。この両者の相関関係が、アクチュアルなのである。
「ワン・バトル」は映画史上、稀に見る人物を送り出した。数々ある本作の素晴らしい要素のひとつである。賞の類はあまり信用していないが、ペンはじめ、本作がアカデミー賞をとれなかったら、ある種の事件になると思う。とアサ芸プラスは報じた。
編集者:いまトピ編集部

 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN



