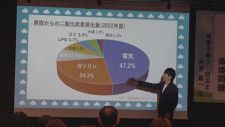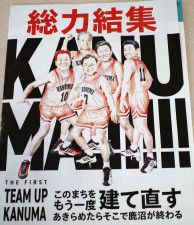海中を漂う無数のごみ。青く透き通った景色が広がる沖縄の海の地上からは見えないもう1つの姿だ。
【映像】海に沈んでいたゴミが、可愛すぎるアクセサリーやキーホルダーに…
この現実を多くの人に知ってもらいたいとの思いで、新たなダイビングショップを立ち上げたのが奈良県出身の東真七水さんだ。
「私たちは水中ゴミ拾い専門店『Dr.blue』というダイビングショップだ。水中ゴミ拾いとは、スキューバダイビングとゴミ拾いを組み合わせたものであり、海底に沈んだ ゴミをスキューバダイビングをしながら楽しく回収する新しいマリンアクティビティだ」(以下、東さん)
ボランティアという印象も強いゴミ拾いをマリンアクティビティとして提供。きれいな海を楽しみながら環境問題について考えることができる。
「この空き缶は1986年くらいまで販売されてたアサヒビールの缶だ。こういうものが時折見つかるためタイムトラベルをしてるような感じでロマンチックであり、面白いゴミがあると一緒に盛り上がれる。また、ゴミも分かりやすく転がっているものより、岩と岩の隙間にちょこっとペットボトルの頭が見えていたり、ビニール袋の端が砂から見えていたりするので“ヒントを探りながら行う宝探し・間違い探し”のようなゲーム性もある」

事業立ち上げのきっかけは、スキューバダイビングで目の当たりにした、沖縄のきれいな海。環境問題を入り口に始まった取り組みだが、次第にゴミ拾い自体の面白さに気づいていったという。
「これはもう販売していないダルマ瓶で30〜40年前の結構レアな形のアイテムだ。あと個人的に面白かったのは『呼び出しベル』だ。『どうして(捨てられたのか)?』と。そんなことを考えてると様々な感想が出てくる」
釣り糸やプラスチックゴミから江戸時代の貨幣まで、多種多様な水中ゴミ。
「ある研究では、海のゴミは直接海に破棄されたというよりは川から来ており、川のゴミは実は街から来ているという解釈がある。というのも、街中の道端のタバコなどは雨や風に飛ばされて水路に入り、そこから最終的に海にたどり着かせてしまっている。海のゴミと陸のゴミは別と思いがちだが、実は“すごく私たちの身近にある見過ごしていること”が原因で起こっている」
街中で見過ごされたゴミが、最終的に海にたどり着き、その後数十年にわたって残り続ける…。海の近くに住んでいなくても、海洋ゴミの問題は他人事ではないのだ。
「このようにゴミの問題などについて発信したり、テレビなどに出る中で『感動しました』『何かをやろうと思いました』という声も届くが、実際に行動に移している人は実はあまりいない気がしている。『いいな』と思っても誰もが日々忙しく、思いも薄れていってしまう。ダイビングに参加してくださった方も『ゴミを拾おうと思った』と言ってくれるが、やはり沖縄から地元に帰って仕事に専念していくとその気持ちは忘れていきやすい」

課題となっているのは、水中ゴミ拾いがきっかけで環境問題に興味を持ってくれた人の思いや行動の継続。そこでDr.blueが取り組んでいるのが、水中ゴミを活用したアップサイクルだ。元の価値よりもアップさせるリサイクルの一種で、拾ったゴミでキーホルダーやアクセサリーを作る体験ができる。
「優しい思いを忘れてほしくないため、“それを思い出させる形に残る何か”を持って帰ってほしいと思った時にアップサイクルがいいと。自分が拾ったゴミがキーホルダーなどになることで、地元に帰っても日々目に入ったり、思いが色濃く残る。ゴミ拾い=意識高い、少し変わった人がやっている、なんか楽しくない、汚い、臭い、大変という3Kみたいなイメージがあるが全然そうじゃない。本当に心の底から面白いところがたくさんあるので、楽しい側面を今後広めることで“1人の100歩より100人の1歩”を実現していきたい」

リサイクルは一般的に、原材料に戻して資源として再利用(例:古紙を再生紙に)するが、ダウンサイクルは価値を下げて資源を再利用(例:古着を雑巾に)、アップサイクルは別の用途のものに作り替え付加価値を与える(例:ゴミをキーホルダーやアクセサリーに)。
ダウンサイクルは手軽にできるが元の製品より価値を下げるため、比較的寿命が短くなる場合が多い。対してアップサイクルは価値が上がるので長く使える可能性が高くなることから、注目されている再利用の形だ。
The HEADLINE編集長の石田健氏は、さらなる課題を提示する。
「アップサイクルは小学校などで学ぶリサイクル活動のイメージとも近く、取り組みやすいため非常に素晴らしい。一方で、全体の環境問題を考えた時に、やはりそもそも企業の大量生産・大量廃棄というモデルに対して声をあげないまま安いからとファストファッションを安易に買っていないだろうか。そしてその一方で、『ゴミ拾いとリサイクルは大事だよね』という考えが、ある種いびつな形で両立してしまっている状況を問題視したほうがよい。もっと大きなインパクトを与えてこの気候変動、環境問題を解決するには、やはり企業側が構造を是正しなくてはいけないのではないか、と消費者から声を上げることが根本的には大事だ」
さらに石田氏は「『ゴミをポイ捨てしちゃいけない』ということも10年ほどで意識変革できた。だからこそ、現在は『(ファストファッションなどは)安いからしょうがない』という意見も全体の半分ほどいるかもしれないが、10年ほど言い続けていたら『大量消費は良くないよね』という価値観に変わっていくかもしれない。メディアが訴えかけることも大事だが、我々もDr.blueのような取り組みを応援しつつ声を上げるべきだ」と述べた。
(『ABEMAヒルズ』より)










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN