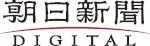宮城県内の自治体から能登半島地震の被災自治体に中長期で派遣されている職員が、これからの赴任を含め20日現在で計22人に上ることが、県のまとめでわかった。東日本大震災の経験を生かし、当時の「恩返し」に腰を据えて取り組む。
4月以降、宮城県庁から石川県庁に6人(4人は輪島市の出先機関勤務)、同県能登町3人、富山県1人の計10人を派遣。仙台市は同県内灘町に3人、志賀町2人、かほく市1人の計6人。このほか石巻市→志賀町、気仙沼市→能登町、名取市→輪島市、東松島市→能登町、山元町→穴水町と、各1人が派遣された。栗原市も6月1日付で輪島市に1人を送る。期間は多くが来年春までだ。
22人中13人が土木などの技術職で、港や上下水道の復旧に当たる。事務職の9人は、被災児童・生徒の就学支援や家屋の公費解体事務などを担う。
大災害時に被災自治体のニーズをとりまとめ、対応できる自治体をマッチングして長期派遣する仕組みは、東日本大震災後に整備が進んだ。今回も全国知事会、市長会、町村会が調整したほか、県から能登町への3人は、4年前に総務省がつくった「復旧・復興支援技術職員派遣制度」に基づく。派遣できる技術職員数を事前登録しておく制度だ。
東日本大震災で県内の市町は、他県からの多数の派遣職員に助けられた。復興事業がピークだった2013〜16年には毎年計600人以上に上り、今も4月現在で石巻市など3市町が計4人の派遣を受けている。
4月1日付で名取市から輪島市に下水道部門の応援で赴任した古山幸永(ゆきのり)さん(40)に、現地の様子などを聞いた。
◇
現地は被害が大きすぎ、下水道施設の本格復旧に着手できていないのが現状。ようやく水道が市全域に通りつつあり、下水道の使用も始まった。問い合わせのきた家屋に対し、仮設的に排水する方法を調べ、建設業者に対応をお願いするのが今の仕事だ。だが、道路や河川の工事に引っ張られ、業者がなかなかいないのが悩みになっている。
東日本大震災との一番の違いは立地条件。石川県は建設機材も業者も金沢近郊に集中し、奥能登には作業員の宿舎も足りない。私自身は能登空港そばの日本航空高校の寮が宿舎で、職場まで1時間近くかかる。近くに店もなく、不自由だが、覚悟の上で来ている。
市町村にはそれぞれ制度やルールがあるので、慣れるためにも応援派遣は少なくとも半年以上はいるべきだ。1〜2週間で交代する短期だと、受け入れ先がかえって疲弊する面もあるようだ。
私は大震災2年後に名取市に入庁し、下水道課などに所属。他県からの応援職員の方々に下水道のイロハを教えてもらったこともあり、自分も声がかかれば、手を挙げようと思っていた。1年家を空けることになるが、妻が「行ってこい」と背中を押してくれた。(編集委員・石橋英昭)










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN