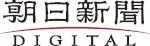原発で重大事故が起きた際の「屋内退避」の運用に関する原子力規制庁検討チームの第2回会合が20日、開かれた。現在は炉心損傷などで「全面緊急事態」となった場合、5〜30キロ圏内のUPZ(避難準備区域)の住民はすぐに屋内に退避するとされているが、今後は屋内退避の開始時期を遅らせたり、対象となる地域の範囲を縮小したりすることも視野に、検討を進めることになった。
検討チームは現在、原発の安全対策が機能することを前提に、事故時にどの程度、放射性物質が飛散するか、仮想の原発を対象にしたシミュレーションをすることにしている。そのため、新たな屋内退避の運用ルールの検討に当たっては、その結果を踏まえたやり方を考えることが望ましいと判断した。検討チームは来年3月に原子力規制委員会に報告書を提出する予定で、内容次第では、新潟県が策定している広域避難計画やUPZを抱える県内8市町(柏崎、長岡、上越、燕、見附、小千谷、十日町各市と出雲崎町)の避難計画に影響する可能性がある。
現在の対策は、東京電力福島第一原発事故を教訓に、事態が急速に悪化して放射性物質が外部に放出される状況を想定して組み立てられている。一方、福島事故後、東京電力柏崎刈羽原発7号機など、規制委の認可を受けた原発には、多重的な冷却・注水設備や、放出される放射性物質を減らす「フィルターベント」の設備など重大事故対策が備えられている。
検討チームは、これらの対策で放射性物質の放出を遅らせることができる半面、屋内退避が指示されたまま長期化した場合、経済活動の停滞など住民の負担が重くなる可能性を懸念。対策が機能した場合を想定した被曝(ひばく)線量のシミュレーションを行うことにした。
これを踏まえて規制庁は20日の会合で、「屋内退避の開始時期を全面緊急事態より遅らせたり、実施範囲をUPZ全域から縮小したりといった柔軟な判断が可能になるか、などの検討を想定する」との考え方を示した。
これに対し、福井県敦賀市の担当者からは、原発の事故対策について「しっかりと住民に理解されることが必要。住民には福島事故のイメージが強く残っている」と指摘。また、全面緊急事態では、5キロ圏内のPAZ(即時避難区域)の住民には避難が指示される点に関連して、宮城県の担当者が「PAZの運用にも手をつける可能性があるのか」と質問。規制庁側は「UPZを対象に検討を行うが、シミュレーションの結果を見たうえでの議論になるのかと思う」と答えた。(戸松康雄)










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN