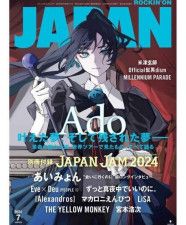人気アーティストAdoの国立競技場ライヴが意外な不評を買っている。「音が悪すぎた」という声がネット上に多く寄せられたのだ。これに対して、音楽ライターの神舘和典さんは、大規模ライヴの難しさを考えるとスタッフに同情すべき点もあるのでは、と指摘する。
***
「絶対に 絶対にすごい2日間にする 絶対に」
4月27日と28日に東京、国立競技場でワンマンライヴを行ったAdoは、決意、闘志、自信を前日Xにアップ。会場には2日間でのべ約14万人のファンが集結した。
ところがライヴの翌日から、熱狂したはずのファンによる“残念ですコメント”がいくつもアップされ、ネットをにぎわしている。
「演出最高だったのに音響がゴミ過ぎる」
「歌声きこえん 聞こえても変 耳障り」
「スタンド席だったけど客席の声ばかり響く」
……などなど。主に音響スタッフに向けての怒りだが、Adoに対しても「謝罪しろ」と書く人まであらわれた。
せっかくのライヴで100%の満足を得られなかった観客は気の毒としか言いようがないが、実のところ、音への不満は、大会場のライヴにはずっとつきものだった。長年、音楽ライターとして、また一人の音楽ファンとして数多くのライヴに通った筆者にとってもお馴染みの“トラブル“という印象である。
観客の入りも音に違いを生む
いい子になるつもりはないものの、筆者は音響スタッフに同情したくなる気持ちもある。それは以下のような理由からだ。
まず、音響の調整はリハーサルで完璧にするのが難しいという面もある。
たとえば、1990年のローリング・ストーンズの初来日公演。彼らは東京ドームで10日間公演を行い、全日程ソールドアウト。チケットの争奪戦がくり広げられた。
しかし、東京ドームで4日間行われた1998年の3回目の来日公演のときは、平日に行われた2日目、3日目の集客が少なく、2階スタンドの空席エリアはシートで覆われていた。筆者は全日程鑑賞。すると、満席の日と空席の多い席では明らかに音が違っていた。満席の日の音には温かさがあり、空席が目立つ日は金属製の響きを感じた。
ライヴは、アーティスト、会場、ファンの熱狂などそこにあるすべての相互作用によって実現するエンタテインメント。ステージ上のパフォーマンスに客席が反応し、リアクションでアーティストのテンションも上がっていく。
その様子にファンがさらに熱狂する。現実的には、歌や演奏は観客の身体や服に吸い込まれ、はね返りして会場に響く。こうした吸音や反響を計算して、音響スタッフは音をつくる。その際、客の少ない夜は演奏がスタンドの椅子のプラスティックや通路のコンクリートに硬く反響するリスクを伴う。
音質レベルは向上しているが…
日本武道館もかつては音がよくないと言われた。武道館は東京オリンピックの柔道の試合場としてつくられた会場。一方、ホールは音楽を聴くために材質が選ばれ設計されている。武道館にホールのような響きを求めるには無理がある。
しかし、そんな声は徐々に聞かなくなってきた。武道館の音響についてスタッフの経験値が上がったことが理由の一つだろう。
さらにアリーナやスタジアムで開催されるコンサートが増えた結果、相対的に武道館は聴きやすく楽しめる会場になっているのかもしれない。
また、スタジアムのコンサートの音響も、数を重ねるごとにレベルアップはしている。音響的な成功例も失敗例も増え、データが積み重ねられて、精度が上がっているのだろう。
さらに、スピーカーやアンプの進化も著しい。かつてはステージの両サイドに大型のスピーカーが積まれていた。すると、どうしても出力される場所からの距離や方向によって、音量やバランスに差が生じてしまう。
今はラインアレイという上から吊るスピーカー・システムが主流。サイズの小さなスピーカーの集合体なので、会場全体に個別に音を届けることができる。個別にチューニングすることもできる。会場のどのエリアで聴いても、同じような臨場感を体験できるように意識したサウンドチェックが行われている。
国立競技場の「経験不足」問題
さて、Adoがライヴを行った国立競技場は、東京オリンピック・パラリンピックのメイン会場としてつくられた。スポーツのために設計されたスタジアムで、ライヴの開催が目的ではない。
竣工は2019年11月30日。その後Adoのライヴまで、ソロアーティストとして有観客でパフォーマンスを行ったのは矢沢永吉のみ。つまり、音響のデータがあまりにも少ない。音のまわりかた、響きかた、風向き、温度や湿度による影響……など、推測によってやらなくてはならないことも多かったのではないか。
そして、もう一つ、国立競技場は野外なので、屋内会場以上に地域住民や企業に配慮しなくてはいけない。国立競技場周辺にはマンションをはじめ集合住宅もあり、会社も多い。夜、好きなだけ音を出せるエリアではない。
音響スタッフは、地域に配慮しながら、客席を満足させられる音量、音質、音のまわしかたを追求し、試行錯誤を重ねたはずだ。その結果、音響に満足できないファンが生じてしまった。おそらくAdoの歌を比較的明瞭に聴けたエリアもあったのではないか。でも、満足して帰宅した人の多くは体験したライヴの余韻に浸っている。ネットに不満を書こうとは思わない。
今後も当面、国立競技場での音響に満足できないケースはあるかもしれない。くり返しになるが、ここはあくまでもスポーツ施設。音楽のために設計されてはいないからだ。そして、今後もスポーツの大会が優先されるために、音楽のライヴが急増するとは考えづらい。生きたデータが集積されるにはまだまだ年月が必要になってくる。
もちろん、プロなのだから経験不足は理由にならない、お金を取っている以上は最高のものを提供すべきだと批判することは可能だろう。ただ、このような現実を私たちオーディエンス側も理解した上でライヴのチケットを購入したほうがいいのかもしれない。
神舘和典(コウダテ・カズノリ)
ジャーナリスト。1962(昭和37)年東京都生まれ。音楽をはじめ多くの分野で執筆。共著に『うんちの行方』、他に『墓と葬式の見積りをとってみた』『新書で入門 ジャズの鉄板50枚+α』など著書多数(いずれも新潮新書)。
デイリー新潮編集部










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN