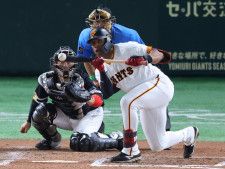毎年強力打線を看板にしているイメージが強い巨人だが、打撃は水物。今季もチーム打率.228がリーグ5位(5月9日終了時点)と打力不足に苦しんでいるが、これまでも貧打に泣いた年もある。
まず球団史上初の最下位に沈み、チーム打率もリーグワーストの.235に落ち込んだのが、長嶋茂雄監督就任1年目の1975年だ。
前年はV10を逃したとはいえ、チーム打率はリーグ3位の.253と、それなりに打てるチームだった。
だが、翌75年は、王貞治とともに“ON”として長年打線を引っ張ってきた長嶋は言うに及ばず、V9時代を支えた捕手・森昌彦、遊撃手・黒江透修の両ベテランも引退。守備面とともに打線にも少なからず影響が出た。
そんななかで、4番・王が打率.285(リーグ10位)、33本塁打、96打点と孤軍奮闘したが、前後を打つ淡口憲治(打率.293、12本塁打、42打点)、末次利光(打率.252、13本塁打、46打点)がともに規定打席未満で、中軸の迫力不足は否めなかった。
本来なら、ここには長嶋の後釜として新外国人のデーブ・ジョンソンが入るはずだったのだが、打率.197、13本塁打、38打点と期待を裏切り、“ジョン損”とこき下ろされたのも大誤算だった。
翌76年は、クリーンアップ強化を重要課題に新3番として日本ハムから張本勲を補強し、王とともに“OH砲”を形成。リーグトップのチーム打率.279で最下位から優勝という快挙を実現した。
順位は3位ながら、チーム打率はリーグ最下位の.243と再び貧打を露呈したのが、第1次長嶋政権最終年の1980年だ。
4番・王が30本塁打を記録したが、打率.236は規定打席到達者30人中最下位。巨人移籍後、2年連続で3割と二桁本塁打をマークしたジョン・シピンも打率.224、9本塁打と不振を極めた。
V9と76、77年の連覇に貢献した王もすでに40歳。柴田勲、高田繁の両ベテランも現役晩年を迎え、若手も成長途上という状況下で、打力低下は当然の結果だった。
シーズン後、3年連続V逸の長嶋監督は解任され、王も現役引退。V9巨人の象徴でもあったONが揃って表舞台を降り、ひとつの時代が終わりを告げた。
だが、「火中の栗を拾う」覚悟で藤田元司監督が指揮をとった翌81年は、長嶋監督時代の“地獄の伊東キャンプ”を体験した若手たちが一気に花開く。篠塚利夫が首位打者争いを演じ、リーグ2位の打率.357、“絶好調男”中畑清も打率.322(リーグ7位)をマーク。さらにはドラ1ルーキー・原辰徳が22本塁打で新人王に輝くなど、若い力が台頭し、V9以来8年ぶりの日本一を達成した。
次に1990年代を見ると、長嶋監督復帰1年目の93年がチーム打率.237で、13年ぶりにリーグワーストを記録した。
チームの最高打率は2番・川相昌弘の.290(リーグ10位)で、得点源となる主軸に故障や打撃不振が相次いだことが響いた。
4番・原はアキレス腱痛再発などから初めて規定打席未満(打率.229、11本塁打)に終わり、新外国人、ジェシー・バーフィールドもチームトップの26本塁打ながら、規定打席到達者最下位の打率.215(29位)と確実性に欠けた。
また、前年まで2年連続3割をマークした駒田徳広も打撃不振から5月に連続試合出場記録が「307」で途切れ、5月までにチームトップの8本塁打を記録した大久保博元も死球骨折で長期離脱するなど、負の連鎖が続いたことも貧打に拍車をかけた。
原をはじめ、80年代以降5度の優勝に貢献した主力が晩年を迎え、新4番が必要なチーム事情から、翌94年は中日から落合博満をFA補強。松井秀喜との新3、4番が功を奏し、5年ぶりの日本一を実現した。
75、80、93年とチーム打率がリーグ最下位を記録した翌年に、いずれもリーグ優勝や日本一を達成しているのは、打線のテコ入れに成功し、投打がかみ合った結果でもある。
FA制度が定着した90年代後半以降、巨人は毎年のように大型補強を繰り返し、重量打線を売りにしていたが、意外にも堀内恒夫監督時代の2005年(.260)、第2次原政権の初年度、06年(.251)と、チーム打率は2年連続リーグ最下位だった。
2割5分、6分台なら貧打とは言い難いが、4連覇を狙った第二次原政権最終年の15年には、チーム打率.243で9年ぶりのリーグワーストとなった。
実はV3を達成した前年も、規定打席到達者中3割打者はゼロで、チーム打率もリーグ5位の.257と重量打線に陰りが見えはじめていた。
翌15年はチーム内の“投高打低”が一層強まる。阿部慎之助、村田修一らの中心打者が故障などで打撃不振に陥り、規定打席到達者も坂本勇人(.269)、長野久義(.251)の2人だけという寂しい結果に。それでも同年は、ヤクルトに1.5ゲーム差の2位。打線がもっと投手陣を援護していれば、V4も可能だったかもしれない。
その後、4年間優勝から遠ざかった巨人は、第3次原政権で丸佳浩をFA補強するなど打線を強化し、19、20年とリーグ連覇を達成したが、21年から2年連続V逸。22年はチーム打率もリーグワーストの.242に沈んだ。
こうして振り返ってみると、巨人の貧打がクローズアップされた年は、概ね黄金時代や連覇の直後で一致している。14年の3連覇達成時に原監督が「勝ちつづけるということは、同時進行で衰退しつづけるということ」と語ったように、改めて常勝チームを維持しつづけることの難しさを痛感させられる。(文・久保田龍雄)
久保田龍雄/1960年生まれ。東京都出身。中央大学文学部卒業後、地方紙の記者を経て独立。プロアマ問わず野球を中心に執筆活動を展開している。きめの細かいデータと史実に基づいた考察には定評がある。










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN