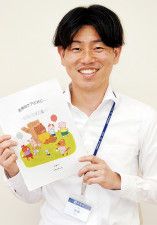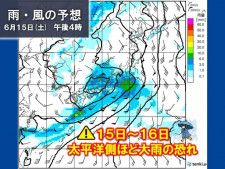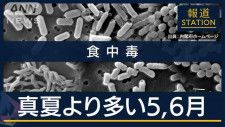「インクルーシブ」「インクルージョン」という言葉を知っていますか? 障害や多様性を排除するのではなく、「共生していく」という意味です。自身も障害のある子どもを持ち、滞在先のハワイでインクルーシブ教育に出合った江利川ちひろさんが、インクルーシブ教育の大切さや日本での課題を伝えます。
* * *
GWが明け、新年度の日常が本格的に始まったような気がしています。我が家には、高3の双子の娘がおり、それぞれの進路を決定する時期が近づいてきました。特に、医療的ケアが必要な長女の卒業後の進路は深刻で、長女と同じクラスのママたちに会うと、みんな同じように「行き先が見つからない不安」の話題になります。このコラムでも何度か書いていますが、現在の日本は、医療的ケア児(小児領域)から医療的ケア者(成人領域)に移行するシステムや社会資源の不足が目立ちます。今回は医療的ケア児者のことについて書いてみようと思います。
■医ケア児は10年で2倍に
5月8日に、「超党派医療的ケア児者支援議員連盟」が設立されました。
この会議は、医療的ケア児を取り巻く課題をテーマとした超党派有志の議員の勉強会「永田町子ども未来会議」に続くもので、2021年に施行された医療的ケア児支援法の2025年度の通常国会での改正に向けて、課題を洗い出すことを目標としているようです。
私が注目したのは、資料の中に喫緊の課題として「大人になった医療的ケア者の法的定義を整理し、社会基盤をつくる」という言葉があったことです。現在日本には、18歳未満の医療的ケア児が2万人以上いるとされ、過去10年で2倍に増えました(厚労省,2021)。そして、医療の進歩により、以前は18歳を超えて生きることができなかった医療的ケア児が成人になることも珍しくなくなり、出生時からケアを担っている小児科のスキルはどんどん上がるものの、成人科への移行システムがうまく機能していないために、いつまでも小児科を卒業できないケースも増えているのです。
■小児病棟に入れない
偶然にもこの原稿を書き始めた日の夜、長女がけいれん発作をきっかけに呼吸不全を起こし入院しました。この病院は長女が生まれたところであり、0歳から何度も入院していますが、制度により15歳以上は小児科病棟には入れないため、主治医が小児科のドクターでも成人病棟になります。今回は週末の夜間だったこともあり、万が一の急変に備えて一般病棟ではなく、全身管理と集中治療ができる救命救急病棟に入院することになりました。病棟の看護師さんたちはとても優しく声をかけてくださいましたが、やはり小児科の雰囲気とはまったく違います。今回は救命病棟ということもあると思いますが、病棟に提出する書類に「蘇生処置を希望するか?」や臓器提供に関する質問があり、社会福祉士の実習で医療従事者側として見てきた場面が、母親として質問されるとやはり少し戸惑ってしまいました。
■人工呼吸器の扱いに不慣れ
また、人工呼吸器の扱いの慣れ具合も小児科とは違いました。長女が使っている人工呼吸器はこの病院で管理されており、小児科病棟では同じ型の人工呼吸器を使用しているお子さんが他にも必ずいましたが、救命病棟であっても成人科ではまだ人工呼吸器の使用が小児科ほど頻繁ではないと知りました。小児科のドクターも一緒に看護師さんに操作の説明をしたものの、今回の入院では人工呼吸器の着け外しは小児科のドクターが行うことになりました。
一方で、「かわいい」や「癒やされる」と笑顔で言ってくれる看護師さんも複数いて、ご高齢の方が多い成人病棟では、17歳の医療的ケア児はまだまだ幼く見えてかわいがってもらえる存在のようです。おそらくこの雰囲気は長女だけに限らないことだと思います。ケアをしてくださる看護師さんのこうした気持ちから、何らかのかたちで受け入れにつながっていくと良いと思いました。
※AERAオンライン限定記事










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN