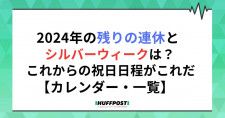新入生が大学に入って驚くことがある。4月下旬から連休が始まり、さあ、ゆっくり休んでアルバイトしよう、旅行しよう、いや、しっかり本を読もう、資格試験に向けて対策を練ろう、と思いきや、くじかれてしまう。大学によっては、連休中の祝日に授業を受けなければならないからだ。たとえば、今年の4月29日(月曜日、昭和の日)には、慶應義塾大、早稲田大など多くの大学で授業が行われた。
* * *
これはどういうことなのか。慶應義塾大の教員に尋ねてみた。
「15週ルールを守るためです」
こう言われたところで、大学教育の仕組みを知らないとよくわからない。
少し解説しよう。大学を設置するために必要な基準を定めた省令がある。大学設置基準だ。これには大学の授業、単位についてこう記されている。
「各授業科目の授業は、十分な教育効果を上げることができるよう、八週または十週、十五週その他の大学が定める適切な期間を単位として行うものとする」(第23条)
大学の授業は8週、10週、15週行うというルールだ。それぞれ「8週×4学期」、「10週×3学期」、「15週×2学期」という意味であるが、大部分の大学は2学期制である。この15週は従来、定期試験を含めて15週だと解釈されていた。
だが、2000年代後半、これが厳しくなった。
中央教育審議会(中教審)の委員会では、日本の学生は諸外国に比べて遊んでばかりいて勉強しない、何とかならないものか、といった議論がなされたという。その後、中教審はこんな答申を出している。
「講義であれば1単位当たり最低でも15時間の確保が必要とされる。これには定期試験の期間を含めてはならない」(「学士課程教育の構築に向けて」2008年)
これは「学士力答申」と呼ばれており、多くの大学は定期試験を含めないで15週の授業を行わなければならないと解釈されるようになった。大学、文部科学省関係者は「15週ルール」と呼び、結果的に各大学はこれまでより2週間、授業の週を増やすことになる。しかし、平日が祝日になってしまう場合、15週でおさめるのはきわめて困難となる。そこで、15週を確保するため、祝日を休まないで授業を行うことになったわけだ。

4月下旬から5月上旬にかけてのゴールデンウィークは祝日が4日ある。日曜日、そして祝日が日曜日と重なれば振り替え休日が設けられ、その結果、休日が5〜6日となり、曜日のめぐり合わせが良ければ大型連休となる。
なかでも2019年は、天皇が即位した5月1日が「国民の祝日」として休日となり、4月27日(土)から5月6日(月)まで、土日と祝日・休日が続いた。このため、「10連休」とする企業も見られた。
大学はそういうわけにはいかない。祝日を休みにすれば、「15週ルール」を守れないからだ。たとえば、南山大は祝日の4月29日(月曜、昭和の日)、5月3日(金曜、憲法記念日)などを休みにせず、10日間のうち授業を6日間行っている。立教大は5日間行っていた。
2022年、専修大は5月3日(火曜、憲法記念日)、4日(水曜、みどりの日)、5日(木曜、こどもの日)に授業を行っている。こどもの日は「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかる」ことを目的としており、こんな日までに授業を行うのはいかがなものだろう。
■大学によって異なるゴールデンウィーク対応
今年(2024年)はどうだったか。
ゴールデンウィークは4月27日(土曜)から5月6日(月曜、こどもの日の振り替え休日)までとなっており、4月30日、5月1、2日が平日になる。
この間の祝日や振り替え休日に授業を行っている大学は次の通り。
◆4月29日(月曜、昭和の日)
一橋大、青山学院大、慶應義塾大、国際基督教大、駒澤大、成城大、成蹊大、専修大、明治大、日本女子大、早稲田大、立命館大、関西大、甲南大、福岡大など。
◆5月3日(金曜、憲法記念日)
東京大、成蹊大など。
◆5月6日(月曜、こどもの日の振り替え休日)
国際基督教大、専修大、東洋大、横浜国立大、京都外国語大、同志社大、熊本大など。
一方、暦通り(4月30日、5月1、2日は授業あり)だったのが、北海道大、東北大、東京都立大、津田塾大、金沢大、京都大、京都女子大、近畿大、神戸大など。
10連休(4月30日、5月1、2日も休み)となった大学は、東京外国語大、法政大などだ。
祝日に授業があるのはゴールデンウィークだけではない。祝日の一部を休みとしない大学がある。おもな大学の学事暦から、祝日授業日を見てみよう(7月以降)。
◆早稲田大
7月15日(月曜、海の日)、10月14日(月曜、スポーツの日)、11月23日(土曜、勤労感謝の日)
◆明治大
7月15日、9月23日(月曜、秋分の日の振り替え休日)、10月14日、11月23日
◆同志社大
7月15日、10月14日
◆関西学院大
7月15日、10月14日、11月4日(月曜、文化の日の振り替え休日)
祝日は「祝日法」で制定された国民の休日である。大学生は国民ではないのか、と突っ込みたくなる。これでいいのだろうか。
■祝日に授業を行う大学は世界でも珍しい
立命館大教授の仲井邦佳さん(専門は言語学、スペイン語統語論など)は大学の学事暦、単位、授業時間数のあり方に詳しい。祝日に授業を行うことの問題点について解説してもらった。
「祝日を尊重するという常識に反した運営が多くの大学でなされているということは、憂うべきことです。大学設置基準を守るために大学は祝日に授業を行うといいます。だが、祝日法は法律であり、大学は社会的存在です。祝日法に定められた公的な祝日を無視していいか、疑問です。一般企業で祝日分を振り替えて別途、出勤日を設けるところはなく、祝日で仕事をしないから給料を差し引くということにもならない。それと同じです。世界中を見渡しても、祝日に授業を行う大学はきわめてまれです」
仲井さんは学生生活にとってマイナス面が多いという。
「運動部の対外試合や、音楽など文化部の発表会が祝日に開催されると、参加を諦めるか、授業を欠席せざるを得なくなります。こうした課外活動は教育の一環であり、それをおろそかにするのは本末転倒ではないでしょうか。さらに少数ですが、子どもを持つ学生もいます。幼稚園・保育園や小学校が休みのため子どもの面倒を見なければならず、大学に通えません」
仲井さんが教えている大学は京都にあり、観光地ならではの課題がある。
「京都の場合、多くの学生が観光関連業(飲食店や店舗)でアルバイトをしており、ゴールデンウィークの祝日に容易に休めません。また、いま、京都には外国人観光客があふれオーバーツーリズムとなっており、休日は電車やバスがたいへん混雑し登校が困難になっています」
教員の教育、研究活動の妨げにもなりかねない。
「教員の働き方改革に逆行します。子どもを預けて大学で教える人もいます。また、学会や研究会などを祝日に行うことができず、研究活動にも支障をきたします」
昨今、先進国のなかで日本の大学の論文数がふるわず、研究力の低下が懸念されている。研究者の集まりが減ってしまうことで、最先端研究の取り組みに影響は出ないだろうか。
一方、祝日をしっかり休む大学もある。近畿大は「本学は、祝日に授業を行いません」(大学ウェブサイト)と公言している。
しかし、その分、補講をしなければならず、夏休み、冬休みが短くなってしまう。祝日授業がない近畿大は8月6日まで、ゴールデンウィークを10連休とした法政大は8月1日まで授業を行うことになっている。
仲井さんは、学生が長期休暇期間を有効活用できないことを心配する。
「夏休みが短くなることで、夏季短期留学ができなくなるケースも出てくる。飛行機代がもっとも高い時期と重なってしまい、学生が海外に出かけづらくなってしまう。グローバル化に逆行しませんか」
また、仲井さんは、「2008年『学士力答申』の『これには定期試験の期間を含めてはならない』という文言が誤解を生んでいる。学事暦上の期間としては、定期試験を15週と別に設定すべきだというのは確かにその通りだ。だが一方で、定期試験受験とその準備学習は学習活動にほかならず、単位計算には含めるのが合理的である。単位制の趣旨と国際的実態からいって、13週程度が妥当ではないか。つまり、設置基準を順守しながら祝日授業をなくすことは可能ではないか」、という見解を示してくれた。
「日本の学生は勉強しない」という認識は間違っていない。学生本人のため、日本の将来のためにもっと勉強してほしい、という願いも理解できる。
だが、授業の回数を増やせば、勉強するようになるとは限らない。授業に出てもボーッとしている学生はいる。勉強するかしないかは学生次第ではないか。量より質、勉強へのモチベーションを高めるのも大学の役割である。
「15週ルール」は、学生生活、教員の教育や研究活動にとって現実的ではない。学生が自由に使える時間を増やすことで、学生が自分でしっかり考える、自学自習する習慣を身につけるように教えることのほうが、大学として大切なのではないだろうか。
学生は授業以外でも勉強する。学生をもっと信じてほしい。
祝日授業を強いる「15週ルール」を見直すべきである。
(※記事中の年間授業日は、各大学のウェブサイトに掲載されている「学事歴」からの引用)
(教育ジャーナリスト・小林哲夫)










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN