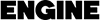“モーター”と“パーツ”を組み合わせた造語!
ちょっと古いアメリカ車、なかでもクライスラーのハイ・パフォーマンス・カー、“モパー”を愛する人たちがいる。“ちょっと古いクルマ”特集ということで、私は愛車である1992年式のジャガーXJSコンバーチブルで待ち合わせ場所である公園の駐車場へ向かった。
駐車場へ入ったジャガーに振り向いた人たちの横には、赤、緑、紫など目にも鮮やかなマッスルカーが並んでいる。いやあ、それにしてもモパーたち、なんてデカイんだろう! 全長4760mmのジャガーXJSコンバーチブルが小さく見える。

さて“モパー”とはもともと“モーター”と“パーツ”を組み合わせた造語で、クライスラーのパーツ部門の名称だった。1960年代になると、大排気量V8を搭載するクライスラーのモデルを愛する人たちがプライドを持って、それらを“モパー”という愛称で呼ぶようになったのだという。
ちなみに“モパー”はステランティス・グループのなかのクライスラー、ジープ、ダッジ、ラムなどのアクセサリーやパフォーマンス・パーツをいまも販売している。日本に馴染みが薄いのは、クライスラーやダッジの正規輸入がないからだろう。
この日集まったのはプリマス・クーダAAR(1970)、同440- 6(1970)、プリマス・ロードランナー(1970)、ダッジ・チャレンジャーRT440- 6(1970)、ダッジ・コロネット(1965)という5台である。
オーナーたちはイベントなどがあると集まる仲間で、モパーの専門店を通じて知り合ったのがきっかけだったそうだ。
なぜモパーなのか?
どうして、シボレーやフォードではなくモパーなのか? 集まったみなさんにモパーの魅力を聞いた。
「サイケデリックというわけではないんですけど、シボレーやフォードとは違うキャラクターを持っているんです。僕が好きになったきっかけはそこですね。エンジンが凄かったり。ただ、僕はシボレーもフォードも興味がないわけじゃないですよ。カッコイイものはカッコイイから」と言うのは、真っ赤なダッジ・コロネットに乗る内田 茂さん。

「勤めていた会社の隣にモパーに乗るご夫婦がいて、何度も見かけていいなあと思いました。雑誌を読み、知れば知るほどモパーはちょっと特殊なクルマで、どんどんのめり込んでいきました。もともとアメリカ車好きですが、いまはシボレーやフォードには興味がありません」と、モパー好きになったきっかけを話すのは、純白のプリマス・ロードランナーに乗る沼田 真さん。今日は息子さんも一緒に来た。
みんなとちょっと違うと言うのは、青いプリマス・クーダAARに乗る榎本茂生さん。
「僕は国産車を改造してドラッグ・レースに出ていたんですけど、そこにプリマス・バラクーダで参加した人がいきなり8秒台を出した。僕たちが13秒台だったときにです。そのクルマが積んでいたのがHEMIエンジン。いやあ、アメリカにはこんなメーカーがあるんだと驚きました。当時は世間に浸透していませんでしたからね」
大排気量V8の加速は爆発的だけれど、自分はそこを求めていないと言うのは、緑のプリマス・クーダに乗る網本顕一郎さん。
「買ったときはドラッグ・レースに出たこともありますけど、ちょっとクルマが可愛そうかなと。僕は独特の雰囲気を楽しんでいます」

紫色のダッジ・チャレンジャーに乗る木ノ本尚道さんは、シボレーやフォードとの違いを次のように説明した。
「シボレーやフォードが大衆向けモデルをバンバン出したときに、クライスラーは後発だったんですよ。後発なのでちょっと異端なものを出した。大衆受けはしないけれど、ものすごく個性がある。個性の組み合わせも多彩だった。ボディ・カラーはもちろん、エンジンやトランスミションの種類、コラム・シフトかフロア・シフトか、さらにはベンチ・シートまで選べた。そういう特殊性が魅力なんです」
異端者が乗るクルマ
映画の影響も大きいと内田さんは言う。
「ちょうどアメリカン・ニューシネマの時代で“バニシング・ポイント”や“ダーティ・メリー/クレイジーラリー”などの映画にモパーが登場したんです」
そうそうと頷く木ノ本さんが続く。
「アメリカン・ニューシネマでも異端な奴がモパーに乗ってるんですよ。たとえば、スティーブ・マックイーン主演の“ブリット”。正義のマックイーンが乗るのはフォード・マスタングで、敵が乗るのが真っ黒なダッジ・チャージャーですから」
映画のなかのカーチェイスでスティーブ・マックイーンが勝つように、操縦性能という面ではシボレーやフォードに劣るようだ。
「モパーは脚がいいなんて聞いたことがない」(内田さん)。
「助手席の人がまるで船だと言った」(榎本さん)。
「トランザム・レースなどの周回レースは全然勝てなかった」(木ノ本さん)。

「乗り比べるとみんなダメって言いますよね。その代わりエンジンの性能は素晴らしいって」(沼田さん)。
一方、目立つことはこの上ないそうだ。
「イベントがあると出口でカメラを構えて待っている人たちがいる」(木ノ本さん)。
「イベントで子供が見ていると、乗せてあげることもあります。富士山でイベントがあったときに、高校生を乗せたら、後に彼はプリマス・クーダを買った。先日も4歳の甥っ子を乗せたら大喜び。小さい子の感性に響くものがあるんだなあと思ったら嬉しかったです」(榎本さん)。
価格は高騰中
さて、みなさんが愛するモパーは日本でまだ買えるのか?
「タマはありますけど、めちゃくちゃ高いですよ。どんどん上がっている」(内田さん)。
「本国でもすごく高い。アメリカ人にとってのノスタルジアなんですよ。もし、この5台をアメリカに持って行ったらとんでもない価格ですよ。それから日本国内で販売されているクルマだったら大体経歴がわかります。あれは誰が乗っていたやつだとか。きちんとした状態で維持されてきた個体というのは、大体僕たちのレーダーに引っかかる。いまはそういうのが少ないかも」(木ノ本さん)。
「だからどうしても譲って欲しいという人が来ます。ところが、時間が経つと“妻が反対して”とか言ってキャンセルする人が多い。熱い思いを持ち続けるのは結構大変です。だから、ずっと乗り続けている人たちは本当に頑張っていると思います」(榎本さん)。

もうすぐ運転免許を取得するという沼田さんの息子、貴暉君はモパーをどう思っているのか?
「大好きです。ほかのクルマと違ってキャラクターがあるから」
なんとも頼もしい返事があった。
「プリマス・ロードランナーには、アニメの“ロードランナー”のステッカーが標準で付いていたりして、そういう遊び心があった。僕たちが愛するモパーが登場した時代はヒッピー文化、ベトナム戦争など、アメリカが揺れていた。過去の価値観が壊れていくなかで生まれて来たものだから、ちょっとほかのクルマとは違うのかもしれない」(木ノ本さん)。
そういうものが次の世代にも影響を与えている。だからちょっと古いクルマは面白いのだ。
「お父さんの秘密のガレージをバーンと開けたら、トヨタ・プリウスが出てくるよりモパーが出て来た方が楽しいでしょ」と木ノ本さんが最後に言った。
文=荒井寿彦(ENGINE編集部) 写真=神村 聖
(ENGINE2024年5月号)










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN