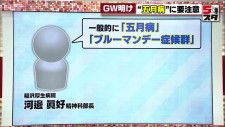<前編のあらすじ>
佳保(47歳)は、男性優位が抜けきらない会社で新卒から25年間勤めあげ、やっと課長に昇進した。部下に「女性だから」という理由で雑用を押し付ける上司や、男社会で女が出世することの大変さを理解していない夫にいら立っていた。ゴールデンウィーク明けに休みがちな新入社員のことを心配していたが、朝起きると佳保自身が無気力になっていて、気合で出勤したものの電車内で具合が悪くなってしまった。
「適応障害」と診断され休職
けっきょく駅員が救急車を呼び、佳保はそのまま病院に搬送された。昼過ぎごろ、大学が休講だった娘の早苗が佳保を迎えに来てくれた。
「体調不良くらいあるよ。お母さん頑張りすぎ」
ハンドルを握る早苗はそう笑っていたが、次の日も、その次の日も、佳保は朝が来る度に激しい動悸(どうき)に襲われて会社には行けなかった。
やがて佳保は適応障害と診断され、休職を余儀なくされた。家のベッドで昼まで眠り、起きてからもリビングでぼんやりと過ごした。
必要なのは休息だったのだろう。休職して動悸(どうき)は収まった。意識だってはっきりしている。
だからこそ、自分を容赦なく責めてしまう。
これなら意識がもうろうとしていたほうがマシだった。
ようやくつかんだポジションだった。25年もかけてようやく出世をしたというのに、どうしてこんなタイミングで、働けなくなってしまったんだろうか。
分かりやすいけがや病気であれば、諦めもつくだろう。しかし精神的な病となると、どうしても自分の弱さを責めてしまう。
すぐにでも復帰をしようと決意をするのだが、そう決心した翌朝になると頭痛に襲われた。
治療法も曖昧で、ストレスを認め、そのことを周りに話すというものだった。ストレスなんてずっとあったし、弘幸にはいろいろなことを話してきたつもりだ。
なのにこの様。これ以上の治療法がない以上、治る見込みだってない。一生、このままじゃないのかという不安が毎日、付きまとっていた。
日が暮れてくると、佳保は寝室に隠れるように戻る。
家族の顔を見るのがつらいのだ。
今の佳保は毎日家にいるくせに、家事は1つもやっていない。全て弘幸や早苗にまかせている。
もちろんそのことを家族は誰も責めてこない。
ありがたいと思う一方で、このふがいない状況がつらくもある。
だから佳保は誰とも会わないで済むよう、寝室に引きこもるようになっていった。
外出先で会社の後輩と鉢合わせ
久しぶりの外出だった。頭上から降り注ぐ5月の日差しに押しつぶされるように、佳保は背中を丸めた。弘幸はそんな佳保と並んで歩きながら、しっかりと手を握ってくれている。
「ちょっとさ、外に出ない?」
弘幸がそう提案してきたのはほんの数時間前。早苗がサークルで外出していた土曜の朝のことだった。
「気分転換にさ、映画でも見に行こうよ」
弘幸の提案に佳保は迷いながらうなずいた。正直、外出するのは不安があったが、迷惑をかけている申し訳なさから断ることができなかった。
映画館についた佳保たちは、早苗が友達と見に行って「絶対泣けるよ」と絶賛していた恋愛映画を見た。若い子とは感性が違うのだから……と思っていたが、泣けた。感動という大きな感情の前には年齢なんてものは関係ないのかもしれない。
「あれ、佳保さん?」
映画館を出たとき、後ろから声をかけられた。振り返ると繭香がいた。
「久しぶり……」
「やっぱり佳保さんだ。お久しぶりです」
自分の不運を呪(のろ)った。休職をしているくせに、休日に夫と映画を見に来ているところを見られた。サボっていると思われたかもしれない。
佳保はとっさにいいわけをしようと思ったが、何も言葉が出なかった。
すると、弘幸が一歩前に踏み出す。
「あ、もしかして佳保と同じ会社の方ですか?」
「はい。えっと……、初めまして。喜多村繭香といいます」
「初めまして。夫の内海弘幸です。今日は妻に無理言って映画に誘って見に来てたんです」
「そうなんですね。私も映画を見に来てたんですよ。元気そうで少し安心しました」
繭香がほほ笑み、佳保は伏し目がちに答える。
「体調はだいぶ良くなったんだけど、どうしても仕事に行くってなると、体が言うことをきかなくて……。皆には申し訳ないと思ってるんだけど」
佳保はどうにかして自分の症状を説明したかった。しかし言葉でどう表現していいのか分からない。
「いえいえ、気にしないでください。仕事は皆でなんとかなってますので」
気を遣って言ってくれただけなのかもしれないが、現場の人にそう言ってもらえると少しだけ心が和らぐ。
「今更こんなこと言ってあれなんですけど、私、ちょっと佳保さんのこと、心配してたんです」
「心配?」
「はい、実は私の友人も同じような経験をしてて」
「そ、そうなの?」
繭香は眉尻を下げてうなずいた。
「その子、真面目で責任感があって、仕事もバリバリやってたんですけど。あるときから、私に体がだるいとか会社に行きたくないとか相談してくるようになったんです」
「え……」
「でも、五月病だってその症状から目をそらして、仕事をし続けた結果、鬱(うつ)になっちゃって……」
そこで繭香は言葉を切った。
まるで自分自身の話を聞いてるようだった。
「そう、だったんだ……」
「だから、佳保さんが課長になって何でも抱え込むようになったのを見て、ちょっとそのときのその子に似てるなって思って、私、心配してたんです。でもなんて声をかけていいのか分からなくて」
佳保はかつての自分を思い返す。
思えば、慣れない仕事ばかりで、それを何とかこなそうと躍起になっていた。周りを頼ることを弱さだと思いこみ、自分ひとりで何とかしようとするばかりだった。
「あの、だから、ゆっくり休んでください。会社は全然問題ありませんから。それともし復帰したら、私たちを頼ってください」
繭香は真っすぐに佳保を見据えていた。
「……うん、ありがとう」
佳保は繭香に感謝を告げる。映画を見にきてよかったと思った。
大事なのは周りを頼ること
それから少しずつ佳保の状態は快方に向かっていった。
心がけたのは背負いすぎないこと、周りを頼ること。
あっという間のようでいて、ひどく長くも感じられる6カ月の療養期間があけて、佳保は仕事に復帰した。
「長い間、休んでしまって申し訳ありませんでした」
佳保は深く頭を下げたが、営業部の社員たちは温かく拍手をして出迎えてくれた。
「迷惑をかけた分を取り返せるように頑張ります」
「違いますよ、佳保さん」
前列にいた繭香がほほ笑んで、うなずいた。佳保は深呼吸をした。
「これからも迷惑をかけてしまうことがあるかもしれません。もちろん私も頑張ります。でも皆さんのことも、ぜひ頼らせてください」
佳保がそう言うと、長年お世話になっている部長が柔和な笑顔を向けてくる。
「少しずつで良い。内海は大事な戦力だから。少し肩の力抜いて、楽にやってくれ」
その言葉に、佳保は肩の力が一気に抜けていく感覚があった。
「はい、ありがとうございます」
男に負けないように、そんなことを考えすぎていたと思う。もちろん格差があるのも事実。しかし、自分が抜けた穴を男女関係なく埋めてくれたのも事実だ。だからこそ、自分はどちらにも目を背けず、目の前の部下や後輩たちが働きやすい部署にしていこう。もちろん、できることからコツコツと。
そんな風に佳保は決意を改めた。
※複数の事例から着想を得たフィクションです。実在の人物や団体などとは関係ありません。










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN




![見落とされた[第4の発達障害]](https://img.news.goo.ne.jp/image_proxy/compress/q_80/picture/nikkan_spa/s_nikkan_spa-1992942.jpg)