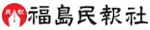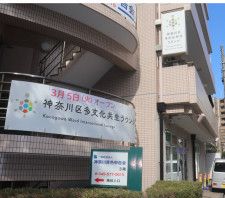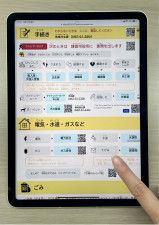県内で外国籍の子どもが増えている中、日本語の理解に向けた支援は追いついていない。学校の授業についていけず、学習意欲を失い、不登校になる例もあるという。人口減少が続く社会にあって、外国人は地域経済の維持にも欠かせなくなってくる。官民一体で学びを支える体制づくりを急ぐべきだ。
2023(令和5)年度時点で県内の公立小中高校に通う外国籍の子どもは311人で、2014(平成26)年度の172人から約8割増加した。日本語の理解が不十分で支援が必要な子どもは3分の1超の113人に上り、過去最多となっている。
日本語指導は、県国際交流協会の支援員やボランティアが担っている。市町村教委の依頼で学校に出向くなどしているが、長時間にわたり授業に付き添うような支援は難しいという。東南アジアをはじめ母語が多様化する中、担い手が不足している地域は多い。県や県教委は市町村、学校、関係団体とともに実情を把握し、人材の育成・確保をはじめ支援の在り方をきめ細かく検討する必要がある。
青森県では、地元の大学教授らが設立したNPOを中心に官民の関係機関が結び付き、子ども一人一人の指導計画作成や指導者育成、交流の場づくりなどを進めている。支援に必要な情報を詳細にまとめたガイドブックも発行しており、参考になる。
本県の県立高入試では、7校が来日3年以内を条件に外国人生徒の特別枠を設けている。今春は10人が志願し、合格は半数の5人にとどまった。受験に必要な日本語能力を3年で身に付けるのが難しい生徒も多く、県内六つの支援団体は今月、来日年数の条件緩和を県教委に要望した。進学の選択肢が広がれば、向学心の高い次代の人材の定着にもつながる。条件緩和は一考に値するのではないか。
浪江町を拠点とする福島国際研究教育機構(F―REI、エフレイ)の本施設整備が本格化するなど、県内に外国人を迎え入れる仕組みづくりは今後、重要性を増す。子どもたちが安心して日本語を習得できる環境を用意できれば、貴重な人材の呼び水にもなるだろう。持続可能な地域づくりの観点から、身近な問題として県民の関心も高めていきたい。(渡部育夫)










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN