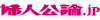2022年、61歳の奥様に先立たれたというベストセラー作家の樋口裕一さん。10歳年下の奥様は、1年余りの闘病ののちに亡くなられたとのことですが、樋口さんいわく「家族がうろたえる中、本人は愚痴や泣き言をほとんど言わずに泰然と死んでいった」そうです。「怒りっぽく、欠点も少なくなかった」という奥様が、なぜ<あっぱれな最期>を迎えられたのでしょうか? 樋口さんがその人生を振り返りつつ古今東西の文学・哲学を渉猟し「よく死ぬための生き方」を問います。
* * * * * * *
死について
一度は癌の手術に成功するも、再発が発見した妻。それからの7か月間、体力がだんだんと失われて、生命力がなくなっていく日々は本当につらく、苦しかっただろう。
しかし、抗癌剤で苦しんでいる時を除いて、妻は大きな声でいつも通りの生活を送っていた。いつも通り、明るい声で語り、笑っていた。
闘病中の人間を持つ家庭は暗くつらいものだと思うが、その中でもそれほど暗い気持ちにならずに済んだのは、妻本人がずっと泰然とし平気な顔でいたからだった。おそらく妻は深刻な様子を見せなかっただろうから、誰もがすぐに回復すると思っていたに違いない。
私を含めて、妻は誰にも死について嘆くことなく、苦しみを口にすることなく、あっぱれな最期を迎えたのだった。
だが、それにしても、なぜ妻はこのようなあっぱれな死を迎えられたのか。そもそも、妻はどのような死生観を抱いていたのだろう。死をどうとらえ、生をどうとらえていたのだろうか。
これまで多くの死生観が語られてきた。小説や詩の中、哲学書の中、演劇や映画の中などに死についての考えが散見される。思うに、ある程度の長さの小説や映画であれば、人の死がかかわらないことはほとんどないといってよいだろう。
ミステリーや戦争もの、ヒーローものはもちろんのこと、それ以外のものであっても、肉親や知人、あるいは主人公の死が語られる。
作家たち、哲学者たちは、どのような死についての意見を吐露しているのだろう。その中に妻の死生観に近いものはあるのだろうか。妻の菫としての死生観はどのような系譜に属するのだろう。
多くの人の死生観をざっと思い出してみる。そして、私なりに整理してみる。










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN