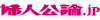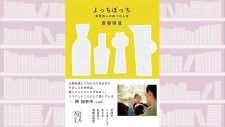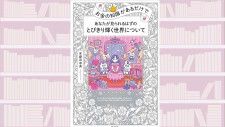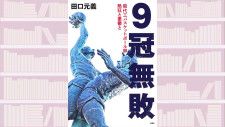今回取り上げるのは『よっちぼっち』(齋藤陽道 著/暮しの手帖社)。評者は書評家の中江有里さんです。
* * * * * * *
手話をことばとして生きるある写真家一家の記録
昔、手話を習ったことがある。
胸の前あたりで両手の人差し指を立て、第二関節部分で曲げる。人差し指を人に見立てて、頭を下げ合うイメージで「こんにちは」。
手話を学ぶなかで、その表現の豊かさに感嘆し、普段話していることばの由来や真の意味に無意識だったことに気づかされた。
写真家の著者はろう者。同じろう者の妻まなみとのやりとりは手話。二人の子どもには、生まれた時から自然と手話で語りかけてきた。
手話の喃語(なんご)を使っていた子どもたちは、やがて保育園に通い始めると、声に出して独り言を言ったり、歌ったりするようになる。
子どもの話す内容がわからないのは、不便で不安だろう。たぶん子ども自身もうまく言い表せられないもどかしさを抱えている。
目を合わさずとも伝わる音声言語と違い、手話は顔を合わせて伝える言語だ。ある日、著者はちょっとしたことで次男を叱った。すると次男は下を向いて動かない。「おとさんに『バカバカ』って言ってたよ」と長男が教えてくれた。
怒られて嫌な気持ちになったのだろう。そこで著者は次男にある手話を教える。
この場面を読んで「すごい」と感じた。子どもの態度に本気で腹を立ててしまう親だっている。でも著者はその気持ちを汲み、あくまで対等に接する。次男の泣き顔の写真はことばにならない思いがあふれ出していた。
出産直後の妻の笑顔、二人の子どもの寝顔。撮る側と撮られる側のおだやかな信頼感が満ちて、どの写真からもぬくもりを感じる。「よっちぼっち」とは「ひとりぼっち」が四人集まったことを表した造語だ。家族という、かけがえのない四人の「ぼっち」たち。
ろう者の父母も生まれ育った背景は違うし、その間に生まれた聞こえる二人にも個性がある。その違いを愛し、認め合う、そんな日常を描いている、これまでにない育児記だ。










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN