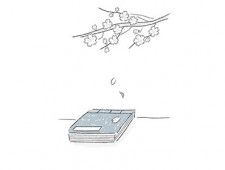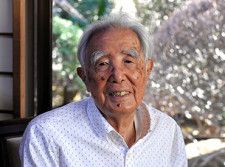詩集『若菜集』で浪漫主義詩人として名を馳せ、その後『破戒』で自然主義文学の作家としての地位を確立した島崎藤村。五七調のリズムが心地良く女性に大人気となりますが、実生活では藤村はモテませんでした。そんな藤村の恋への思いが名詩を生んだのです。
文=山口 謠司 取材協力=春燈社(小西眞由美)

新体詩を完成させた藤村
藤村の人生の大きな岐路は、大正3年(1914)、42歳の時に『桜の実の熟する時』という小説を書いたことだと思います。『桜の実の熟する時』は岸本捨吉という主人公が年上の女性・繁子との交際に破れ、その後出会った勝子という教え子との恋愛にも挫折して、関西への旅に出るという自伝的青春小説です。妻を失い、自分の姪を妊娠させた藤村が、つらい現実に耐えかねて逃げた先のフランスで書いたものでした。いったい藤村に何があったのでしょうか。今回はそこに至るまでの藤村と代表作について紹介したいと思います。
初戀
まだあげ初(そ)めし前髪(まへがみ)の
林檎(りんご)のもとに見えしとき
前にさしたる花櫛(はなぐし)の
花ある君と思ひけり
やさしく白き手をのべて
林檎をわれにあたへしは
薄紅(うすくれなゐ)の秋の實(み)に
人こひ初(そ)めしはじめなり
わがこゝろなきためいきの
その髪の毛にかゝるとき
たのしき戀の 盃(さかづき)を
君が情(なさけ)に酌(く)みしかな
林檎畑の樹(こ)の下(した)に
おのづからなる細道(ほそみち)は
誰(た)が踏みそめしかたみぞと
問ひたまふこそこひしけれ
『藤村詩抄』所収『若菜集』より「初戀」(岩波文庫)
明治の初期まで「詩」といえば「漢詩」のことでした。しかしヨーロッパの詩の翻訳から、徐々に新しいスタイルの「新体詩」が広まります。その一翼を担ったのが、『新体詩抄』という本です。
編者は東京大学教授の井上巽軒、谷田部良吉、外山正一の3人で、彼らは日本人も西洋のように普段使う言葉で詩を作るべきだという運動を起こしたのです。そんななか、漢詩では決して表現できない、日本語の詩を書いた人物が登場します。それが北村透谷でした。
しかし透谷は明治27年(1894)、25歳の若さで自死してしまいます。透谷の影響を受けて詩を作ったのが島崎藤村でした。
明治30年(1897)に出版した『若菜集』は、若い女性を中心に称賛を浴びます。先に掲げた「初戀」はそのなかでもとくによく知られている詩です。
遂に、新しき詩歌の時は來りぬ。
そはうつくしき曙のごとくなりき。(後略)
『藤村詩抄』より「自序」(岩波文庫)
明治37年(1904)に出版した『藤村詩集』(『若菜集』『一葉舟』『夏草』『落梅集』の四卷をまとめた合本)の序文で、藤村が自ら浪漫的な言葉で回顧したように、五七調の定形律に古典として杜甫や松尾芭蕉の詩境を踏まえた藤村の詩は、新体詩のひとつの完成体となったのでした。










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN