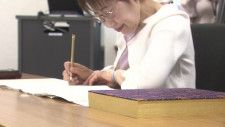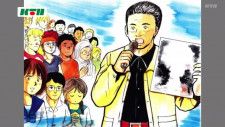長崎市郊外の中学校で平和学習 地元住民の戦争体験を紙芝居に
長崎市の中学校で平和学習の一環として、原爆をテーマにした紙芝居の発表などが行われました。
長崎市の茂木中学校では平和学習で地元の人たちが経験した戦争や原爆について学んでいます。
今回は学校の近くに住む宮本 務さんの体験を紹介しようと、生徒たちが作った紙芝居が披露されました。
紙芝居
「ピカっという閃光が走り、まもなくして昼間というのに夕方のようにあたりが暗くなり、生暖かい爆風と共に、近くの家の瓦や窓ガラスが吹き飛んだのを覚えています」
宮本さんは原爆が投下されたときは3歳で、母親や妹と一緒に爆心地から8.5キロ、当時の西彼杵郡茂木町にいました。
しかし国が定める被爆地域の外で、入市被爆を証言する人もいなかったため「被爆者」とは認められていません。
紙芝居には被爆者の認定をめぐる問題も盛り込まれています。
16日は被爆四世の大学生、大澤新之介さんも若い世代だからできる平和の発信方法について語りかけました。
鎮西学院大学 大澤新之介さん
「僕は持続可能な、今後10年、20年、30年後、被爆者の方々がいなくなったあとの社会でも、こういった平和の声を出せる人を増やしたりとか、平和について考えるきっかけを生み出そうよ、という活動をやっています」
Tシャツなどの「ピースグッズ」を作ってその収入を平和活動にあてるなど、新たな取り組みを進めています。
生徒
「稼いだお金をまた平和活動に回していく発想がいいと思いました」
生徒
「被爆者じゃなくても若い人でもやれることがあるから、私たちもできることはやっていこうと思いました」
生徒
「どんどん被爆者が減っていく中で、どうやって世界に発信していくかが一番頭に残りました」
原爆投下から79年が近づき、当時の記憶を直接、聞く機会は多くありません。
生徒たちは自分に何ができるか考えるきっかけとなったようです。










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN