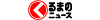昨今は「旧車」や「ネオクラシック」が人気を博していて、今となっては不便な装備も、逆にレトロ感を演出する小道具になったりします。かつてのクルマに採用されていたレトロな装備にはどのようなものがあるのでしょうか。
現代では姿を消したクルマのレトロ装備とは?
いまや、昭和っぽさが「映える」「逆に新鮮でカワイイ」と人気になる時代。クルマも、昭和や平成初期のモデルが“ネオクラシック”として人気を博しています。
そんな旧車には、現代のような完成された装備ばかりが搭載されているわけではありません。
ただし、不便さを感じる装備も、見方を変えればレトロ感を感じる装備だったりするのですが、クルマの懐かしい装備にはどのようなものがあったのでしょうか。
●フェンダーミラー
いまでもタクシーなどで見かけるフェンダーミラーもレトロ感あふれる装備のひとつ。1970年代に登場した名車と言われるクルマはすべてフェンダーミラーが当たり前でした。
顔を動かさずに視認できるメリットがある一方で、横方向を目視しないまま右左折してしまう事例が多発。
死角の多さや距離が遠すぎるなど安全性の面の課題もあり、1983年に国内でドアミラー装着が解禁になったことを受け、乗用車では装着する例が減ったと言われています。
●手動式の三角窓
三角窓とはフロントドアウインドウ前方に設けられた補助窓のことで、主に三角形だったことが名称の由来です。
今でもダッシュボードが前方に遠いミニバンや、トヨタ「プリウス」などAピラーが寝ているクルマにそのなごりが残されています。
1960年代前後は国産車にとってカーエアコンどころかカークーラー(冷気のみ)も夢の装備だった時代がありました。
そのため、夏の暑さや換気をするために取り付けられていた装備として、手動式の換気窓が装備されていました。
ただし車内のベンチレーションの進化や、安全性の観点から廃れてしまいました。
●手動開閉式のウインドウ(ウインドウ・レギュレーター)
いまでは当然のように搭載されているパワーウインドウですが、1980年代後半になるまで普及していませんでした。
それまでは高級車のみに装備される程度で、それ以外はハンドル(レギュレーター)をぐるぐる回す手動開閉式のウインドウが一般的でした。
1980年代後半からのバブル景気によって、クルマの装備が一気に電動化され、手動のレギュレーターは下火になりましたが、現在でも軽トラックなどでは手動式のモデルも存在します。
この手動式ウインドウは、バッテリーが上がっても窓を開閉することが可能なほか、構造がシンプルなので故障が少ないといったメリットもありました。
●オートアンテナ
クルマに搭載された最初のオーディオ機器はラジオでした。そしてラジオの電波を受信するために必要なアンテナも年々進化しています。
オートアンテナは1980年から2000年代前半のいわゆるネオクラシックに多く残っている装備です。
それまでの固定式のロッド(竿)アンテナに代わって、ラジオの電源と連動して自動で伸縮するオートアンテナが装備されるようになりました。
当時はセダン全盛でステータスのひとつとして人気だったのですが、ちょっとした衝撃で曲がりやすく格納できないなどのトラブルも発生したものです。
今ではアンテナはさらに進化を遂げ、フロントウインドウ上部やリアウインドウに貼り付けるタイプやシャークアンテナなどが登場しています。
●カセットデッキ
ラジオに次いで人気になったオーディオ機器がカセットデッキです。1990年代初頭までは自分の好きな曲をセレクトして収録するのが大流行したものでした。
当時のラジオはアナログで、かつ喋りの多いプログラムが中心。車内で音楽を聞きたいユーザーからカセットデッキは絶大な人気をほこったのです。
1990年代後半からはデジタル音源の普及によってその座を奪われてしまいましたが、最近のリバイバルブームで一部復活するなど、新たな魅力を感じる人も多い装備だといえるでしょう。










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN