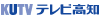4月に開校した高知県の安芸市立安芸中学校。校舎が建つ場所には以前から遺跡があることが分かっていましたが、校舎建設の際の調査で新たな発見がありました。一体、どんな遺跡だったのでしょうか。
安芸市にある2つの中学校が統合して4月に開校した安芸市立安芸中学校。

大きな時計台がシンボルマークの、木の温もりを感じるピカピカの校舎にはおよそ250人の子どもたちが通っています。学校には、遺跡広場と言われる場所があります。そう、ここにはかつて「瓜尻遺跡」と呼ばれる遺跡があったんです。

「瓜尻遺跡」は、もともと弥生時代の一般的な集落だと推測されていましたが、中学校を建設する際に行った発掘調査で、意外な新事実が発覚しました。いまで言う市役所のような建物や寺院、さらに運河が流れていた跡が見つかり、およそ1300年前=奈良時代の古代遺跡だったことがわかったのです。

いったい、どんな場所だったのでしょうか。
(安芸市立歴史民俗資料館 泉直人さん)
「一辺25mの溝と塀に囲まれた作りになっており、中には建物と井戸があります」

「推測にはなってしまいますが、身分の高い者が建物の中にいて井戸の水をくみ上げて何かしらの儀式をしていたのではないかと推測されます。今みなさんがご覧になっている景色は1300年前からほとんど変わらず現代に続いています」
文献からも、この瓜尻遺跡が重要拠点だった可能性が読み取れます。奈良時代を記録した歴史書「続日本紀」によると、土佐国の安芸郡には凡直伊賀麻呂(おおしのあたい・いがまろ)という、安芸郡で2番目に位の高い人がいました。凡直伊賀麻呂は奈良県の西大寺に稲2万束と牛60頭を献上し、見返りに貴族の身分を与えられたと記されています。

ひょっとしたら、この場所で凡直伊賀麻呂が儀式を行っていたのかもしれません。1300年の時を経て、瓜尻遺跡はいま、子どもたちが学びを深める場所となっています。
(中学3年生)
「安芸にも歴史的な建物があったがや、意外でした」
「小学生のときに遺跡があると聞いて見にきて、大きい井戸とかも見てすごいと思いました。遺跡があること自体すごいことですし、そういうところに建ってる学校もすごいなと思いました」
瓜尻遺跡から発掘された瓦や井戸枠などは、安芸市立歴史民俗資料館に展示されています。展示資料から古代に思いを馳せてみませんか。










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN