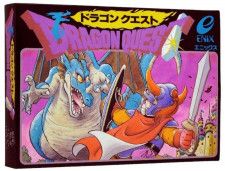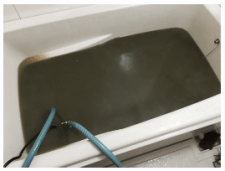早過ぎたVR、ネットワーク機器
ファミリーコンピュータやPlayStation 2、そしてNintendo Switchなど大ヒットになったゲーム機はたくさんありますが、その一方で歴史の影に隠れてしまったものもたくさん存在します。
そういったゲーム機があまり売れなかった理由はさまざまながら、ひとつの傾向として「早過ぎた」というものがあります。そう、目の付け所は悪くなかったものの、時代に合わなかった可能性があるのです。
この記事では、早過ぎたがゆえにヒットしなかったであろうゲーム機たちを振り返ります。これらも、時代が違えば大人気のゲーム機になったかもしれません。
任天堂の「バーチャルボーイ」は、日本国内で15万台しか売れなかったゲーム機として有名です。赤いゴーグルを覗き込むと、赤色LEDを活用した立体視を楽しめる、バーチャルリアリティ(VR)のはしりのようなゲーム機でした。
今でこそVRは当たり前になりつつあり、PlayStation VRやMeta Questなどで楽しんでいる人も少なくないはず。しかし、バーチャルボーイは1995年発売のため、あまりにも先駆けていました。
立体視を活かした『マリオズテニス』や『バーチャルボーイワリオランド アワゾンの秘宝』など19タイトルが発売されましたが、残念ながら勢いが出ず発売中止になったタイトルも多々ありました。
とはいえ、バーチャルボーイが完全に無駄になったわけではありません。任天堂はその後、ニンテンドー3DSで裸眼立体視を、Nintendo Switchの『Nintendo Labo』でVR対応に挑戦しています。バーチャルボーイの真っ赤な画面こそ早過ぎましたが、その後のノウハウにはなったといえるでしょう。
「ドリームキャスト」も早過ぎたゲーム機といえるでしょう。このゲーム機自体はそれなりに売れて人気もありましたが、やはりインターネットを活用した体験という意味で早過ぎました。
ドリームキャストが発売された1998年はADSLが登場する前年であり、インターネット普及率もまだそこまで高くありませんでした。先鞭をつけたといえば聞こえはいいものの、早過ぎたきらいがあります。

PlayStationにも「早過ぎたゲーム機」があった
もちろん、ドリームキャストでインターネットを楽しんだ人たちにとってはよい思い出となっているでしょう。『ファンタシースターオンライン』で仲間と冒険をしたり、『あつまれ!ぐるぐる温泉』でのんびりボードゲームを楽しんだ人も少なくないはず。2000年7月には「ブロードバンドアダプタ」が発売され、ブロードバンドを使用したインターネット高速接続サービスに対応しました。これを機にオンラインゲームデビューを果たした人も多いことでしょう。
しかし、ゲーム機においてインターネット接続が当たり前になったのはPlayStation 3やXbox 360の時代からでした。もちろん、PlayStation 2でもインターネット接続を前提としたソフトはいろいろあったわけですが、市場の成熟に先駆け過ぎていたといえます。
オンライン機能にまつわる話でいえば、「PlayStation Vita」の3G接続機能は早すぎたといえるかもしれません。
従来の携帯ゲーム機からネットワーク連携が強化された「PlayStation Vita」は、「Wi-Fi」モデルに加えて「3G/Wi-Fi」モデルも発売されました。携帯ゲーム機としてはPlayStation Portableの正統進化であり、それなりの人気もありました。
しかし、PlayStation Vitaが発売された2011年はスマートフォンがかなり普及しつつあり、3G接続機能の実装は、携帯ゲーム機としてこの流れに乗ろうとしたものと思われます。つまり、PlayStation Vitaでいつでもどこでもネットワークを介した遊びが楽しめるようなものが想定されていたのでしょう。
実際、PlayStation Vitaでは基本プレイ無料のゲームがいろいろと展開されていました。『拡散性ミリオンアーサー』や『チェインクロニクルV』、そして『みんなといっしょ』など、楽しんだ人も多いはず。
しかし、回線契約をしなければならない複雑さ、そもそもモバイルネットワークが必要なのかという疑いは払拭しきれなかったようです。
実際、現在発売されているNintendo SwitchやSteam DeckもWi-Fi接続のみです。
「PlayStation Portable go」も紛れもなく早過ぎたゲーム機です。これはPlayStation PortableのUMDドライブを省いた機種であり、要はDL版のみに対応したハードです。
今でこそPlayStation 5 デジタル・エディションやXbox Series Sなどディスクドライブを省いたゲーム機が当然のようにありますし、Steam DeckやROG AllyのようなPCゲームを遊ぶ携帯型ハードに至ってはそもそもディスクドライブが必要ありません。
ゆえに、今ならばPlayStation Portable goはアリかもしれません。しかし、このゲーム機が発売された2009年時点では「ダウンロード販売/購入」というものが市場に浸透しきっておらず、まだ時代が追いついていなかったのです。
いずれのハードも、当時のゲームユーザーのニーズやプレイ環境に合わず、斬新過ぎたきらいがあります。しかし、実装された機能は、VRやネットワーク機能など今では当たり前となったものばかりです。各ゲームメーカーの先鋭的なチャレンジが、後世に受け継がれていると見ることもできるでしょう。










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN