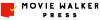安藤桃子監督が語る、東京国際映画祭の醍醐味と観客とのコミュニケーション「映画に命を吹き込んでくれる場所」
■「映画祭は、行き先を照らす“未来への羅針盤”」
世界中から優れた映画が集まる東京国際映画祭。今年の「コンペティション」部門には、114の国と地域から1942本がエントリー。厳正な審査を経た15本が期間中に上映され、クロージングセレモニーで各賞が決定する。コロナ禍を経て、世界中から映画と映画人が集う機会となるが、安藤監督は「映画祭は、映画愛にもとづいて人々が集まってくる場所。映画祭のポスターを撮影した際、“和”というキーワードが浮かんでいました。日本にたくさんの映画と人々が集って、調和をしながら、世界の行き先を照らしていくイメージですね。そして映画祭は、“未来への羅針盤”のようなものなのではないかなと感じています」と熱っぽく語る。
さらに「映画は人の心を照らしていくことができるメディアです。そしていまを生きる監督がチーム一丸となって送りだす作品は、歴史ものや未来を描くSFなど、どのようなジャンル、題材であっても、その時代を象徴するものになると感じています。コロナ禍を経て、作り手も『どこに進みたいのか』という想いや希望を込めながら、あるゴールに向かって映画を生みだしているわけですよね。だからこそ映画祭は、東京に世界中からたくさんのゲストの方をお迎えして、映画界だけではなく『これから私たちはどこへ向かうのか』ということを話し合えるような場所になる。そしてナビゲーションとは、その道を示していくことだと思っています」と自身の役割をかみ締める。
今年は生誕120年となる小津安二郎監督の特集が行われることもあり、安藤監督と奥田が並んだポスターは小津監督の代表作の一つである『東京物語』(53)にオマージュを捧げるようなイメージに仕上げられている。
この撮影では、父親と映画界についていろいろな会話することができたという安藤監督。「ポスターのビジュアル監修をしてくださっているコシノジュンコさんは、私が幼少期のころからご縁のある方でもあります。そして撮影のディレクションをしてくださった鈴木順之さんは、コシノさんのご子息でもあり、奇しくも私自身、以前から存じあげていて。いろいろな意味で、見えないバトンのようなものを感じる時間でした」としみじみ。「私たちも変化や進化をしていますが、その先にはこれからの未来を作っていく子どもたちがいる。そしてこれまでを振り返れば、映画界の先人や先輩たちがいる。そういった脈々たるものを感じました」と想いを馳せる。
安藤監督は、高校時代よりイギリスに留学し、ロンドン大学芸術学部を卒業。ニューヨークで映画作りを学び、助監督を経て2009年に『カケラ』で監督・脚本デビューした。長年映画界に身を置いている父親の姿を見てきた安藤監督にとって、映画界に足を踏み入れるのは「とても自然なことでした。物心ついた時からそばに映画があった」という。
覚悟を決めたのは、奥田が初めてメガホンを取り、連城三紀彦の同名小説を映画化した『少女〜an adolescent』(01)の撮影に参加した18歳のころだそう。「どの部署も、この仕事が好きで仕方がないという熱を込めて、撮影に打ち込んでいる姿を目の当たりにしました。想像したことが創造されてゆく!これが現場だ!現場よ、一生続いてくれ!と思うような興奮がありました」と、映画づくりのすばらしさを実感し大きく背中を押されたと回想する。
■「高知は、人間にとっての原点を感じられる場所。優しい世界の実現を目指しています」
子どもたちを対象に映画制作についてのワークショップも実施している安藤監督だが、子どもたちと接するなかでも、“映画の力”を感じる瞬間がたくさんあると続ける。
「映画は総合芸術と言われるものですから、現場に携わるうえではいろいろな役割があるもの。ある意味、映画の現場というのは社会の縮図のようで、一人一人が柱となり、輝ける場所だと感じています。ワークショップで子どもたちが映画を完成させていく過程を見ていると、どの子もものすごく輝き始めるんですよ!次第に『自分が好きなのはこういうことだ』『将来はこういうことをやりたい』と口にする子も出てきて、3日間のワークショップのなかでも大きな変化を感じることができます。こういう経験ができるのも、映画づくりや、映画の本質なのかなと思っています」。
現在は、移住先の高知で映画を中心とした文化を発信している。11月には、映画を通じて心と文化を伝える「kinema M」を高知市中心市街地にオープンする予定だ。さらに高知県での映画祭開催に向けても準備を進めるなど、精力的に映画と人をつなぐ活動に励んでいる。
安藤監督は「高知は、人間にとっての原点や、人との一体感をものすごく味わえる場所です。高知には“よさこい”がありますが、“よさこい”って全員が主役で、“前に進む”というルールからもわかるように、とてもポジティブな力を持っているもの。また高知のみんな心のなかには、坂本龍馬がいるようなところもあって。目的を果たそうとする志があって、とにかくすばらしいんですよ!」と、高知という土地からたくさんのエネルギーをもらっている様子。
そんな彼女がいますべての活動の指針としているのが、「優しい世界の実現」だ。「子どもたちと畑を耕したり、実行委員長として『高知オーガニックフェスタ』に関わらせてもらっていたりと、生物多様性や微生物を研究している人、大学の教授などと話す機会もたくさんあります。すると、『すべての命に優しい世界を実現したい』という想いが湧きあがってきて。私も過去には『もう生きていたくない』と思った経験もありますが、生命の本質というのは光に向かっていくものだと信じています。もし暗闇に植物の種を蒔いて、1ミリだけドアを開けたとしたら…。その1ミリの光に向かって、植物が伸びていきますよね。そうやって、命あるものは明るい方へ生きる方へと向かう本質的な力がある」と持論を展開。「優しい世界の実現は、映画祭でもできると思っています。映画を通していろいろな人の感性が響き合うことで、きっとそれぞれが希望に向かっていけるような意識の変化をもたらすことができるはず」と目を輝かせる。
映画祭では、あらゆる人々と対話することを楽しみにしているという安藤監督。2017年に開催された第30回東京国際映画祭では、Japan Now 部門女優特集「Japan Now 銀幕のミューズたち」において実妹で女優の安藤サクラの特集上映が組まれ、姉妹でトークショーに登壇。「映画ってすごいと思いませんか?皆さんの魂になにかをバーン!と突っ込んでくる。我々ができるのはこの道を開いていくこと」と声をあげ、会場から大きな拍手を浴びていたことも印象深い。安藤監督は「覚えています。あの時は、お客さんとの一体感がすごかった!」とにっこり。「そうやって、お客さんとコミュニケーションを取れることも映画祭の醍醐味ですよね。監督としては、自分の作品をお客さんが観てくれて、それに対して自分でも思ってもみなかった分析をしてくれて、心に響いたことを伝えてくれたりするとすごくうれしいもの。作り手は自分を知る機会にもなるし、作品もまた成長していく。そう考えると、映画祭はお客さんがさらに映画に命を吹き込んでくれる場所でもありますね」と開催を待ち望んでいた。
取材・文/成田おり枝










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN