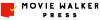『哀れなるものたち』ヨルゴス・ランティモス&衣装デザイナーらスタッフ陣が語る、作品へのあくなきこだわり
■「ベラの気づきや成長とファッションは密接に関わっています」(ワディントン)
天才外科医のゴッドウィン・バクスター(ウィレム・デフォー)が蘇生させたベラ(エマ・ストーン)は、幼児の知能と大人の身体を持ち、自らの目で世界を目撃し成長を遂げる。モノクロで始まった映像は色彩を得て、ベラの成長、開放と呼応していく。もともとは2〜3シーンをモノクロで撮るつもりだったのが、フィルムテストの際にランティモス監督がひらめき、ベラが生まれ変わり旅に出るまでをモノクロで撮り、旅に出るとカラーになる構成に変えたのだそうだ。衣装デザイナーのホリー・ワディントンが「スタッフみんな、撮影直前までモノクロで撮るシーンがあると知らなかったので、カラーでの撮影を前提に衣装をデザインしていました。そこで、ヨルゴスと一緒に衣装ルームへ行って、iPhoneのカメラのモノクロ機能を使って、どのように映るのかテストをしました。色彩のトーンを活かしたデザインが多かったので、仕様変更が必要になると思いました」と言うと、ランティモス監督は「最初はモノクロでしか映していなかったシーンも、成長したベラが戻るとカラーになるといった、視点を推移させることができます。最初はモノクロでもカラーでも撮影するので、準備したことが無駄になることもありません」と説明する。
プロダクション・デザイナーのジェームズ・プライスは、「撮影まであと1週間、全体の3/4はできあがっていたところでした。でも、やるしかなかった(笑)」と思い返し、彼のビジョンを具現化するプロダクション・デザイナーのショーナ・ヒースは、「ヨルゴスが熱心にカメラテストをしていたので、モノクロで撮ることになるだろうと気づいていました(笑)。セットデザインは、深みのある風合いを活かすように作りました。壁の質感はどんどん深みを増しデコボコになり、どこもかしこも風合いが感じられるセットになりました。魚眼レンズで撮影しているので、天井も壁のように映り込み、家の構造のインパクトが増します。実際に、天井が大きな口を開けているようで、穀物のようにデコボコした質感が体の部位のように見えてきます。ベラの部屋の壁はキルティングのようになっていて、彼女があまり傷つかないように、というバクスター博士の思いやりが感じられます」と、セットデザインについて説明していた。
キルティングの壁のように「居心地がよくふわふわしたもの」は、ワディントンの衣装デザインにもインスピレーションを与えた。ベラの気づきや成長とファッションは密接に関わっているとワディントンは語る。「幼児期の脳を持つベラの未発達な部分を表すように、シアサッカーやキルトといった、ベビー服でよく使われる生地を使いました。朝にめちゃめちゃなコーディネートの服を着ても、1時間もしないうちに脱げてしまって、大きなブルーのブラウスと下着だけになってしまう、といった子どもの生態を理屈として認識し、衣装デザインをしました。ベラが家の中で着ている、人魚のしっぽのような奇妙なコルセットは、ビクトリア朝時代の補強具として使われていたものです。それから、ベラが外出する時に着ているチーズのような色のケープは、彼女自身がヴィンテージのコンドームに包まれているようなイメージから連想しました。最初の性的な出会いから、彼女は自分が何者なのかを知る旅に出て、医学への興味を発見します。そして、自分自身で適切なスーツを着るようになるのです」。
プライスはセットデザインに関して「俳優が飛び回れるような没入感のある環境」を目指したと言う。「みなさん『女王陛下のお気に入り』はご覧になりましたよね? あの魚眼レンズというものは死角がないのです。魚眼レンズで撮ると、床まで映ってしまう。立ち位置を張ったテープとか、カーペットとか、すべてが。安い魚眼レンズを買って、自分のカメラにも装着してみました。そうしたら、オー・マイ・ゴッド! セットの窓の外を通りに見立て照明を当てると、監督やキャストが家の中に入っていくような環境を作ることができる、という最も重要なことに気づきました」
■「どうしたらこの作品を具現化できるのかと考えていました」(フェンドリクス)
特筆すべきは新進気鋭ミュージシャン、ジャースキン・フェンドリクスによるスコア。2020年発売のアルバム「Winterreise」をランティモスが気に入り大抜擢、初の映画音楽を手がけ、アカデミー賞にも初ノミネートとなった。フェンドリクスは、この映画の医学的アプローチに影響を受けたと語っている。「幸運にも、トニー(・マクナマラ)の脚本と、ジェームズ(・プライス)とショーナ(・ヒース)、ホリー(・ワディントン)によるデザイン、バイブルを手に入れることができたので、撮影開始の数ヶ月前から準備を開始できました。脚本はとても美しく、とても感動的で、どうしたらこのような作品を具現化できるのだろうと思っていました。つまり、このような映画のデザイン仕様書を想像していただけるといいのですが、動脈瘤をPDFにしたようなものです(笑)。それを見て、いわゆる通常のオーケストラによる音楽でないことはわかりました。
この映画の大きなテーマは、医療に対するある種のファンタジー的なアプローチに由来しています。だから、呼吸と人工呼吸、医療器具と実際の有機的なものとの間の未開の地のようなものについてたくさん考えました。多種の楽器を演奏し組み合わせ、シンセサイザーを使い有機的なサウンドに仕立てました。パイプオルガンやバグパイプのように、人工的な呼吸を用いて演奏する楽器も好んで使っています。さっきホリーが言っていたように、そういったものが“質感”に影響してくるのです。衣装も、生地の選択がとても魅力的で、毒性があるような、かなり気持ち悪さを感じるようなものでしたよね。僕らは弦楽器の音を大きくして、実際に聞こえるレベルの音量で質感を表しました。この映画から視覚的に栄養価の高い情報を得られたことで、音楽芸術分野で言い伝えられている音の資質を引用することができたと思います」。
リスボンでのダンスシーンにも、フェンドリクスのスコアが異色に、そして魅力的に響く。このシーンの撮影が行われたハンガリーの民族音楽家たちが参加しているそうだ。フェンドリクスは、「撮影中、ヨルゴスのリアリズムへのこだわりはかなり大きな部分を占めていました。音楽はすべてカメラの前で生演奏され、撮影現場ではみんなそれに合わせて踊っていました。実際の環境に身を置くことで、俳優たちも自由に動くことができるようになるのです」と証言する。ランティモス監督は「ダンスシーンの撮影は複数のカメラを使って2日間に渡って行いました。俳優陣にとって、短いけれどかなり疲弊した撮影だったと思います。彼らはずっとダンスのリハーサルを繰り返していました。マーク(・ラファロ)は、自分が最高のダンサーであることに疑念を抱いていて、自信なさげでした。彼のダンスは、本当に最高でかなりおかしかったと思うんですが」と、助演男優賞にノミネートされたラファロの隠れた資質を賞賛する。
各映画賞に該当カテゴリーがあるわけではないが、ランティモス監督は映画を支えたスタッフの中で、特にインティマシーコーディネーターのエル・マカルパインと、プロデューサーのエマ・ストーンに多大なる感謝を述べていた。このイベントが行われたのは俳優組合のストライキ中で、ランティモス監督は「エマと私は、脚本からわかるように、ベラのキャラクターに忠実に、インティマシーシーンも大胆にやるべきだとわかっていました。映画の中で、セックスシーンをほかのシーンと同等に扱わないのはとても不誠実だと思います。ベラがたくさんの男性を部屋に招き入れてセックスをするシーンについて、しっかり議論をしました。どんなシーンになるのか、どんなふうにセックスするのか、どんな体位があるのか、なにを見せるべきか、なにを見せるべきでないのか。すばらしいインティマシーコーディネーターのエルに手伝ってもらい、このシーンのためだけに半日だけ撮影に参加する役者たちが居心地良く撮影に臨める雰囲気を作る、というような助けをしてくれました。インティマシーシーンの撮影は、撮影監督のロビー(・ライアン)が自らカメラを操作しレンズを交換し、僕とエマと3人だけで行いました。時には音声技師も外していたくらいです。お互いに信頼できる相手と、親密な関係を作り撮影を行いました」と、登壇できなかったエマ・ストーンに代わり撮影において最も重要な役目について語っている。
『哀れなるものたち』が観客ひとりひとりに多大なる気づきを与える映画になったのは、ランティモス監督が掲げる映画哲学にある。ジェームズ・プライスは、「ヨルゴスは『過ぎ去った時代の技術と最新技術を融合させてこの映画を作りたい』と言っていました。彼の勇気と狂気に感謝します。彼にとってかなり大きく大切な今作において、僕らみんなにチャンスを与えてくれたのはまさに狂気の沙汰ですから」と、独特な言い回しで誉め讃える。ランティモス監督はこうまとめる。「私が映画を作る時にいつも念頭に置いていることのひとつは、観客が自由に受け取れるように、具体的で緻密な作品を作るということ。しかし同時に、観客の解釈や鑑賞体験に対してもオープンであるべきで、それぞれの心境やあらゆる文化的な経験値を持つ人々が映画の中に入り込む方法を見つけ、自分が受け止めたいものを見つけてくれることを願っています。それが、私たちが映画を作る理由だからです」。
文/平井伊都子










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN