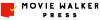「五臓六腑で体感してほしい」ブランドン・クローネンバーグ監督が語る『インフィニティ・プール』の裏側
■「曖昧さから解釈と議論が生まれることに、重要な価値がある」
ジェームズの心に棘となった、この処女小説の題名「変わりゆく鞘(The Variable Sheath)」がまず、意味ありげでおもしろい。「Sheath」は主に刀を収める「鞘」(転じてコンドームを指すことも)だが、日本語に訳すと豆の「鞘」と同じ言葉になる。ここで侵略系スペースホラーの名編『SF/ボディ・スナッチャー』(78)を連想するファンも多いだろう。あの映画では、人間のコピーを生みだすべく、宇宙から巨大な豆の鞘(Pods)が飛来してきた。そもそも、この小説は一体どんな内容なのだろう。
「劇中にはタイトルしか登場しませんが、夫婦関係に悩む泌尿器科の医者の物語でした。実際に僕が執筆して、800頁くらいの小説に仕上げたんです。出版の予定はないですけどね」。いままでも過去の短編映画や小説など、自身の習作を数年間煮詰めて長編映画化してきたクローネンバーグ監督。もしかしたら、今後「変わりゆく鞘」がなんらかの作品として不思議な実を結ぶかもしれない。
主人公のジェームズはこのリゾートで予期せぬ異常体験をする。ここでは大金を払えば自身のクローン製造が可能で、どんな罪も分身が贖えばいい。批評によって文壇から「抹殺された」彼はある罪で逮捕され、実際に自分が「処刑」される現場に立ち会う。この体験は一種の型破りなセラピーにも思える。
「僕もメタクソに叩かれた経験がある。どの作品かは伏せますが」と監督は笑う。「ただ、個人的な実感として、批判されたくらいでは死にませんよ。でも、ジェームズは迷子の状態だから、確かに強烈な衝撃を受けたはずです」。
物語が進むにつれて複数のクローンが登場し、オリジナルと区別がつかないサスペンスが生まれる。しかし、映画は誰が本物なのかを積極的には示さない。ラストの解釈は複数のジェームズと、彼が大事に保管する骨壺の数がヒントになるのだろうか。「僕自身が決めた結末はありますが、明確な回答は避けます。曖昧さから自由な解釈と議論が生まれ、さらなる思索を促す。そこに重要な価値があると思うんです」。
■「ミア・ゴスは限界を突破する度胸を持ちながら、微妙なニュアンスも表現できる」
本作の魅力の一つがクセモノ揃いの俳優陣。悩み多きジェームズ役で体当たりの熱演を見せる『ノースマン 導かれし復讐者』(22)のアレキサンダー・スカルスガルドを筆頭に、誰もがすばらしい存在感を発揮しているが、やはり圧巻はワイルドなミア・ゴスだ。彼女は罪を巡る物語のなかで欲望のままに行動し、受け身のジェームズを混沌の泥沼に導く悪魔的な“運命の女”である。
「ミアはエモーショナルな役者で、カメラの前で限界を突破する度胸を持ちながら、微妙なニュアンスも表現できる」と監督は絶賛。特に怖気づいたジェームズを挑発する場面では、感情を高めるウォーミングアップの時間を作り、芝居が爆発寸前となる頃合いで本番に臨んだ。
「もう、好き放題にやってもらいました。過激すぎたら編集でカットすればいいので」。その結果には監督も大満足。ただ、どんなに暴走してもカットの声がかかれば普段のミアに戻る。「素顔の彼女はとても礼儀正しい人ですよ」と、付け加えてくれた。
■「脳からあふれる感情を、五臓六腑で体感してもらいたい」
そんなミアが捕食者のように、ジェームズと初めて肉体的な接触を持つ場面は度肝を抜かれること確実だ。「日本では修正されてるの?」と監督も興味深そう。「ボカシは仕方ないけど、男性器は作り物ですよ。特殊効果のダン・マーティンはさまざまな映画にシリコン製の男性器を提供している性器作りの達人で、彼の部屋のクローゼットには男性器がゴロゴロしまってあるんです」。
クローネンバーグ監督の周辺には独創的な作家が集っているようだが、撮影のカリム・ハッセンも、カルトな監督作『大脳分裂』(00)で知られる異才だ。デビュー作の『アンチヴァイラル』(12)以来、ずっと組んでいる彼をクローネンバーグ監督は“マッド・ジーニアス”と呼ぶ。2人は撮影に入る前に視覚言語を踏まえたショットリストを作りつつ、何か月も映像実験に没頭する。これが楽しくてやめられないそうだ。その成果は本作の後半に展開する幻覚シーンで存分に発揮されている。
また、本作ではジェームズの脳の処理能力を超えて、暴力の衝撃が襲ってくるので編集のカッティングは素早くした。一方で『ポゼッサー』(20)の主人公は暴力にどっぷり漬かった殺し屋なので、バイオレンス表現には中毒性と官能的なニュアンスをこめた。「登場人物の体験をそのままダイレクトに味わってほしい。感情が脳からあふれるのを主観的に表現し、五臓六腑で体感してもらいたいですね」。
脳内から肉体へ、イメージからフィルムへ。頼もしい共犯者たちと共に、無限の創作欲を探求するクローネンバーグ監督の旅はまだまだ続きそうだ。
取材・文/山崎圭司










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN