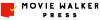高山一実&結川あさきが『トラペジウム』に掛けた想いを告白「“夢を持てない人”に寄り添いたい」
■「結川さんの第一声を聞いた瞬間に、監督と無言で頷き合いました」(高山)
――高山さんは、キャストオーディションにも立ち会われたそうですね。アイドルを目指す高校生、東ゆう役に、結川さんを抜擢された際の決め手とは?
高山「それが、オーディション会場に入ってきた瞬間からすでに、「(東ゆうは)この子かも!」というオーラを、結川さんが放っていたんですよ」
結川「うれしいー!」
高山「声優さんのオーディションに立ち会うのは初めてだったのですごく驚いたのですが、ブースに入った直後に、『はい、どうぞ!』って始まるんですよ。結川さんは第一声を聞いた瞬間に私と監督さんとで顔を見合わせて『うん』って無言で頷き合いました』
結川「本当ですか!?」
高山「声についてはキャラごとのイメージがそこまで固まっていたわけではないのですが、直感的に『この人がいい!』と思えた皆さんに、“東西南北”(『トラペジウム』に登場する、東ゆうを筆頭とした4人組アイドルグループ)の声を入れていただきました」
■「アフレコ中は、本当に女子高校生が4人集まったかのような雰囲気でした」(結川)
――結川さんは、オーディションにどんな意気込みで望まれたのでしょうか?
結川「テープ審査のあと、スタジオオーディションだったのですが、当時の私はスタジオオーディションの経験が少ないうえに、歌のオーディション自体初めてだったので、右も左もわからないような状態で…。悩み始めるとドツボにハマるなと思ったので、ファーストインプレッションのままに。歌もセリフもその時の自分の精一杯を出し切りました!」
高山「私が求めていたのは、まさに結川さんのような“ガムシャラさ”だったので、逆に結川さん自身もご経験が浅いところも、ゆう役にめちゃくちゃハマったんですよ。でも、あの歌い出す瞬間は、さすがに緊張しますよね(笑)?」
結川「それはもう…!何回かリハーサルをするものだとばかり思っていたら、『結川さん、聞こえますか?』『はい。聞こえます!』『じゃあ、スタート!』って言われて、内心動揺しまくっていました(笑)。いまとなっては、まさにあの必死さこそが、東ゆうとして正解だったのかな、とも思いますが、あの時は本当に緊張してました」
高山「しかも、オーディションの時っていわゆるデモ音源がないんですよね。私が乃木坂46時代にレコーディングをしていた時は、ほとんどが仮歌を聴きながら歌うものだったので、仮歌がない状態で歌われている皆さんの歌声が、もう本当にすごすぎて…!」
――その後、本番で声を収録された際は「東西南北」のメンバーの皆さんとご一緒に?
結川「はい。皆さんとは収録の場で初めてお会いしたのですが、まさに『最強の4人だ!』って期待感が高まりました。アフレコ中もすごく和気あいあいとした雰囲気で、本当に女子高校生が4人集まったかのような雰囲気で(笑)。皆さんとご一緒できて、たくさんのことを学ばせていただきました」
高山「結川さんはセリフも多くて大変だったと思うのですが、皆さんプロフェッショナルだから、2日間くらいであっという間に録り終わってしまったのが、私的にはちょっと寂しかったです。お弁当選び一つとっても『どれにしよう?』って選んでいる時の、『どれにしよう〜?』の声が可愛くて…(笑)。もっとあの4人のやりとりを見ていたかった!」
■「ゆうの怒り方が絶妙で、好感度が下がらないところも、原作者としてはありがたい…」(高山)
――お2人のお気に入りのシーンを挙げるとしたらどこになりますか?
高山「私はゆうが東西南北のメンバーの華鳥蘭子に、『そんなのおかしいよ!』って、激しい怒りをぶつける場面が、特に好きですね。ああいう風な怒り方って、まさに高校生ならではのものだと思うし、しかも結川さんの怒り方が絶妙なんですよ。めちゃくちゃ怒っているのに、どこか可愛さが残っているから、思っていたより、ゆうの好感度が下がらないところも、原作者としてはありがたくて…(笑)」
――結川さんは、その場面を演じた際のことを覚えていますか?
結川「はい。もちろんハッキリ覚えています。自分の人生において、あそこまで本気で怒ったことがなかったので(笑)。女子高校生が全力で叫んだ時って、どんな感じになるのかなって考えたりもしたのですが、結局はいまの私で表現する精一杯の声で、ちょうどよかったみたいです(笑)。ゆうが本気であるからこそ、あの怒りに表れているのかなと思いつつ、あのシーンはメンバーの関係に暗い影を落とすシーンでもあったので。怒りながら胸がすごく苦しくなった記憶があります」
――では、結川さんのお気に入りのシーンはどこでしょう?
結川「たくさんありすぎて選び難いのですが、『このままだと東西南北がまずいぞ』みたいな状況になった時に、滅多なことでは落ち込まない性格のゆうが、その時ばかりは珍しく塞ぎこんで、『私ってさ、イヤなやつだよね…』って、お母さんに弱音を吐く場面が特に印象に残っています。『そういうところも、そうじゃないところもあるよ。ゆうには』というお母さんの言葉が、私にはすごくあったかくて、すごく愛のある厳しい言葉に感じられました。あのシーンを観ると、いまでもちょっとグッと来るものがあります…」
高山「うれしい…」
■「小説版より、確実におもしろいものになっていると思っています」(高山)
――小説をアニメ化されるうえで、新たにキャラクター造形が必要になると思うのですが、高山さんが小説を執筆された際は、どこまで具体的にキャラを思い浮かべていたんですか?
高山「それぞれのキャラクターの性格は、自分なりの明確なイメージがありましたけど、映像化するにあたってさらに深掘りしていく必要があったので、スリーサイズから、靴のサイズ、血液型や誕生日、家族構成に至るまで、一つずつ考えていきました」
結川「確かに、オーディション用の資料にもキャラ設定がかなり細かく書いてあった記憶があります。『東ゆうは、○○に影響を受けている』『ゆうの憧れの人物は、○○』みたいな感じで」
――そうだったんですね。高山さんは、アニメ化について率直にどう感じていますか?
高山「本当に、光栄すぎる!という気持ちでいっぱいなんですが、4年近い歳月をかけて皆さんと作り上げてきた作品を公開するにあたって、正直、不安要素も少しあって…」
――どのような不安ですか?
高山「小説を買って読んでくださる方は、私を応援してくださるファンの方々も多かったと思うのですが、本作に触れていただく方はおそらくもう少しカジュアルな層になってくる。となると、また受け取り方が変わりますよね。スタッフの方と小説版からさらにいろいろな要素を加えてグレードアップさせたことで、自分としては確実におもしろいものになっていると思っているからこそ、もしこの映画をご覧になった方々が『おもしろくなかった』と感じたら、自分の価値観が世の中と解離していることになるので。その事実に直面するのは悲しいなと思っていて。そこはちょっと不安ですね」
――世間の反応とご自身の感覚にズレがないかどうか、不安だと。
高山「そうなんです。私のなかには、『これからもクリエイティブにかかわるお仕事を続けていきたい』という切なる想いがあるので。たとえ、自分にとってそれがどれだけ耳が痛いことだったとしても、世の中の声には敏感にセンサーを働かせておかないわけにはいかなくて…」
――なるほど。創作や表現に真摯に向き合っているがゆえに、湧き上がる不安ということですね。結川さんは、高山さんが執筆された原作小説のどんなところに魅力を感じていますか?
結川「知られざるアイドルの世界の裏側や、アイドルを目指す過程がここまでリアルに綴られている小説は、なかなかないなと感じました。私が演じた東ゆうを始め、登場人物たちが使う言葉や感情が、いい意味で取り繕っていない、高校生たちのリアルがそのまま描かれているので、感情移入しやすいうえに、世界観にも入っていきやすい。アイドルというキラキラしたものと、まさに青春真っ只中にいる高校生たちの少し青い感じが、いい具合に折り重なって入っているところが魅力だなと思います。アニメでも、高山さんを筆頭にスタッフの皆様がものすごい熱量で作られていて、目にするたび圧倒されています。完成版を観てくださる方たちもきっと心動かされるものがあるはずなので、先程高山さんは心配されていましたが、絶対に杞憂に終わると私は思います!」
高山「ありがとうございます!!」
■「ゆうみたいに、“やれることは全部やってみる”体当たり精神がなにより大事」(結川)
――ちなみに、高山さんが思い描く“アイドル像”というのは、本作で東ゆうがアイドルに求めているイメージと近いですか?
高山「実は、『トラペジウム』を執筆する前は、いわゆる“アイドルの定義”みたいなものが、自分のなかでまだ定まっていなくて。書きながら見えてきたらいいな、くらいに考えていたんです。実際に小説を書きあげて、グループを卒業したいま、私のなかでようやく見えてきたアイドル像は、ゆうの掲げていたものとは少し変わってきましたね」
――具体的にどのような変遷を辿られたのでしょうか?
高山「プロットの段階では、1回挫折を味わわせてから、改心する流れにしようと考えていたので、最初はゆうをもっと嫌われる要素の強い子からスタートさせようと思っていたんです。でも最終的にゆうにはアイドルとして成功してほしいから、『根っから悪い子だと成功しないよな』と思い直して逆算して作った結果、『彼女みたいな子が実際にいたら、本当にトップアイドルまで登り詰めるんじゃないか』と思えるような子になりました」
――なるほど。結川さんは、ゆうに共感する部分はありましたか?
結川「叶えたいものやなりたいものがある人は、その想いが本気であるがゆえに、ゆうと同じように、周りが見えなくなったり、空回りしちゃったりすることもあると思うんですよ。でも、本気にならないと見えてこないものも、世の中にはたくさんあって…。自分の心のなかになにか強い想いがあるのなら、周りとぶつかることを恐れずに、ゆうみたいに“やれることは全部やってみる”体当たり精神がなにより大事なんだなってことを教えてもらった気がしています」
■高山が考える”アイドルになれる条件”
――では、改めて本作を通じて辿り着いた、お2人にとってのアイドルの定義とは?
高山「“可愛い”“誠実である”“爆発力がある”…もしくは、“それらすべてに憧れている”という4項目のうち、2つ以上に当てはまる子なんじゃないかなと思っています。可愛くなくても、アイドルに憧れて、誠実であればなれると思うし、可愛くて爆発力さえあれば、誠実じゃなくても、別に憧れてなくてもイケると思うんですよね。それが、私のアイドル論。結果的にその条件に当てはまっている東ゆうは、すばらしいアイドルだったなと思います」
結川「説得力がすごい!私はアイドルの経験はないので、あくまで自分から見たアイドル論になるのですが、一言でカッコよく言うなら、“愛さずにはいられない存在”でしょうか。歌やダンスが上手というのももちろん魅力の一つだとは思うのですが、できないところさえ愛おしく思えるからこそ、あんなにもアイドルを好きになるんだろうなとも思います」
■「アイドルという職業自体が、光を放つものだと思っています」(高山)
――ポスターのキャッチコピーにも採用されている、「はじめてアイドルを見たとき思ったの。人間って光るんだって」という、ゆうのセリフがとても印象的で…。応援するファン1人1人の小さな光が集まって、アイドルを輝かせているのか。それとも、そもそもアイドルとしてデビューする前から、人は光っているものなのか。お2人はどうお考えですか?
高山「『トラペジウム』を書く前に、私が『人って光るんだ!』と明確に思った瞬間は、ライブのステージ上でガムシャラに踊っているアイドルと、それを客席から応援しているファンの方たちがいらっしゃって。その会場を斜め上からねらっているカメラの映像を見た時なんです。特定の誰かを見て思ったというより、ステージで踊っているアイドルがちょっと引きで映った時に、そこにいる全員がみんなキラキラして見えて。アイドルって光るんだ!って思ったんです。光って見せるためにはきっと素質が必要だけど、私はそのアイドルという職業自体が、光を放つものなんだと認識した記憶があって。ファンの方によってアイドルは光るものだとも思うけど、そもそも1人1人のアイドルも、光る要素を持っていないと、ファンの方に光らせてもらえないんじゃないかなと思っています」
――いまのお話を聞いて結川さんはどう感じました?
結川「深いなあって思いました。やっぱりアイドルって、普通の人とは決定的になにかが違う気がします。舞台の上で歌って踊っている女性や男性を、みんなで盛り上げている図って、冷静に見るとちょっと特殊だったりするじゃないですか。それでもなぜみんなあんなに熱狂するのかというと、ステージの上にいる1人1人が、すごく本気だからなのかなと。内に秘めている熱い想いとか、いろんな輝きを纏っていて。アイドルという存在になった瞬間、それらが一気に放出されるから、あんなにも輝いて見えるのかなって。でも、今回の作品を通じても答えが見つからず、未だに考えあぐねているような状態だったので、いまの高山さんのお話を伺って、腑に落ちました」
■「夢は、1個叶えたら終わりじゃなくて、ずっと続いてくもの」(結川)
――夢や叶えたいものがあるからこそ、アイドルは光っているのかもしれません。お2人にとって、いま思い描く新たな夢はありますか?
高山「いやあ、それが困ったもので…。新たな夢を抱くのって、意外と難しいんですよ。それこそ、年齢的なものなのか、時代的なものなのかよくわからないのですが、私の夢はアイドルになることだったから、夢って、人生で何個も持てるものではないんだなということを、身をもって知れたことはよかったなとは思います」
――まさに、夢を叶えた人にしか言えないセリフですね。
結川「本当に!」
高山「そう考えると、本当にありがたい話ですよね。というのも実は、アイドルだった時からすでに私にはこうなる未来が見えてはいたんですよ。だからこそ、悔いなくやり遂げようと思っていて。それで、実際にアイドルをやめてみたら、案の定、次の夢が見つからない…」
――どこか、“燃えつき症候群”のような?
高山「そうですね。でも、悲しいというよりも、本当に大きな夢が叶ったからこそ一区切りついたというか。第1章が終わったな、と思っていて。ここから先は、自分の夢のためにではなく、誰かの夢のために生きるのもいいのかもしれない。実はいろいろと考えている真っ最中なんです。大切な人のために生きる、友人のために生きる、あるいは見ず知らずの誰かのためや、地元のために生きる…とか。選択肢はきっとほかにもあると思いますし、どれか一つに限定する必要もないとは思うのですが…。いまの私の正直な気持ちとしては、まだ迷っていて。それこそ、『トラペジウム』を書いた時は、いま夢を持っている人の背中を押すようなものにしたいと思っていたのですが、いまとなっては、夢ってそう簡単に浮かぶものじゃないよなって。むしろ“夢を持ちたくても持てない人”に寄り添いたい気持ちがあるんですよね。そういう方たちと『夢、欲しいよね』って、語り合いたい」
――結川さんは、どう感じましたか?
結川「私が感じているのは、逆に『夢って、叶ったらそこで終わりじゃなくてずっと続くんだな』ってことなんです。これまで携わらせていただいた作品についてもそう感じていますし、これから『トラペジウム』 が公開されて、私自身がこの作品に直接かかわる機会が少なくなったとしても、いまこうして高山さんと一緒に取材を受けていることも含めて、私はこの作品を通して本当にいろんな経験をさせていただいたので。きっとこれからもこういう時間を思い出して、大切な作品たちを抱えて歩んでいくんだろうなって思うんです。そのことが、私にはとてもうれしく感じられていて。自分が夢のためにそれまで頑張ってきたことや、夢を叶えて得たものは、絶対に消えてなくなったりしないはずだよなって。だから、夢って1個叶えたらそこで終わりじゃなくて、ずっと続いてくものなんじゃないかなって…。なんだかちょっと大人びた視線で、夢について考えたりしています(笑)」
高山「うわあ、すごい…!しかもそのステキな言葉を、東ゆうが結川さん越しに私自身に語りかけてくれているような、そんな不思議な感覚になりました。なんか、鳥肌が立ってきた!」
結川「でも今回、こんなにステキな作品と出会えたことで、『私のこれからの人生は、絶対明るいものになる!』って本気で思えたので。出会って、収録して終わりじゃなくて。出会えたからこそ、この『トラペジウム』という作品が、今後の私の糧になってくれるんだろうなって。いま、高山さんとお話ができたことで、さらにその想いが強くなりました!」
取材・文/渡邊玲子










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN