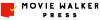『蛇の道』柴咲コウのフランス語力に西島秀俊が驚き!「相当な努力をされる方」
愛娘を何者かに殺されたアルベール・バシュレ(ダミアン・ボナール)が、パリで働く日本人の心療内科医、新島小夜子(柴咲)の協力を得ながら犯人探しに没頭、復讐心を募らせていく姿を描く本作。
アルベールの復讐に協力する小夜子役を演じた柴咲は、フランス語の厳しいレッスンに臨み、現地で実際に生活をしてパリで暮らす謎多きヒロインを自分のものにした。黒沢監督は「動きがすごいです。獰猛というか」と柴咲を絶賛。「『バトル・ロワイアル』を超えたんじゃないかと思う」と柴咲の出演作をあげつつ、「柴咲コウってこんなに動けるのと。肉体のものすごさは必見に値すると思います」と称えた。柴咲は「蛇のようなしなやかさ。サササー、パクッ!みたいな感じですかね」とちゃめっ気たっぷりに語り、会場を笑わせていた。
心を病んだ小夜子の患者・吉村役を演じた西島は、スタッフともフランス語で話している柴咲の姿を見て「あ、フランス語を話せる方なんだなと思った」と語る。「そうしたらこの作品のために勉強をされたと聞いて、本当に驚いた。相当な努力をされる方なのかなと思っています。セリフも、僕から聞くと本当にナチュラルに話されていた。現場にも馴染んでいた」と感心しきり。小夜子の夫、宗一郎に扮した青木も「佇まいが、ずっとパリで生活をしている女性像になっていてすごく驚きました。立ち姿が美しかった」と証言した。
「フランス語は話せなかった」と打ち明けた柴咲は、「クランクインの半年くらい前から練習できるようにとお願いをしたんですが、なかなか日取りが合わなかったり、不定期になって、ちょっとずつ練習を開始して。クランクインの3か月くらい前になって、『このペースでは間に合わなくない?』と焦り始めて、ものすごく集中して取り組んでいった」と振り返り、「フランス映画として取り組む作品なので、『聞き心地が悪いね、この日本人のフランス語』と思われるのは絶対に嫌だった」とストイックな姿勢を吐露。さらにクランクインの1か月くらい前からはパリでの生活を始めたそうで、「アパートを借りて、自炊をしながら、マルシェで野菜を買って、とぼとぼ歩きながら玄関の扉を開け、キッチンで料理を作るというのを毎日重ねて、1か月かけて馴染んでいきました」とパリで長年暮らしている女性像を、身体に染み込ませていったという。
またステージでは、本作が“徹底的な復讐劇”であることにちなみ、それぞれが「リベンジしたいこと」を告白する場面もあった。柴咲は「いつも、昔の自分に対してバカ!と思うことが多い。でもそれを乗り越えるしかない。あの時に失敗したな、しくじったなと思った態度を改めたり、大人になって作法を学ぶとか、そういうことの繰り返しなのかなと思います」としみじみ。
「いま演じている役が体重を落とさないといけない役」だという西島は、「甘いものを3か月くらい食べていなくて、現場で『甘いものを食べないんですね』と言われて悔しい思いをしている」と嘆き節。「あと1日で(撮影が)終わるので、終わったらドーナツ、ケーキとかいろいろ食べたいなと思っています。なにから食べようかなと、そのリベンジを考えています」とスイーツ好きな一面を披露して笑いを誘いながら、「プリンも食べたいし、みたらし団子、マカロンもいいですね。カロリーの高いものを食べたいと思います」と夢を広げていた。青木は「柴咲さんの今回の役への向き合い方についてお話を伺っていて、佇まいというのは必要なんだなと思った。だいぶ前からしっかり準備して、その土地に入ることは重要だなと思った。しっかり前のりをしようかと思う。特に海外ロケは、どんな数シーンであっても1か月、2か月は前乗りして生活したい。その場合、パリ以外もいろいろ行っちゃうかも」と笑顔をのぞかせていた。
最後に黒沢監督は「ダミアン・ボナール、マチュー・アマルリック、グレゴワール・コラン、スリマヌ・ダジなどフランスで有名な、癖のある強烈な俳優たちが次から次へと出てきます」と紹介し、「一癖も二癖もある強烈な彼らのなかで、柴咲コウがどのように立ち回り、彼らをどのように手懐け、彼らをどこに連れて行くのか。いまここでしゃべっていらっしゃる柴咲さんとは全然違う、もうひとつの恐ろしい柴咲コウが見られると思います」と熱を込め、拍手を浴びていた。
取材・文/成田おり枝










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN