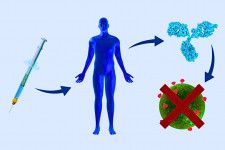私たちは日々、頭の中で自分と会話をしています。これは「内なる声」と呼ばれ、私たちの思考や行動に大きな影響を与えています。
しかし、驚くべきことに、人口の5〜10パーセントはこの内なる声を持たない「無内言症(anendophasia)」という状態であることが近年の研究で明らかになりつつあります。
デンマークのコペンハーゲン大学(UCPH)で行われた新たな研究では、内なる声を持たない人々は単語の記憶力が低く、タスクの切り替えなども普通の人とは異なることが示されました。
こうした症状を初めて聞いたという人も多いでしょうが、無内言症の人々の日常生活や思考プロセスはどのようになっているのでしょうか?
研究内容の詳細は2024年5月10日に『Psychological Science』にて発表されました。
目次
- 「内なる声」なしで生きる人々がいる
「内なる声」なしで生きる人々がいる
内なる声、または内言(inner speech)は、私たちが心の中で行う自己対話のことを指し、他人とコミュニケーションをとるために発する言葉は「外言」として区別されています。
マンガにおいては「吹き出し」として表記される言葉が外言、心の声(モノローグ)として記載される部分が内言と言えるでしょう。
認知科学において内言は計画、問題解決、自己反省、感情の調整など、多くの認知活動に関与し、私たちが日常生活で意思決定を行い、感情を整理し、社会的状況に適応するのを助けてくれていると考えられています。
また、外国語をコミュニケーションに使用するためには、一定期間内なる声を用いて練習する必要があり、この内なる声が効果的に使えるようになって初めて、第二言語の習得が進むと言われています。
これまでの内なる声に関する研究でも、内なる声は前頭前野と側頭葉の特定の領域で生成されることが示唆されています。
これらの脳領域は、言語処理や実行機能に関連しており、内なる声が思考と言語の交差点に位置することを示しています。
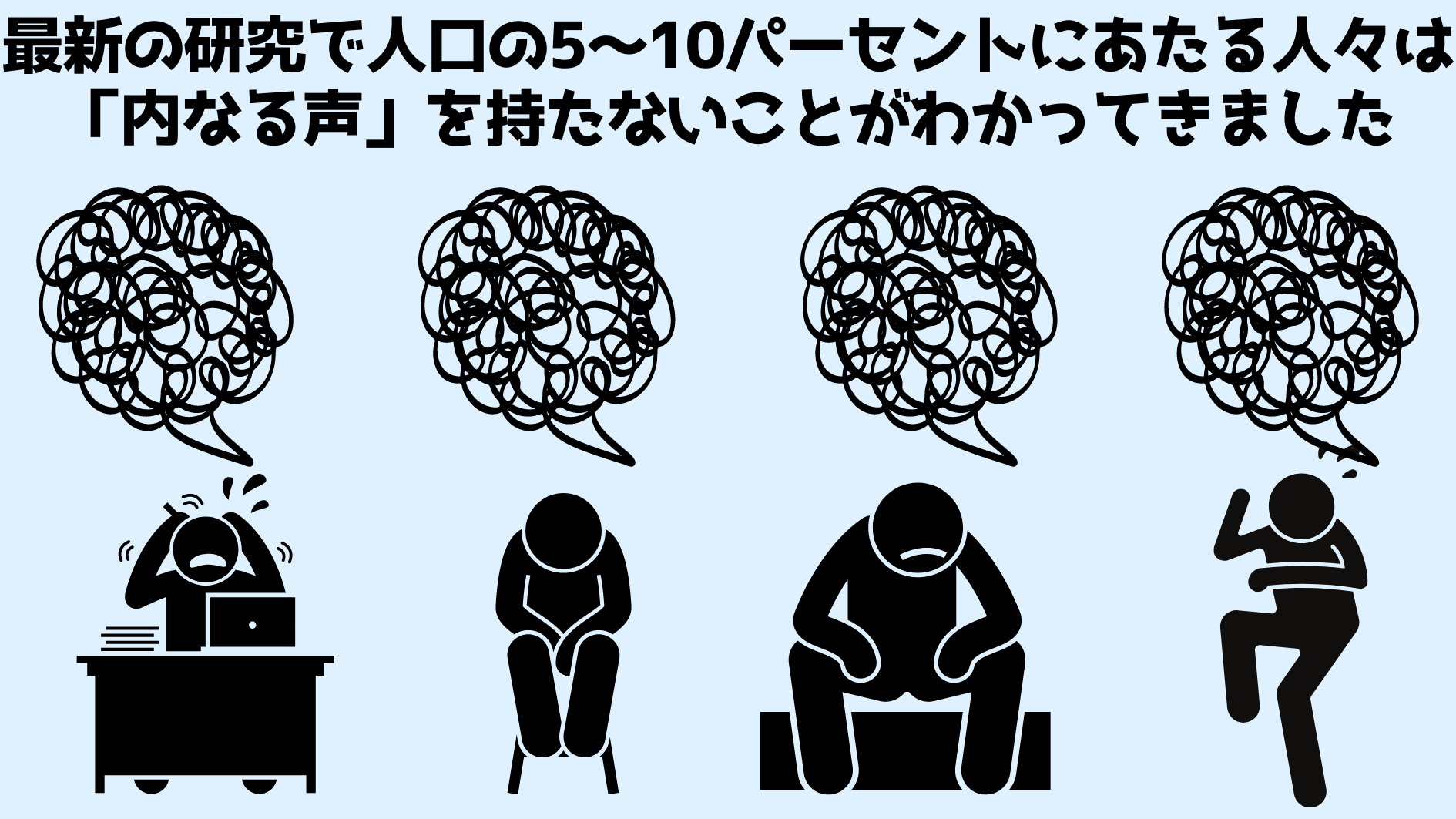
しかし最新の研究では、人口の5〜10パーセントはこの内なる声を持っていない「無内言症(anendophasia)」の状態にあることがわかりました。
また無内語症の人々は、内なる声を持つ人々とは異なる方法で情報を処理していることが示されています。
たとえば、内なる声を持たない人々は、視覚的なイメージや感覚に頼ることが多く、しばしば「言葉で説明することができず絵を描いて説明する」というパターンがみられます。
そこで今回コペンハーゲン大学の研究者たちは、内なる声の欠如が問題解決能力に与える影響を調べることにしました。
最初の実験では、参加者が「はなび」「はなみ」「はなぢ」「はなれ」など、音声的にも綴り的にも似ている単語を順番に記憶しました。
研究者たちは「これは誰にとっても難しい課題ですが、内なる声を持っていない場合、頭の中で自分に言い聞かせる必要があるため、さらに難しいのではないかというのが私たちの仮説です」と述べています。
実験結果から、内なる声を持たない人々の単語記憶能力が著しく劣っていることが示されました。
同じことが、参加者が絵に韻を踏む単語が含まれているかどうかを判断する課題にも当てはまりました。
たとえば、「ふくろ」と「ふくろう」の両方が書き込まれている絵などです。

内なる声を持つ人は絵から簡単に「ふくろ」と「ふくろう」を選び取るすることができました。
しかし内なる声がない人々は音や韻を比較して判断するのに苦労していることが示されました。
一方で、異なるタスクを素早く切り替えたり、似た図形を区別したりする際に内なる声がどう役立つかを調べた他の2つの実験では、内なる声がある人とない人の間に違いは見つかりませんでした。
以前の研究では、こうしたタスク切り替えや図形の区別でも内なる声が重要な役割を果たすことが示されていましたが、これら2つは成績には反映されなかったのです。
研究者たちは「内なる声を持たない人は別の方法を学んでいる可能性がある」と述べています。
実際、研究では「タスクごとに異なる指を使う」といった工夫をしている人もいました。
たとえば、絵の中から猫を選ぶタスクでは人差し指を使い、犬を選ぶタスクでは中指を使うなどです。
このような指の変更に頼ったタスク切り替えは、内言能力があるひとではあまりみられませんでした。
実験で判明した言語記憶の違いは、日常会話ではほとんど気づかれません。
しかし、内なる声の存在が実際的な行動や感情の調整、問題解決のスタイルにどう影響するかは重要なポイントです。
たとえば認知行動療法では、有害な思考パターンを特定して変更する必要があり、そのようなプロセスでは内なる声を持つことが非常に重要になる可能性があります。
内なる声を持たない人々の認知行動療法の効果を調べることができれば、個人に適した治療法の開発が進むと期待されます。
研究者たちは「研究が進むにつれ、内なる声を持たない人々がどのように独自の方法で生活を営み、問題を解決しているのかが明らかになってくるでしょう」と述べています。
参考文献
People without an inner voice have poorer verbal memory
https://humanities.ku.dk/news/2024/people-without-an-inner-voice-have-poorer-verbal-memory/
元論文
Not Everybody Has an Inner Voice: Behavioral Consequences of Anendophasia
https://doi.org/10.1177/09567976241243004
ライター
川勝康弘: ナゾロジー副編集長。 大学で研究生活を送ること10年と少し。 小説家としての活動履歴あり。 専門は生物学ですが、量子力学・社会学・医学・薬学なども担当します。 日々の記事作成は可能な限り、一次資料たる論文を元にするよう心がけています。 夢は最新科学をまとめて小学生用に本にすること。
編集者
ナゾロジー 編集部










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN