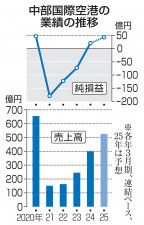「のし紙」印刷請負業者の富士印刷は、3月15日に破産手続き開始決定を受けた。設立は2002年9月だが、前身ののし紙印刷業者(1933年創業)の分社化でスタートした経緯があるため、実質的には業歴90年を超える。主に百貨店向けの「のし紙」を扱い、伝票や包装紙なども手がけていた。配送・納品を自社で行い、印刷設備も保有して子会社に貸与し印刷を発注。印刷業者としての立ち位置で顧客のニーズをくみ取り、きめ細かいサービスで特注品へも対応、得意先の多くは長年のなじみ先であった。「のし紙」は安定した収益源となり、業績へ大きく貢献した。
しかし、近年は得意先である百貨店業界の業況が悪化。20年の新型コロナ感染拡大がさらなる打撃となった上、百貨店で中元や歳暮を購入する消費スタイルも変化、「のし紙」の受注減は著しく03年8月期には9億5000万円あった売上高は、23年8月期には約5億7000万円に減少していた。この間コロナ禍で迎えた20年8月期の決算で、営業段階で赤字を計上し債務超過に転落。そのまま赤字経営から脱せず、資金繰りが悪化し公租公課を滞納する事態に陥った。積み上がった未払いの滞納金は月商ほどの水準となり、厳しい債権回収に対応しきれず、事業継続を断念することとなった。
時流の変化で商品需要は下向き、未曽有のパンデミック(世界的大流行)が打撃となり屋台骨が揺らいだ同社。しかし、ゼロとなる市場ではなく、根強いニーズは残っているはずと再構築を図っていたが、公租公課が大きな足かせとなった。コロナ禍から企業活動が正常化する一方で、特例措置は縮小されている。納税は企業が公平に負う義務であり、支払いがなければ回収に尽力されるのは当然のことだろう。今後も「公租公課」滞納が、最後の引き金を引いてしまうケースはさらに増えていくのではないか。その警鐘とも思えるような、同社の幕引きであった。(帝国データバンク情報統括部)
【関連記事】 倒産寸前企業が頼りにする知られざる「育成所」










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN