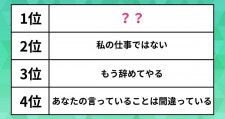◆「ゲームで稼ぎたい」若者を襲った悪夢
自分の好きなことをして稼げたら…。そのような風潮が強まるなか、副業感覚でYouTube配信やポイ活(ポイント活動)、ゲームなどをしてお金や金券類などを稼ぐ人が増加。そこにつけこむ詐欺師たちも急増し、後を絶たない。
福井悠斗さん(仮名・21歳)は、「自分は絶対に騙されない。騙されるほうがバカだと思っていたぐらいなのに、まさか騙されるとは…」と悔しさを滲ませる。福井さんは、ニュースには敏感で、社会問題になっている詐欺に関するネット記事は積極的に目を通していた。
「当時の僕は通信制の大学生で、卒業後のことも考え、在宅でできる仕事を模索していました。ネット関連で少額の報酬を得ていましたが、できれば得意なゲームで稼いで、その報酬と併せて生計を立てていきたいと考えていたのです」
人気のサードパーソン系シューティングゲーム「荒野行動」ではスポンサーが付いていた時期も長く、主催する大会に出場して何度も賞金を獲得。そういった経験もあり、ゲーム分野で報酬を得たいと考えていた福井さんは、あるサイトに登録した。
「ゲーム関連のトレードサイトです。僕はそこでゲーム内の武器を販売したり、依頼を受けてゲームを進める代行作業をしたりしていました。代行作業を規約で禁止しているゲームも多いですが、僕が作業を手がけたゲームは当時、代行作業を禁止していませんでした」
そのため「これで稼げるなら、夢のよう」だと思い、努力して依頼者が増えるよう信頼を積み重ねた福井さん。サイト内での取引が多いときは複数回にわたることもあり、少額ずつではあったが、自分の好きなことで得られる報酬は格別なものだった。
「代行作業の依頼は多かったのですが、数百円程度と少額だったため、数をこなす必要がある。どうにか効率よく稼ぎたいと考えていたとき、代行作業を有利に進められそうなゲーム内のアイテムを販売している人をみつけたのです」
◆URLに仕掛けられた巧妙な罠
いつもは依頼を受けたり販売したりする側だったため、アイテムを購入するのは初めて。それでも操作は簡単で、とくに困ることもなかった。ただ、サイト内で出品者と購入者がメッセージのやり取りをするチャット空間で、出品者から指示を受けている。
「内容は、『詐欺多発に伴い、本人確認をする必要があるので下記URLよりログインしてください』というもの。僕が、このURLを開いてログインしてしまったのにはいくつかの理由があります。まず、普段から使い慣れていたサイト内での出来事だったこと」
そして、「取り引きは通常、“①出品物を購入②入金(いったんサイトが預かる)③商品の受け渡し④相互レビュー⑤出品者に商品代金が反映される”といった順番で行われます。僕が詐欺に遭ったのは、 “③商品の受け渡し”のタイミングです」と続ける。
「出品者からURLよりログインして本人確認をするよう促されました。焦りと慣れは、本当に怖い。面倒なやり取りをサッサと終わらせて早く稼ぎたいという気持ちも高まり、寝起きの頭が冴えていない状態でチャット内のメッセージからURLを開いてしまったのです。」
ゲーム関連の詐欺については認知していたが、「昨年2023年当時に流行っていた、“ニセモノのアカウントやデータを買わせる”とか“いったん売ったゲームアカウントを購入者の承諾なく奪い返してまた売る”などといった内容のものとは違っていました」と、福井さん。
「いま振り返ると無意識のうちに、自分が持っていた詐欺の知識に頼りすぎていたのだと思います。また、使い慣れたサイト内だったことから、考えるより先に行動していたというのも正直なところ。さらに、URLを開いた先にも巧妙な手口が仕掛けられていました」
URLを開くと、福井さんがアイテムを購入したトレードサイトの名称やロゴが記載されたページが出現。そのため「出品物を購入したときは、自動的にURLが出品者のメッセージに貼り付いてきて手続きをする仕組みなのだろう」と薄っすら思った程度だった。
「振り返ってみたらそう思っていたという程度で、無意識にURL内でトレードサイトのログイン情報を入力してしまっていたというのが正直なところです。仲間同士で取引して作ったのか、取引実績が十数回あると表示されていたことも信じたひとつの要因といえます」
詐欺の方法はそれぞれだが、福井さんが騙されたケースでは「formrun(フォームラン)」が利用されていた。フォームランはグッドデザイン賞も受賞しているデザイン性の高いサイトで、誰もが簡単に問い合わせやアンケートフォームを無料作成できる非常に便利なツール。
「でも当時は調べても、フォームランがフォームを作成できるツールだということしかわからなかったし、まさか個人が勝手にトレードサイトの名称やロゴを使ったログイン画面まで表示させることができるとは考えてもみませんでした。そして僕は、騙されたのです」
◆なりすましで被害が発覚
URL内でトレードサイトのIDとパスワードを入力した福井さんは、アイテムの引き渡しを楽しみに待っていた。ところがそのあとすぐ、相手方がレビューを書き込んだとの通知が届く。それは、とても不思議なことだった。
「通常は購入者が先にレビューを書き、そのあとで出品者が購入者のレビューを書きます。でも、僕はまだ、レビューを書いていない。不審に思った僕は、すぐにサイトにログインしました。すると僕の代わりに誰かが、僕になりすましてレビューを書いていました」
福井さんはすぐ、アカウントが乗っ取られたことを悟ったとか。そして、購入したはずのアイテムは引き渡されるどころか、ゲーム内で貯めていた現金に引き換えることができるポイントのみが万単位で減っている。「騙された…」と青ざめたが、時すでに遅し。
「すぐにパスワードを変更し、トレードサイトに状況を報告。その後、連絡した警察では、『この手の詐欺は多く、犯人が検挙される可能性は低い。被害届を出してもサイト側が協力してくれるかは不明だが、それでも被害届を提出しますか?』と聞かれました」
そして、ゲームの代行作業がグレーな行為であることやトレードサイト内で被害に遭った人たちが泣き寝入りをしていることについても知ったという。犯人の検挙は難しいと感じたが、それでも「自分と同じように詐欺に遭う人を減らしたい」と被害届を提出。
◆口座情報を教えないと返金されない?
「その後、サイバー犯罪を専門とする部署に引き継がれ、あらためて事情を聞かれました。最初に相手のIPアドレスとだいたいの居住地が判明。それから半年ぐらい経った頃に、犯人が特定されたという連絡がありました」
そして、「警察は、『犯人は反省していて騙したお金を返金したいと言っている。口座番号を相手に伝えて返金してもらうかどうか考えてほしい』と言いました。でも、自分の名前や口座情報などを加害者に伝えるのは勇気がいるものです」と福井さん。
「できればもう、詐欺師なんかとかかわりたくない。けれど詐取されたお金を返金してもらうためには、警察に口座情報などを伝え加害者と情報を共有して振り込んでもらうか、弁護士に被害金を受け取ってもらうよう依頼するしかないと説明がありました」
けれど、弁護士に依頼すると高額。数万円程度の被害金額を取り戻すために依頼をすれば、マイナスになってしまう。福井さんは被害に遭ったお金の返金を悩んだ末に諦めたが、いまでも「しっくりしない」という。
「僕のように口座情報などを教えるのが不安で、返金を諦めた人もいるのではないでしょうか?でも、たとえ数万円でも、お金を稼ぐのは大変なことです。たとえ少額でも取り返したいというのが本音。自分の口座情報などを開示せず、返金できる制度を作ってほしいです」
筆者のほうでも警察に確認を取ってみたが、やはり、“加害者の反省が相当と認められ、被害に遭ったお金を返金してもらう場合は、加害者に口座情報を伝えて返金している”とのこと。詐欺が横行するいま、被害者が安心して返金請求が可能な仕組みの新設を祈るばかりだ。
【夏川夏実】
ワクワクを求めて全国徘徊中。幽霊と宇宙人の存在に怯えながらも、都市伝説には興味津々。さまざまな分野を取材したいと考え、常にネタを探し続けるフリーライター。Twitter:@natukawanatumi5










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN





![男を騙す[頂き女子]最新事情】](https://img.news.goo.ne.jp/image_proxy/compress/q_80/picture/nikkan_spa/s_nikkan_spa-2002345.jpg)