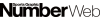先の春場所は尊富士が110年ぶりとなる新入幕優勝を成し遂げ、相撲ファンのみならず日本中で世紀を跨ぐ大快挙が大きな話題となった。番付も東前頭17枚目という幕内42人中、“ランキング”は最下位にもかかわらず、大関、関脇、小結の3人の役力士を撃破しての13勝は、堂々たる成績である。
尊富士の新入幕優勝も“奇跡”とは言い切れない?
土俵はニュースターの誕生で活気づいたが、一方で新入幕力士に賜杯をさらわれた上位陣にとっては屈辱以外の何物でもない。今場所は大関以上の看板力士が先場所の雪辱を果たさなければならなかったが、初日は1横綱4大関が全滅。2日目は横綱照ノ富士、大関貴景勝が休場(不戦敗)となり、大関豊昇龍は連敗スタートとなった。カド番の大関霧島は序盤から黒星が大きく先行して休場するなど、先場所同様、“下剋上”の様相を呈している。
角界には横綱を頂点とした番付という厳然たる実力の序列が存在する中で、尊富士の功績は歴史的に見れば“奇跡”であるのだが、ここ最近はそうとも言い切れない現象が頻発している。
昨年名古屋場所は新入幕の伯桜鵬が14日目終了時点で、関脇豊昇龍、北勝富士とともに3敗で優勝戦線のトップに並んだ。当時の伯桜鵬は、幕下15枚目格付け出しのプロ入りから4場所目の19歳。千秋楽は勝てば北勝富士との優勝決定戦に進出であったが、大関取りが懸かる豊昇龍の上手投げに屈した。
「勝つために準備して勝てなかったのが悔しい。豊昇龍関が自分より強い。それが結果なので、稽古して強くなるしかない」と最後は力尽きたが、初めての大舞台にも決して雰囲気に飲み込まれなかったのは、さすがは10代ながら“怪物”と言われた新鋭である。
翌秋場所は幕内通算2場所目で、この場所が5場所ぶりの再入幕だった熱海富士が1敗の単独トップで終盤戦に突入。12日目から関脇大栄翔、大関貴景勝に連敗したが、最後まで優勝戦線をけん引した。千秋楽の朝乃山戦に勝てば優勝だったが、完敗すると貴景勝との優勝決定戦にも屈し、初賜盃は一歩及ばなかった。
「熱海富士関が優勝争いをして、悔しい気持ちもある。自分も早く優勝争いをやってみたい」
年下の兄弟子が躍動する姿を目の当たりにした尊富士は当時、まだ幕下だったにもかかわらず悔しさを露わにすると、そのわずか3場所後、本当に“大仕事”をやってのけてしまった。
「いまは有望な子ほど進学」番付の権威が揺らぐ理由
大相撲は他のプロスポーツよりも、プロとアマの実力差が圧倒的に大きいと言われてきた。いわゆる“たたき上げ”と学生相撲出身者とでは、鍛え方が根本的に違っていたからだ。アマチュアでいくら大きな実績があろうとも、関取と言われる十両以上には通用しないというのが、少なくとも昭和時代までは“定説”だったが、いまは大相撲の根幹をなす番付の権威が揺らぎ続けている。
長く三役で活躍したある親方は「いまは素質があって有望な子ほど、高校、大学に進学するので、自然とアマチュアがレベルアップしてきている」と指摘する。加えて「新弟子の人数が減ってきているのも大きい」とも話す。どのスポーツでも裾野の人口拡大が、その競技の全体的なレベルアップにつながるのは自明の理だ。
「番付上位に絶対的な“型”を持った力士が少ないのでは」という声も角界内外から少なからず聞こえてくる。現役時代の横綱白鵬に右四つがっぷりの胸を合わせる体勢で勝てる力士は、ついに現れなかった。怪力で鳴らした魁皇も晩年は満身創痍ながら、左四つの型があったからこそ、大関として39歳直前まで土俵を務めることができた。
相撲は防具を一切身につけないコンタクトスポーツである故、力士にケガは付き物。本場所は年6場所、2カ月に1回はやってくるため、毎場所常にベストなコンディションで臨めるわけではない。“型”がなければ、好不調の波がそのまま成績に反映されることは想像に難くない。結局は番付に関係なく、その場所で一番調子がいい力士が賜盃を手にしているのが、昨今の傾向と言えるのかもしれない。だとすれば、ケガの蓄積がまだ少ない素質のある若手力士にも、大いにチャンスがあるということにもなる。
若手ホープの台頭は歓迎すべきことだが…
今場所も入幕3場所目の新小結大の里が、1横綱2大関を撃破して快進撃を見せている。先場所は尊富士と千秋楽まで賜盃を争い「優勝が夢から目標に変わった。目標として持ち続けて頑張りたい」と意気込む。“目標達成”となれば、早くも来場所での大関取りの声も聞こえてきそうだ。
若手ホープの台頭は歓迎すべきことであり、番狂わせはファンを熱狂させるが、やはり最後は番付上位の力士が勝って土俵を締めるのが本来の姿。長い目で見れば、番付の秩序が保たれてこそ、大相撲に永続的な人気と繁栄をもたらすことは歴史が証明している。
文=荒井太郎
photograph by JIJI PRESS










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN