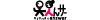ゴールデンウィークが明け、「なんとなく体がだるい…」「集中力が続かない」というような症状を感じている人も少なくないと思います。この時期に、よく見聞きするのが“五月病”です。五月病というと、寒暖差のある 天候や新生活での環境の変化によるストレスなどが原因といわれています。今回は、五月病が「ストレスを知らせる大事なサイン」と語る、心理学を研究する摂南大学・現代社会学部現代社会学科の竹端佑介准教授に、五月病のメカニズムや対処法などについて、聞いてみました。
ストレスで正常に副腎や自律神経系が働かなくなる
Q.まず、五月病とは、どういう症状なのでしょうか。
竹端さん「頭痛、肩が凝る、体がだるい、疲れがとれない、眠れない、気分が落ち込む、やる気が出ないといった心身の不調を訴えることがいわれていますが、人によってその症状はさまざまです。
一般的に五月病と言われていますが、正式な医学用語ではないことにご注意ください。病院で診てもらった場合、適応障害やうつ病などと診断されるかもしれません。
また、最初に挙げたような症状があった場合に別の病気が隠れていることもあるかもしれませんので、詳しく診てもらう必要があります」
Q.なぜ、5月になると、体がだるく感じたり、集中力が続かないといった症状が出やすくなるのでしょうか。
竹端さん「新年度を迎えて、さまざまな環境変化を頑張って乗り越えようとして、張りつめていた緊張の糸が切れしまう時期が5月頃と考えられます。ですが、5月になると必ずそのような症状が出るという訳ではなく、頑張り、踏ん張りがきかなくなった時、先ほど言ったような緊張の糸が切れてしまい、さまざまな心身の不調として現れてくると考えた方がよいかもしれません」
Q.五月病は新生活での適応障害や、ストレスが原因といわれていますが、どういうメカニズムになっているのでしょうか?
竹端さん「天候 や人間関係などストレスは多種多様です。私たちの心身はさまざまなストレスに対して適応しようとしています。
ストレスに適応する心身の仕組みはとても複雑です。今回は、体 がどのようにストレスに適応しようとしているのか、一つの側面から考えてみます。
例えば、体 の中には腎臓があり、さらに、その腎臓の上には副腎という小さな臓器があります。この副腎はストレスに対して重要な役割を果たすとされています。
ストレスを受けると、脳(視床下部や下垂体と呼ばれる箇所)と副腎は連携してストレスに適応しようとします。すなわち、脳と連携した副腎の副腎皮質からストレスホルモンと呼ばれる「コルチゾール」(グルココルチコイドの一種)の分泌が促されます。なお、ストレスを受けた場合には、もう一つ、脳の視床下部から自律神経系に指令が行き、心身の変化が起こるルートもあることを付け加えておきます。
さて、このコルチゾールは、ストレスを受けた場合に、体 (脳を含む)に必要なエネルギーを供給するためのブドウ糖を作り出すよう促し、血糖値を上昇させる役目があります。また、コルチゾールは炎症やアレルギーなどを抑制する働きもしているといわれています。
過度のストレスや慢性的なストレスにより正常な副腎の働きができなくなってしまいます。そのため、副腎皮質から過剰にコルチゾールが分泌されることにより、必要以上のブドウ糖が作られ、血糖値が上がり過ぎてしまう高血糖を引き起こす可能性があるといわれています。それだけでなく、免疫力の低下を引き起こし、風邪などをひきやすくなります。
過度のストレス、あるいは慢性的なストレスは、自律神経系の変化も引き起こします。
自律神経系は緊急の事態に対応するために働く交感神経系と、体 の休息と回復を促すために働く副交感神経系の二つがあり、両者はバランスをとっています。
しかし、過度のストレスや慢性的なストレスがある場合、常に交感神経系が興奮した状態となる、あるいは、必要以上に副交感神経系が働くなど交感神経系と副交感神経系のバランスが取りにくくなってしまいます。
こうした副腎や自律神経系が正常に働かなくなることで、さまざまな症状が現れ、適応障害やうつ病、生活習慣病などストレスに関連した病気を引き起こしている可能性があります」
Q.五月病だと感じたら、どうすればよいのでしょうか。ストレスマネジメントの方法など、対処法を教えてください。
竹端さん「先ほどのコルチゾールは朝に多く分泌されることが分かっており、体内リズムと関連すると考えられています。
リラックスするために、スマートフォンやタブレットなどを使い過ぎてしまい、ついつい寝るのが遅くなってしまうと生活リズムが崩れ、コルチゾールが慢性的に分泌され、メンタルヘルスの問題につながることが予想されます。
規則正しい生活をとよく言われますが、「ストレスがかかっているな…」と思った時ほど、意識的に生活リズムを整えることが大切です。ちなみにですが、ジョギングやウォーキングなどはリズムのある運動です。リズムのある運動は精神状態を安定させるセロトニンを作り出すとされています。
SNSなど常に強い刺激に大量にさらされている現代人にとっては、一時的にもそうしたストレスから離れる時間も大事だと思います。この意味で、リラックスして『ぼーっ』とする時間を確保することは五月病を乗り切るためのストレスマネジメントになるかもしれません。
さまざまに現れる症状は、私たちの心身がストレスに適応できなくなりつつあることを教えてくれている大事なサインの可能性があります。少しでも心身の違和感をもったら、その違和感を見逃さず、違和感を生じさせているストレスがあるかどうかを振り返り、早めにそのストレスに対処する方法を考え、行動に移していくことが大切ではないかと思います」










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN