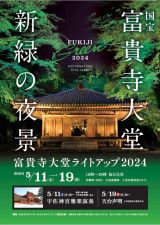宮内庁の中には「式部職楽部(しきぶしょくがくぶ)」という、雅楽(ががく)の演奏をなりわいとする団体がある。26人ほどの楽師は、平安時代から代々雅楽を担ってきた「楽家(がっけ)」と呼ばれる家の出身の方が多い。
楽部では春と秋の年2回、演奏会を行っている。4月のよく晴れた日、これを聴くため皇居を訪れた。披露されたのは、管絃「迦陵頻(かりょうびん)」と「酒胡子(しゅこうし)」、そして朗詠「東岸(とうがん)」、舞楽の「北庭楽(ほくていらく)」と「敷手(しきて)」。楽器だけで演奏する「管絃」と、歌の「朗詠」あるいは「催馬楽(さいばら)」、そして舞を伴う「舞楽」がセットになるのが雅楽の演奏会としては一般的なスタイルだ。
「迦陵頻」は、天竺(てんじく)にある祇園精舎(しょうじゃ)の供養の日に迦陵頻(極楽浄土に住む鳥のような生き物)が飛来した際、妙音天(弁財天)が奏でた曲だといわれている。この曲は舞楽になると、子どもが背中に美しい羽をつけ、銅拍子(どうびょうし)(小さなシンバル)をたたきながら舞う。その音は迦陵頻の鳴く声をまねたものだという。
「酒胡子」はその名の通り、酒盛りの時に演奏したとも伝えられている。真面目な様相の雅楽ではあるが、酒に酔った様子を表した舞や(「胡徳楽(ことくらく)」という演目ではなぜか酔人役の面の長い鼻がブラブラ揺れるようになっている)、酒宴の喜びを表す歌などが実に多く残されている。
「朗詠」というのは、優れた漢詩に雅楽風の歌を付けたもの。今回の「東岸」では、慶滋保胤(よししげのやすたね)の詩で早春の風景が美しく歌われる。
東岸西岸之柳(とうがんせいがんのやなぎ) 遅速不同(ちそくおなじからず)
南枝北枝之梅(なんしほくしのうめ) 開落已異 (かいらくすでにことなり)
(岸の東と西とでは柳の芽吹きの早さを同じくしない。枝の南と北とでは、梅の開くのも落ちるのもすでに異なっている)
「北庭楽」は初めて夫婦となる日に、そして「敷手」は天皇元服の際に奏されたといわれる曲。感じ入るのはその色彩の豊さだ。北庭楽では赤を基調とした「襲(かさね)」と呼ばれる幾重もの装束を用いる。「片肩袒(かたかたぬぎ)」といって片方の上着の袖を脱いでいるので、下に着た白の下襲(したがさね)や絢爛(けんらん)な刺しゅうを施した袢臂(はんぴ)(ベスト)がのぞいているのがとても美しい。
敷手でも、舞の途中で片肩袒をする。青緑に染められた薄い上着から下に着た白と赤の装束が透け、4人並んで舞う姿は大変涼やかで上品だ。野外を模した玉砂利の会場に、大きな太鼓の響く様は〝美事(みごと)〟の一言だった。
秋に行われる演奏会は、7月のはがき抽選で当選すれば一般の人も無料で見ることができる。千年以上続く雅楽の正統の本丸をぜひ体感してみてはいかが。
【KyodoWeekly(株式会社共同通信社発行)No.20 からの転載】
かにさされ・あやこ お笑い芸人・ロボットエンジニア。1994年神奈川県出身。早稲田大学文化構想学部卒業。人型ロボット「Pepper(ペッパー)」のアプリ開発などに携わる一方で、日本の伝統音楽「雅楽」を演奏し雅楽器の笙(しょう)を使ったネタで芸人として活動している。「R-1ぐらんぷり2018」決勝、「笑点特大号」などの番組に出演。2022年東京藝術大学邦楽科に進学。










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN![オーヴォ [OVO]](https://img.news.goo.ne.jp/image_proxy/compress/q_80/img/ip_logo/ovo.gif)