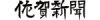私は産科をしたくて産婦人科医になりました。ところが、大学病院の産婦人科に入局してみると正常分娩(ぶんべん)は少なく、多くは婦人科の悪性腫瘍(がん)の患者さんでした。
研修医1年目で初めて主治医になったのは、私と3歳くらいしか違わない卵巣がんの患者さん。未婚で片方の卵巣をがんで摘出した後、再発予防の抗がん剤治療中でした。ひと月に1回の抗がん剤治療と月経が重なって本当につらそうでした。当時は今のように良い吐き気止めがありませんでした。つらい治療をしたのにもかかわらず、反対の卵巣に再発してしまいました。
2回目の手術で反対の卵巣と子宮も摘出しましたが、ご両親の頼みで本人には告知しませんでした。将来、妊娠して子どもを産むという希望を失わせたくなかったのです。
術後また追加の抗がん剤治療をしましたが、月経はありません。「どうして生理がこないの?」と聞かれて「今度は強い薬を使っているからよ」と答えました。超音波をしながら「子宮はどれ?」と聞かれて「腸管のガスで見えにくいけど、これかな」と苦しい答えをしていました。でも本人は分かっていたのかもしれません。研修医2年目になって「先生、点滴上手になったね」と褒められました。
ご両親は長い入院期間中、毎日欠かさずお見舞いに来られました。彼女もご両親にわがままも言わず、前向きで明るく年上の患者さんたちからもかわいがられていました。
大学病院なので、異動があり主治医が何人も代わりました。彼女はこう言っていたそうです。「最初の主治医にまた戻って、これで終わりかな…」最後は肝臓に転移して亡くなりました。はじめから妊孕性を温存せずに子宮も両方の卵巣も全摘していたなら、助かったのかもしれないと悔やまれました。
いま卵巣がんの抗がん剤治療は飛躍的に進んでいます。今ならきっと彼女の病気を治療して出産してもらうこともできたと思います。心に残る、忘れられない患者さんです。
(伊万里市 内山産婦人科副院長、県産婦人科医会理事 内山倫子)










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN