10枚目のオリジナルアルバム『Rosy Moments 4D』を昨年9月にリリースしたD'ERLANGER(デランジェ)が、『D’ERLANGER TOUR 2024 Rosy Moments 4D』と題した全国ツアーを先日4月29日、EX THEATER ROPPONGIからスタートした。コロナ禍でもできることを模索しながら精力的な活動を展開してきた彼らが、最新アルバムを携えて久しぶりに行う全35公演に及ぶロングツアー。その初日を終えたばかりのkyo(Vo)に、ライブの手応えとバンドの近況を聞いた。
――ツアー初日の4月29日、EX THEATER ROPPONGIを拝見し、圧倒されました。手応えをお聞かせください。
今年はスロースタートで、2月4日に1本ライブがあって、そこから2ヵ月半空いてからのツアーになるんですよね。4月26日にファンクラブ会員を対象に開催したプレショウは、いつもよりちょっと緩い雰囲気でやりながらも、久しぶりにメンバー4人で音を出して。そこでは楽しさがあるんですけれども、ツアー初日、しかも珍しく東京初日だったので緊張感が加わって。いい意味でピリッとする、ソリッドになるというか。“あぁ、やっぱり瞬間的にD’ERLANGERになるんだな”という手応えはありました。 だから、よりツアーは楽しみになっています。
――kyoさんの歌声はパワフルで、圧巻の音圧でした。ご自身の声のコンディション、歌に対する“こうありたい”という理想の実現度はいかがでしたか?
こういう風に言うと偉そうですけど、まずスタートとしては100点だったと思います。声も個人的にも気持ち良く出ていましたし。ただ、その100点がもっと大きくなっていくんですよね、“旅”に出ると。全部終わった時に“まだまだの100点だったな”と思えるようでいたいです。あの会場は気持ちいいんですよ。音もそうですし、僕はあそこの景色が好きで。もっと言うと楽屋とかも好きなので、トータルで気持ち良くできて。ベストのD’ERLANGERの音だったので、ボーカリストとしてもベストであったと思います。
――歌声もそうですが、“この新曲を、こういう身振りで表現されるのだな”という視覚面の楽しみも大いにあり、陶酔しながら拝見しました。ああいったパフォーマンスのイメージトレーニングはなさるのですか?
全く(笑)。出たとこ勝負のバンドなので、何かを事前に用意して、それを表現するというのはなくて。だから、他のメンバー3人の空気感を瞬間的に掴み取る、ということのほうが大切なスキルなんですよね。空気の揺れ方だったり、“こっちの世界に連れて行かれるのかな?”と感じ取ったりするところは抗わずに委ねたい、というか。パフォーマンスは後でビデオを見返すと恥ずかしいところもありますけど、より曲の中に入り込めたってことじゃないかな?と思います。
――アルバム『Rosy Moments 4D』がリリースされたのは2023年9月13日。新曲たちをどのようにして染み込ませていかれたのですか?
例えば「Andre」とかはレコーディングする前から、コロナ禍の最初の頃からライブではやっていたので、付き合いは長い曲になるんですけれども。D’ERLANGERは“アルバムをつくろう”となって曲が出てきて、レコーディングして完成するまでの期間がすごく短いので割と瞬発力でつくるし、ファースト・インプレッションで形にしていくところが多いんです。それにプラスして、去年リリースしてすぐにライブがあったんですよね。
――はい、9月16日の梅田クラブクアトロ公演を皮切りに、大阪と東京で年内8本のライブをされました。
だから、ちょっと語弊があるかもしれないけど、ボヤけた輪郭がよりしっかりとした輪郭になっていく感じ、というか。いざ表現する時には、曲をつくった時の気持ちってそんなに大きくなくても良くて、ライブでポン!と出した時に返ってくる気持ちが大事だったりするんです。その時によりリアルになるというか。そういったところを一つひとつ確認しながら、なのかな?

kyo(Vo)
■去年はあまりにもいろんな出来事が多過ぎた。生と死……は言い過ぎかもしれないけど、自然とアルバムの曲と重なっていった感じはすごくあります。
――アルバムには、色気に満ちたD’ERLANGERらしいグラマラスなロックンロールと、直接的な表現はされていないものの、喪失の哀しみに寄り添うようなブルージーさが共存していて。その光と影の対比が、ライブではより際立って感じられました。
去年はあまりにも……いろんな出来事が多過ぎたじゃないですか? 制作の時期にもそれがあったし、その前には自分の病気のこともあったし、コロナ禍もあったし。そこを意識しながらつくったわけではなかったんだけども。リリースしてライブをやっていく中でのほうが、儚さ、瞬間の美学というか、その大切さがよりリアルになって。生と死……は言い過ぎかもしれないですけど、自然とアルバムの曲と重なっていった感じはすごくあります。
――思いもよらない訃報が相次いだ2023年後半だったので、曲の聴こえ方も必然的に変わってしまいましたね。
そういう意味ではちょっと特別なアルバムになったのかな?と思いますよね。こういうことってないと思うし、ないほうがいいし。ただ僕は、無理に何か物事を埋める必要がないっていうことを伝えたいと思うし。前に進めなくなるとか、塞ぎ込むのは良くないことだと思うんだけど、失くしたもの、失くしたこと、亡くした人に対して、未来に想いを馳せるように想うことって大切じゃないかな?と思うんですね。今回のアルバムは、奇遇にもそういうテーマの曲が元々幾つかあったので、それがきちんと重なり合って、大きなエネルギーになればいいな、とは思います。
――哀愁を湛えた曲たちに聴き入りつつ、最終的に心に届いてきたのは、強い生命力だったんです。それがライブの力であり、生で音を体感することのすごさだと実感しました。
すごくうれしいですね。そこが、自分たちがライブにこだわっている部分だと思う。そういう意味では、これからもライブバンドでいたいし。年齢も重ねてきましたので、それができるように昔よりは努力をしようかな?と思います。
――セットリストはアルバム曲を網羅しつつ、それに加えて盛り込む楽曲たちはどのような基準で選ばれたのでしょうか?
全然、基準はないんですよね。セットリストを考える時に“じゃあ、合間にこれ挟もうか”みたいな感じで、自然に湧いてきたものです。今回のツアーでは一応A、B、C、Dの4パターン持って回ろう、と。均等に4パターンやるかは分かりませんが、全会場2Daysあって、2日間同じことはやらないので。ツアーが進んでいく中で変わる時もあるし、そこは出たところ、というか感じ方に任せようかな?と。
――メンバーのどなたかが中心になって組むのですか? それも決まっておらず、皆さんで何となく決めていかれるのですか?
誰かが軸になる時もあれば、本当に手探りで“じゃあ、こうは?”みたいな風に4人でやりながら決めていくこともあります。その場合も、最終的には誰かが軸にはなるんですけども。ただ、アルバムが出て以降、まだ東京と大阪以外ではライブをやっていなくて(※取材日の5月1日現在)、その時のセットリストがツアーのセットリストの考えの基本になっているところはあります。
――昨年11月、Veats Shibuyaでkyoさんは「そろそろ自分の街で聴きたいよね」といったMCをされていました。各地から駆け付けたファンの方もいらっしゃったでしょうね。
うん、遠征で来てくれる人がすごく多いと思うんです。でも自分の街で観るライブって特別だったりするじゃないですか? だからできるだけ行けるところは行きたいと思いますし。今回、再結成前も含めて、盛岡はこの4人で行くのは初めてなんですよね。そういうところもあるので、ツアーはすごく楽しみです。
――35本のロングツアーであり、その後のExtraも含めると全45本。すごい本数ですね。
今年は年間のスケジュールをまとめてボーン!と出したから、フライヤーとかで見ると“おお!”と僕らも思いますけど、毎年そのぐらいの本数はやっているので、たぶん大丈夫です。
――それにしてもすごいと思います。EX THEATERでのMCにもありましたが、コロナ禍にも屈することなく、早くからライブを再開し、度重なる延期や中止を乗り越えてツアーを完走。あの経験が今、糧になっている部分もあるのでしょうか?
あれは大きかったですね。僕らがライブを再開した頃って、“もうやっても大丈夫”という状況だったから始めたんですけど、まだライブの動きが少ない時で。延期して1発目が札幌だったんですね。ファンの皆さんはマスクをしなきゃいけない、声を出しちゃいけない。椅子が置いてあって、どう観ていいか分からないんですよ。僕らもどうしたらいいか分からなかったし。頭の1、2曲目まではお客さんが椅子に座っていて、“立つのはいいみたいよ?”と僕が言うと、初めて立つ。そういうところから始めたもので。やっぱり歓声が無いのって大きいんですよね。その中でファンの皆さんは拍手という、クラシック・コンサートのような表現方法で愛情を注いでくれて。光モノのグッズをつくったりして、いろいろとコミュニケーションの取り方を試行錯誤しながら、あの時なりのライブの形を見つけて。ああいう時期だったから、もし延期のまま中止になったとしても特別なことじゃなかったのかもしれないけど、やり切りたかった、というのはありますよね。中途半端にしたくなかった。しかも、スケジュールを増やしながらやっていったし。
――立ち止まるどころか、むしろスピードを上げて活動されていたんですよね。
(コロナ禍の規制下でも)あの時はライブをやりたかったし、“これはこれでアリだな”と思っていたし、実際にライブをやることで前に進めたと思うんですけど。でもどこかお互い、ファンの皆さんもバンドもスタッフも、少しずつ我慢していたと思うんですよね。それが去年、歓声と熱狂が戻ってきた時には“あぁ、やっぱりこの熱狂よね”と。そのワクワクで、まだまだ回れます。
――ファンの皆さんの歓声、熱狂から受ける影響はやはり、大きいのですね。
想像してない景色を見せてもらったり、想像しないテンションで “(自分が)こんな表現してる”と驚くことももちろんあったりするので、やっぱりそれがライブだと思うんですよ。たくさん練習して“練習通りに上手にできました”じゃなくて、その時にしかないエネルギーみたいなものを感じ取りながら、“どこに連れていってもらうんだろう?”という。そういう答えのないところで最終的な到達点に行くのが楽しい、というか。

CIPHER(Gt)
■つくられた物語をやりたくないのかもしれない。タイトルと白紙の紙があって、ライブで1行ずつ進んでいく、というのが好きなんだと思う。
――今回、ツアー開始前のリハーサルはどのくらいの期間されていたんですか?
期間で言ったら、2日ぐらいです。
――そんなに短いんですね!
そう、あまりやらないんです。ライブ当日も、サウンドチェックをして、リハーサルは曲数で言ったら2、3曲。会場によっては、音が決まらないと決まるまで時間を掛けるのはありますけど、基本的にはそんな感じです。それで付いてきてくれるスタッフがすごいと思いますよ。
――それは、再結成15周年を越えた今の4人だからこそ、なのでしょうか? 昔からですか?
昔はどうだったかあまり覚えていないですけど、それが僕らの当たり前なんですよね。たまに友だちとかが観に来てくれて、リハの時から遊びに来てくれると“えっ、これで終わり?!”とはよく言われます(笑)。逆に言うと、ワンステージ分ぐらいリハーサルやることのほうが僕らには信じられないし、すごいって思います。
――丸ごとリハーサルしたら新鮮味もなくなってしまう、という感覚ですかね?
つくられた物語をやりたくないのかもしれない。カッコいい言い方をすると、タイトルと白紙の紙があって、ライブで1行ずつ進んでいく、というのが好きなんだと思う。
――リハーサル期間についてお尋ねしたのは、メンバー間の雰囲気を知りたかったのもあってだったのですが、kyoさんからご覧になって、バンドのモードはいかがですか?
いい意味でリラックスした関係です。“最近どう? 何か面白いことあった?”みたいな他愛もない会話をしながら、“ツアー、どうしようか?”みたいなところに流れていって、“じゃあ、こういうふうにやろう”“音を出してみようか”みたいな。初日に“あれ、この曲どうだったっけ?”というところがあっても、2日目にはもうD’ERLANGERになっていて、すごいな、さすがだなと思います。雰囲気はすごくいいですし、あまり長く会わな過ぎると久々に会った時に恥ずかしいですから(笑)。ちょっと長い春休みがあって4人集まって、これから長い“旅”に行くので。そういう意味では、身も心も準備はできた感じだと思います。
――ツアーに出られると、東京に逐一戻らず、行きっ放しの期間もあるのですか?
ううん、基本的に週末公演なので。ライブをやっては帰ってきて、また週末に行って、という感じですかね。
――ちなみに2Daysで地方に宿泊される際、現地でどのように過ごされているのですか?
前までは、ホテルに帰ってシャワーを浴びて、ご飯を食べに行ったりしていましたけど、コロナ禍以降、感染を避けるためにお弁当になったんです。なので、1日目と2日目の夜は本当にゆっくり過ごしています。
――その日のライブを振り返ったり、現地の空気を感じたりする時間でしょうか?
振り返ってはいないと思う(笑)。疲れて寝ちゃいますね。ご飯を食べてシャワーを浴びて早めに休んで。朝早く起きるので、散歩して、観光まではいかないですけどその土地土地を少し感じながら。あとは、夜のお弁当もそうですしお昼も、イベンターさんおススメのものを楽屋に入れてくれるので、そういう食でその土地土地を感じたり……オッサンになりましたよね(笑)。
――いえいえ、素敵な時間です(笑)。そして盛岡には、4人では初めて行かれる、と。
D’ERLANGERではそうですね。ソロ時代にライブをやったこともありますし、個人的にはキャンペーンですごくお世話になった街というイメージがあって。でも、本当にもう何十年かぶりなので、すごく楽しみですね。

SEELA(Ba)
■瞬間、瞬間の楽しいことは10代の時もありましたけど、50代のバンドになった今、その楽しみは10代の時よりも上。だから、もっともっとやりたい。
――EX THEATERで印象的だったのは、明日何が起こるか分からない、というMC。“何かに裏切られるかもしれない。でも、何かが叶うかもしれない”という言葉に胸を打たれました。どういう想いから出てきたのでしょうか?
本当に……分かんないじゃないですか? 去年はそういう出来事が多過ぎたから。無意識でしたけど、ネガティブなことが先に言葉として出て、その後“明日何か叶うかもしれないし”というポジティブな言葉が出てきたのは、本当に自分が思っていることだからなのかな?って。悲しいことも良いことも同じように、均等に思っていいし。良いことが多いほうがいいけど、必ず繋がっているものだとも思うので。例えば、病気をしたという自分の経験から、実際にそう思えているから、上っ面の言葉じゃなくきちんと伝えたいと思うし。でも必要過多に伝えたいとは思わないし、自然にやってますけどね。本当に先のことは分からないから。でも、ライブって瞬間を共有することじゃないですか? だからこそ、その瞬間を大事にしたいし、その先に繋がるものになればいいなとは思います。
――ライブに対して“いちばん嘘のない場所だ”という表現もありました。ファンの方たちが何を感じるか?も人それぞれで、一律の正解や間違いがあるわけではないでしょうし、その時、その人が感じることをあるがまま受容する、というか。そんな包容力をkyoさんのMCからは感じました。
ロックって僕はやっぱりアンダーグラウンドなものだな、というのがあって。人の、心の隅っこのほうに普段は押しやっている感情を爆発させるのがロックのライブなのかな?って。僕らは、例えばそれを突いたりくすぐったりして、表に出すことを手伝ってあげられればいいと思うんですね。僕らの表現はそうですけど、他にもいろいろな音楽があって、良いことを歌う音楽もあるじゃないですか? そういう音楽で人生を助けられる人もきっといると思うし。僕も最近back numberの「水平線」という曲をたまたま聴いて、“すげぇいいこと歌ってるな”と思ったし。
――kyoさんがback numberを聴かれるとは、意外な気もしますが、名曲ですよね。
いろいろなあり方があって、観に来る人、聴く人もいろんなチョイスの仕方があって。D’ERLANGERのコンサートに、“背中を押してもらおう”と思って来る人は少ないと思うんです。でも、選んだ場所にある答えを共有できて、それが大きなエネルギーだったらすごくいいなと思うし。もしそれを得られなかったとしても、そこに嘘はないわけだしね。
――変わらぬメンバーでバンドを長く続けて行くこと、それは奇跡である、と痛感する昨今です。D’ERLANGERとしての歩みの一歩一歩、1本1本のライブに対する重みは増していっている実感はありますか? こちらとしては、ずっと続けていただきたい、と願うばかりです。
ありがとうございます。去年(の出来事)はやっぱり大きくて、1本1本の重みが大きくなった感じはあります。でもだからと言って、いい意味で、何かが変わるわけじゃないんですよね。だから……何かが“増えていってる”のかな? そんな気はします。“一つひとつが大切だ”ということの重みはより増しているし、瞬間、瞬間の楽しいことは、10代の時もありましたけど、50代のバンドになった今、その楽しみは10代の時よりも上ですから。だから、もっともっとやりたいです。
――10代の時よりも今のほうが楽しい。これ以上ないほどに素晴らしい言葉ではないでしょうか?
例えば、10代の時に『Rosy Moments 4D』みたいなアルバムは絶対つくれないし。逆に今、例えば『LA VIE EN ROSE』(1989年)みたいなアルバムを……つくろうと思えばつくれると思うけど、あの時の刺さり方、震え方とはまた違ったものになるんだろうし。作品もライブも、その時にしかできないものをやりたいですよね。ありがたいことに、それができるバンドにいるので、だから欲張りになります。

Tetsu(Dr)
■僕たちもお客さんに煽られるんですよ。その相乗効果が35本あると思うと、楽しみでしょうがないです。
――『Rosy Moments 4D』というアルバムタイトルは象徴的な言葉で、今回はRosy Momentという“瞬間”を積み重ね、複数形のMomentsにしていくツアーになっていく予感がします。kyoさんはこのタイトルについて、ツアーがスタートした今、改めて何をお感じになりますか?
『LA VIE EN ROSE』から始まって、薔薇というキーワードがあって、やっぱり特別なものになって、ちょうどオリジナルアルバム10枚目で。薔薇を背負って、薔薇を降らせて活動してきたバンドなので、“Rosy Moments”というのは、D’ERLANGERの人生そのものだと思います。“もっと、もっと!”と思えるってことは、その先の人生を描きたいと思うってことなのかな?と思うしね。
――バンドとしての未来を感じている、ということですよね。
そうですね。ツアーが決まっている時点でもう、未来があるから。ツアーのスケジュールを先に発表するとそれが約束事になるので、素敵なことだなと思います。
――セットリストが4パターンある、とおっしゃっていましたが、リハーサル段階で予め多めに音合わせしておくのですか? それも準備なさらないのでしょうか?
4パターン持って出るのは今までなくて、大体2つだったんですね。だから一応、ツアーが始まる前に、やる曲を触っておいたりはしています。
――そもそも今回は通常よりもパターンを増やそう、という流れになったのはなぜですか?
単純に長い“旅”ですし、熟成して楽しい時もあれば、いい意味で慣れてきて時には“ちょっと違ったおかず食べたいな”みたいな感じに近いのかな? とはいえ、厳密に4つになるかは分からないですね。ただ当面2つはあると思う。まだリハでやってない曲もありますけど、ツアー中のサウンドチェックの時に合わせてみて、それがその日のライブに突然出てくるという事もあるかもしれません。
――2Daysは両日必ず変わりつつ、プラスアルファ何かあるかもしれない、と。
そうですね。予定にない曲が突然始まることもあります。楽器はその瞬間に“この曲”って感じで入るんだから、それができるのはすごいなと思う。それがD’ERLANGERの空気感なんでしょうね。だから僕も気が抜けないんですよ(笑)。
――kyoさんは、予定調和的な準備はなさらないにしても、ステージ上で瞬発的に輝くために、何か日頃心掛けていらっしゃることはあるのですか?
風邪を引かないようには気を付けてます。病気をした後にはやっぱり体力が落ちたので戻したくて、少しトレーニングをするようになって。結果、歌にもいい影響があって、気持ち良く声が出るんですよ。なので、それが習慣にはなってきたかな? それは昔とは随分大きな違いです。大人になってから、真面目にやることイコールの気持ち良さがあるってことをようやく知りました。若い時は、その場その場で楽しいことが美学だったけど。まぁ、あまり“努力してます”みたいなのを言うのは好きじゃないんですけどね。年齢的に、僕には必要なことになってきたのかな?とは思います。
――35本目の札幌ファイナルでどのような景色が見えたら、kyoさんはツアーが成功だと思われるでしょうか?
札幌は、ここのところ行けていなかったんですよ。そういった特別な想いもあるんですけど、やっぱりいちばんの熱狂がそこにあってほしいな、と。会場のキャパの話ではなくて、お客さんとバンドの温度がそれを塗り替えていく、常に上回っていく感じを楽しみにしています。本当にいい意味で、僕たちもお客さんに煽られるんですよ。だから、お客さんのテンションが高いとこっちのテンションもどんどん上がるし、その逆もあるでしょうし。その相乗効果が35本あると思うと、楽しみでしょうがないです。
――これは常に思うことですが、4人が向き合った瞬間“誰が音を出すんだろう?”というスリル、あそこの真ん中に立ったら射抜かれてしまいそうな磁場、緊張感はD’ERLANGER特有。もう一度味わいたい、と渇望させる中毒性があります。
無音の時のカッコいい気持ち良さが伝わってるとうれしいし、本当にそうなんだよね。うちのバンドの強いところってそこで。無音の時に蠢いているものがすごいんですよ。それが音に憑依してドンッ!と来るので、すげぇ気持ちいいんです。あの気持ちいい空間を、一緒につくりたいですね。
――全国各地で待っている方たちと共に、ですね。
そうですね。特別なツアーにしたいですね。
取材・文=大前多恵
ライブ写真撮影=Hiroshi Tsuchida、Akito Takegawa











 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN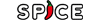







![imase、MILLENNIUM PARADE、[Alexandros]の新曲、B’zのTM NETWORKカバーなど『New Music Wednesday [Music+Talk Edition]』が今週話題の新作11曲を紹介](https://img.news.goo.ne.jp/image_proxy/compress/q_80/picture/spice/s_spice-328748.jpg)




















