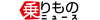航空自衛隊も導入を進める新型のステルス戦闘機F-35が、ようやく本格的な量産体制に移行する模様です。当初は2017年には全規模量産になる予定だったのに、なぜここまで遅れたのでしょうか。
当初は2017年に達成する予定が…
2024年3月12日、アメリカ国防総省はロッキード・マーチンF-35「ライトニングII」ステルス戦闘機について「全規模量産(FRP)」を承認したと発表しました。これにより、F-35の量産計画は「低率初期生産(LRIP)」を終え、本格的な生産フェーズ、すなわちフルレート生産に移行します。
当初、アメリカ国防総省は2017年にF-35の全規模量産を開始する計画でしたが、開発の遅れなど、さまざまな要因により数度となく延期されてきました。そのため、これまで実に16年間にわたって低率初期生産が続いていました。
ここまで長く低率初期生産が続いていると、F-35の製造が順調でなかったのではないかと思われがちですが、実際には全世界の戦闘機生産の過半数をF-35が占めており、ある意味でほぼ独占状態にあるといえるでしょう。
F-35はアメリカ空軍、海軍、海兵隊、および同盟諸国の既存の戦闘機を統一機種で更新するという野心的なプロジェクトです。そのため、開発前から既存の戦闘機とは一線を画す巨大なプロジェクトでした。ゆえに「低率」という言葉とは裏腹に、すでに年産150機にも達しており、2024年4月現在で各国への引き渡しは航空自衛隊向けを含んで990機にまで達しています。
では、何が順調でなかったのでしょうか。
F-35は既存の軍隊に対して高性能すぎるため、演習でその能力を完全に発揮できないという問題がありました。F-35の能力を実証するには「統合シミュレーション環境(JSE)」と呼ばれるシミュレーターが必要ですが、JSEの開発遅延により、F-35の試験ができない状況が続いたのです。
将来60年以上にわたって飛び続けるために
ただでさえ高性能なF-35ですが、現在は「TR-3(テクニカルリフレッシュ3)」と呼ばれるコンピューターのハードウェアを更新した性能向上型が生産中です。しかし、TR-3上で動作する「ブロック4」ソフトウェアの実証が遅れている影響で、2023年末から引き渡しが停止しています。つまり、F-35 TR-3という機体は完成しているものの、ソフトウェアがインストールされていない状態で、70機あまりが保管されているのです。
ブロック4の実証が完了次第、引き渡し停止も解除される見込みですが、2025年を予定しています。そのため、2024年の生産数は数十機になり、続く2025年は繰り越した分が加算され200機を超えることが予想されます。なお、これに伴い4桁の大台となる1000機目の引き渡しも同時に達成されるでしょう。
F-35の全規模量産認証は、これから何かが変わるというよりも、各種実績の積み重ねによって目標を達成したという意味合いが強いものです。そのため、ここから特段F-35の量産数が増えるということはないでしょう。おそらく、年産150機程度が今後10年以上続くと思われます。
なお、アメリカ軍におけるF-35の運用計画は、これまでの2077年から2088年へ延長される見込みです。そういったことを鑑みると、当面世界の戦闘機市場においてF-35一強の時代が続くのはほぼ確実である模様です。










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN