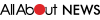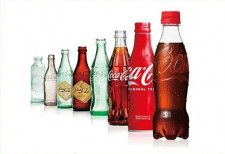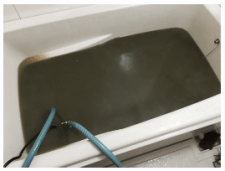「グラスが長いからロングカクテル」は勘違い! 「違いの分かる人」になれるカクテルの豆知識
1806年5月6日、ニューヨークの週刊新聞『The Balance and Columbian Repository』でカクテルという言葉が使われ、それはどのような飲み物かという読者からの質問に、翌週5月13日の紙面で記者が回答したことに由来しています。
今回は、カクテルの語源やショートカクテルとロングカクテルの違いなど、「違いの分かる人」になれるカクテルの豆知識をご紹介します。
■カクテルの語源は?
カクテルの語源は諸説ありますが、国際バーテンダー協会のテキストにも記載されている「木の枝説」が有力とされています。
メキシコの港町に停泊したイギリス船員たちが入った酒場で、少年がきれいに皮を剥いた木の枝をマドラーにしてミックスドリンクを作っていました。
船員が「それは何?」と少年に尋ねた際、ドリンクの名前ではなく木の枝のことを聞かれたと勘違いした少年がスペイン語で「コーラ・デ・ガジョ(Cola de gallo)」と答えました。
英語に直訳するとTail of cock、すなわち雄鶏のしっぽという意味で、木の枝の形が似ていたために少年が愛称でそう呼んでいました。そこからミックスドリンクをTail of cockと呼ぶようになり、さらに転じてcocktail(カクテル)と呼ばれるようになったとされています。
■007がマティーニをシェイクするのはなぜ?
映画『007』シリーズの最新作『ノー・タイム・トゥ・ダイ』でも登場した007ことジェームズ・ボンドの名ぜりふ「Vodka Martini. Shaken, not stirred.(ウォッカ・マティーニを。ステアせずにシェイクで)」に憧れて、実際にバーで注文したという人もいるではないでしょうか。
マティーニは「カクテルの王様」とも呼ばれる、ジンとドライベルモットをミキシンググラスでステアして作る辛口のカクテル。
ジンではなくウォッカを使い、しかもステアではなくシェイクさせるというボンドの型破りなレシピが人気となり、原作小説の1作目で登場して以降、『007』シリーズの定番になりました。
「舌がしびれるほど冷やしてくれ」というせりふもあるように、氷を入れてシェイクするためにステアするよりもキンキンに冷えて、まろやかな味わいになります。
原作者のイアン・フレミングが熱心なカクテルの愛好家であり、その飲み方を勧められて試しに飲んだら気に入ったことで、小説に採用したとされています。
■「ショートカクテル」と「ロングカクテル」の違い
カクテルにはショートカクテル、ロングカクテルがありますが、「グラスが長いからロングカクテル」という意味ではありません。
ショートやロングは、飲み干すまでの「時間」のこと。
ショートカクテルは、短い時間で飲み干すことを想定されているために氷は入れず、手の体温でぬるくならないように容量が少ない足つきのカクテルグラスに注がれます。
一方のロングカクテルは、ゆっくり時間をかけて飲むことを想定されているため、氷が入っているのが特徴です。必ずしも長いグラスに入っているわけではありません。
ショートカクテルはアルコール度数が高いので、お酒の弱い人はロングカクテルがおすすめ。またショートカクテルを楽しみつつゆっくりしたい人は、冷えているうちに飲み干して、チェイサー(お水)を飲むとよいとされています。
本格的なバーに行くもよし、お家で手軽に作るもよし。この機会に、自分好みのカクテルを楽しんでみてはいかがでしょうか。
※お酒は20歳になってから
この記事の筆者:石川 カズキ
1984年沖縄県生まれ。筑波大学人間学類卒業後、会社員を経て芸人・作家・コピーライターに。エレキコミック・ラーメンズを輩出した芸能事務所トゥインクル・コーポレーション所属。第60回宣伝会議賞コピーゴールド受賞、LOFT公式YouTubeチャンネル『コントするイシカワくん』シリーズのコント台本・出演、KNBラジオCMコンテスト2020・2023協賛社賞受賞など。お仕事あればお気軽にご連絡ください。AIから仕事を奪うのが目標です。










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN