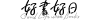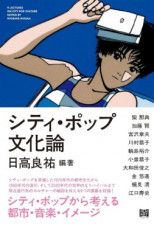「シティ・ポップ文化論」 [著]日高良祐
シティ・ポップとは、一九七〇年代後半〜八〇年代に日本で流行(はや)った、都会的で洗練された音楽。二〇一〇年代に突如、海外から再評価ブームが巻き起こった。
一過性の「バズ」ではなく息の長い社会現象となり、今現在、街中の至るところにシティ・ポップなるものの影響は広がっているように見える。楽曲のみならずデザイン面でも顕著だ。たとえば先日、私がコンビニで買ったミニサイズの飴(あめ)。パッケージデザインに漂うキラキラした詩情(ポエジー)は、なんだかとてもシティ・ポップっぽかった。
ブームはすでに一段落ついているとした上で、「文化」としてのシティ・ポップを考えようというのが本書。講義形式で全九講が展開、執筆陣は研究者多めでかなりディープだ。インターネット音楽の系譜、都市論、リスナー研究。専門領域が異なるため同一テーマでも見える景色が少しずつ変わり、飽きずにずっとワクワクできる。大人の楽しいお勉強だ。
再ブームの起爆剤となった竹内まりや「プラスティック・ラヴ」。YouTubeのアルゴリズムの気まぐれや、別の曲のジャケット写真でないと再生回数がのびないといった事情が面白い。インターネットなのにこの人間臭さときたら。
人は自分が生まれていない時代、育っていない街で鳴っていた音楽にも、懐かしさを感じ、愛(いと)しく思う生き物。「幻視」したイメージで胸をせつなくさせ、踊るのだ。シティ・ポップの魅力が星図のごとく描き出され、無限に広がる。
海外から降って湧いた再評価は、ともすれば「日本スゴイ」言説に陥る危険性も孕(はら)む。過去の音楽を「再開発」する時期(ターム)に入った今、TikTokから生まれる流行にも柔軟に対応してしっかり収益化をはかることは、後手に回ってきた業界の急務だろう。そうして得たお金を「将来世代にどれだけ投資できるか」が重要という指摘よ、音楽業界の人に届け!
◇
ひだか・りょうすけ 京都女子大講師(メディア研究)。共編著書に『クリティカル・ワード ポピュラー音楽』。










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN