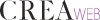2024年1〜4月にCREA WEBで反響の大きかった記事ベスト7を発表します。カルチャー部門の第1位は、こちら!(初公開日 2024年2月15日)
2024年2月3日土曜、梅田 蔦屋書店でお昼3時から始まった『BLANK PAGE 空っぽを満たす旅』刊行記念、内田也哉子トークイベント。会場は満席である。
「週刊文春WOMAN」連載5年分の対談の貴重な裏話に加え、母・樹木希林さんの奇抜な子育て、特殊な家族関係、夫・本木雅弘さんとのヒリヒリするような夫婦エピソードなど、濃厚な90分となった。

母を亡くした直後のオファー。初回執筆時の「記憶がない」
聴き手は、「週刊文春WOMAN」の編集長・井﨑彩さん。お二人は颯爽と登場……したのだが、椅子の座り方に手こずる珍事が。「おろろ」「よいしょ」と座り直すところから始まり、会場になごやかな見守りの空気が漂う。
無事ポジションが整い、いざ、トーク開始! まずはご家族と樹木希林さんのエピソードに花が咲く。内田家の子育ては何度聞いてもパンチが強い。也哉子さんは幼少期、テレビもおもちゃも与えられなかったという。鍋や傘を工夫して遊ぶことを教えられ、服は小学校を卒業するまで古着だった。
希林さんが海外ロケの時は「世界でいろんなことを見なさい」というこだわりのもと、学校を休ませ同行させたそうだ。スクリーンに映し出される家族の旅行写真も、日付が「1月14日」だったりする。学校始まってますよね!
「決して私を子ども扱いしなかった。これから大人になっていく中で、父という存在への疑問もそうだし、人生の根源的な疑問をぶつけたら、200%の心をちゃんと受け止めてくれて、返してくれる人でしたね」
と、也哉子さんは回想した。
樹木希林さんが亡くなったのが2018年9月15日。そして『BLANK PAGE 空っぽを満たす旅』の連載が始まったのが12月29日発売の創刊号。これについて、井﨑さんから驚きのエピソードが。
「也哉子さんに原稿をお願いしたのが、9月末だったんじゃないかなと思うのですが」
希林さんが亡くなった同月の打診! 也哉子さんもびっくりしたと話す。
「こんな大変な時に何を書けばいいんだって。できるはずがないと思ってたんですけど、一番私に影響力があった人物が、本当にこの世から消えてなくなる、家族を失うという体験が初めてだったので、藁をもすがる思いでエッセイをまず書いて」
第一回目は、対談ではなく、樹木希林さんのエッセイ「Driving My Mother」。也哉子さんは当時の記憶がないという。「Driving My Mother」の冒頭の一文にもこうあった。
“うわのそら。この言葉が今、最も自分の心の有り様を表している”
「心を紐解いていく作業。原稿を送った時は、放心状態でしたね。そこからやっぱり人に会いたい気持ちがムクムクと湧き上がってきて」
そうして対談形式が決まったという。
「ブランクっていうのは、空欄、空っぽという意味があるんです。すごく寂しさで溢れているけれども、視点を変えれば、どのようにでも真っ白を埋めていける、満たしていける。喪失と希望が両方存在するような気持ちで始まったんですね」
病床に伏す樹木希林が語っていた、衝撃の言葉
会場がどよめいたのが、希林さんの半年後に内田裕也さんが他界したときの話だ。
「父もいろんな病気を持っていて入退院を繰り返していたので、母に『お母さんが先に亡くなってしまったら、私はお父さんと残されてどうしたらいいの?』と、思わず心の声を漏らしたら、母が『大丈夫、必ず私が連れて行くから心配しないで』って言われて。その時は『もうまたまた〜』と笑ってたんですけど。こればっかりはびっくりしましたね。本当のことはわからないですけど、嵐のように去っていきましたね」
どよどよどよ……。会場にビックリな空気が流れる。偶然としてもすごい話である。
也哉子さんの対談の一番目は谷川俊太郎さんだ。
「おもちゃも与えられなかった幼少期、母の本棚の中の片隅に絵本だけはあって、その一冊が谷川さん翻訳のフランスの絵本『ジョゼット かべを あけて みみで あるく』という絵本で。日本語を耳にしても美しい、目にしても美しい、と感じた初めての本だったので、今砂漠のようになった心に、一滴でも二滴でもいいから、恵みのような言葉を頂きたいと思って。
特に死や両親のことを話すつもりはなかったんですけれど、心の中のもやみたいなものを谷川さんが察知してくださったのか、真っ先に仰ったのが『自分はね、死っていうものを実はすごく楽しみにしてるんだ』という言葉だったんですね」
谷川さんだけでなく、自然と、対談のお相手とは、心のなにかが共鳴するように、大切な家族との生と死について語ることになったという。

伊藤比呂美さんのお父様の骨をコーヒーミルで砕くエピソード、ご自身の死が近づいていることを悟っていた坂本龍一さんとの話など、どれも衝撃的。ただ、生と死、大切な人を弔うという内容は誰しも避けられないテーマ。共感するところのほうが多くあり、客席も、大きく何度も頷く人、口に手を当て聞き入る人の姿が見えた。
ここからは井﨑さんによる、対談の驚くべき裏話。
「普通、対談にはスタッフや編集が何人か同行するのですが、(也哉子さんに)『ついてくるな』と言われまして(笑)。『本当の話っていうのは1対1じゃないと聞けないと思っているので』と。でも原稿が上がってみて、確かに1対1じゃなきゃできない話だなと思いました」
たとえば2回目の小泉今日子さんは、芸能活動を休止しているときだったが、也哉子さんに『当日は一人の人間としてすっきりと也哉子さんの前に座ってみたいと思っています』という一言が来て、話が進んだという。
也哉子さんは「本当は私も会いたかったんですが……」と本音を漏らす井﨑さんに「ごめんなさい〜」と恐縮しながらも、
「普段はスタッフがいらっしゃる方も、お一人でポツンといてくださる。そして誰しも持っている影みたいな部分を私が差し出すと、必ず普段は出さない影の部分を出してくれて、これはやっぱり1対1の醍醐味というか。
年齢、状況、経歴、全然違う15人の方々ですが、皆さん本当に一人ぼっちがとってもよく似合うんですよね。自分と仲良くできている人たち。転んだり、擦りむいたりもしてきたけれども、自分の力で立ち上がって歩いてきた人たち。だからこそ優しくて強い。それがすごく共通していたなと思います」
“一番の読者” 夫・本木雅弘の「ぐうの音も出ないひとこと」
さて、連載の5年間、也哉子さんにとって常に一番の読者だったのが夫の本木雅弘さんだったという。
井﨑「(単行本刊行の際)本木さんに一言いただけませんか、とお願いしたら、『内田也哉子という人が、有名な芸能人の両親や妻という肩書きから脱しよう、人生後半頑張ろうともがいて毎回書いてきたのに、最後に自分が出たらダメじゃないですか』とおっしゃって、ぐうの音も出ず……」

やだモッくんカッコいい! しかし井﨑さんは「一言」とはまた違う角度で「夫婦対談」をお願いするというウルトラCを思いついた。それが2023年12月22日発売の「週刊文春WOMAN」創刊5周年記念号(Vol.20)「特集:母と娘って」の夫婦対談「内田也哉子が聞く、本木雅弘『婿の言い分』」である。
井﨑「(本木さんは)いろいろあったけど仲のいい夫婦です、みたいな企画はつまらないから絶対やりたくない、とおっしゃって」
内田「そう、ヒリヒリした部分も晒したいって」
21ページにわたる特集は、本当に「これ言っても大丈夫?」と驚くほど、ぶっちゃけた内容となった。
9時間かかったけど「このレベルの話し合いは日常茶飯事」
この夫婦対談は撮影を含め6時間、打ち合わせ時間も合わせると9時間かかったという。しかし、也哉子さんご夫婦にとって、このレベルの話し合いは日常茶飯事。問題があると、十何時間も話し続けるそうだ。もはや戦い! 也哉子さんは笑いながら言う。
「戦うというより精査してるんですね。思いが微妙に違うなら、その微妙さの加減を知りたい。しつこいの(笑)。お互いしつこさが似てるから離婚危機も何度もあったけれども、ここまできたら諦めずに……とかいいつつ、明日もし離婚してたらごめんなさい」
客席から思わず笑いが起こる。

「やっぱり他人だから、いつ別れてもおかしくない。その危険をいつも目前に置いておけば、この日常が尊くなるっていうか。突き詰めると、違う扉から入ってくるだけで、出会える部屋はもしかして一緒なのかな……と」
ご両親の内田裕也さんと樹木希林さん夫婦は、結局、別れずに50年。
「母の方がしがみついている風に世間には見えていたかもしれないけど、父もいざ別れましょうとなると離婚届を持ってこなかったり、結局両方とも別れたくないんじゃないかっていう。それがすごく不思議でしたね。別れなかった2人にしか見えなかった景色があったと思います」
と振り返る。
「母は『あなた自身が変わらなければ、たとえ離婚して相手を変えようが、結局何も変わらないんだよ』と。これが真髄か、と噛みしめて、放棄したくなったら、もうちょっと頑張ろう、と。両親がそうであったように、続けた先にしか見えない、わずか一瞬の“きらめき”があるかもしれない。今はそれを希望に、一生懸命駆り立てています」
也哉子さんが体験した激しい家族とのサバイブと別れ、それを埋める旅のエピソードは客席に不思議な一体感を生んでいた。
自身の家庭と重ねる方、心の在り方を模索している方、質問コーナーでも熱い想いがいくつも飛び出す。客観的に物事を見るにはどうすれば。家族の存在とは――。もはや質問コーナーというより、1つの穏やかな対話の場。「深い! 答えられるかしら。頑張ります」と、一つ一つゆっくり言葉を探し答える也哉子さん。
時間制限が無かったら、彼女はずっと質問に答え続けていた気がする。

「友達や家族、そして思いもかけない人から、自分を気づかされますね。人との出会いで別の角度が見える」
そう答えいていた彼女にとって、きっと、対談の15人と同じくらい、この1時間のトークイベントも空欄を埋める大切な出会いなのだ。
終了後、会場に残るスタッフに「一筋のきらめき、という言葉に救われました」と感想をくれた方がいた。それをあとから聞いた也哉子さんはこう言った。
「救われたのは私のほうなのに」
彼女の空っぽを満たす旅は、まだまだ続きそうだ。
文=田中 稲
撮影=佐藤 亘(ポートレート、書籍)、編集部(イベント風景)
ヘアメイク=渡邉ひかる(ambient)










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN