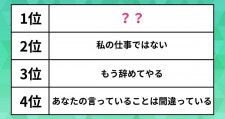願わくは認知症や寝たきりにならず生涯を全うしたい――。人生100年時代、老化をいかに防ぐかが鍵であり、そのためには健康食材が欠かせない。専門家いわく、「おつまみ」の印象が強いチーズこそ実は最強のアンチエイジング食品。チーズの秘めたる力に迫る。【齋藤忠夫/東北大学名誉教授】
***
日本の食卓に足りないものは何か――。
2013年にユネスコの無形文化遺産に登録され、私たちが世界に誇る「和食」は、塩分摂取量が多めになってしまう弱点を除けば、おいしさと栄養バランスにおいてほぼ完成されている食事といえるでしょう。
しかし、日本が超高齢社会の道を進んでいるいま、私たちは適切に栄養を摂取するにとどまらず、それにプラスして病気予防等に寄与する機能性を持った食品を取ることが求められています。
そして日本人には、さまざまな機能性を持った、ある食材の摂取が不足しています。例えば、その食品は認知症予防につながる成分を含んでいるにもかかわらず、「世界の酪農情況2022」によれば、国民1人当たりの摂取量は第1位のフランスの10分の1に過ぎません。世界の中でも高齢化の先頭を走る日本だからこそ、認知症予防等に役立つこの食品をもっと取るべきではないかと私は考えています。
正解は、日本人には「チーズ」が足りていないのです。
〈こう説くのは、東北大学名誉教授の齋藤忠夫氏だ。
畜産物利用学・応用微生物学を専門とし、特に乳製品に詳しい齋藤名誉教授は、日本では健康食品として定着しているヨーグルト(発酵乳)だけでなく、チーズがもたらす優れた健康効果にも、もっとスポットライトが当たるべきだと言う。
『チーズの科学』の著作がある齋藤名誉教授が、驚くべき健康作用を持ったチーズの奥深い世界を解説する。〉
近年注目される「認知症予防効果」
乳製品が体に良いのは誰もが知っていると思います。そして、私たちの健康維持・促進に役立っているのは、乳製品に含まれる乳酸菌なのだと思っている方は多いでしょう。
しかし、そこにはちょっとした“誤解”が含まれています。もちろん、乳酸菌自体がさまざまな健康効果をもたらしてくれることは間違いありませんが、実は発酵の過程で乳酸菌が生み出す代謝産物や、乳酸菌自体が分解された成分もとても重要なのです。乳酸菌やカビで一定期間発酵(熟成)させたチーズには、さまざまな機能性を示すペプチド(アミノ酸化合物)が多種類含まれていて、その点ではヨーグルトよりも魅力的だとすらいえます。
そのチーズの健康効果として、近年注目されているのが「認知症予防効果」です。かねて、「チーズなどの発酵乳製品を習慣的に摂取している人は老後の認知機能が高く保持されている」という疫学的調査結果が数多く存在するものの、どのような成分が有効なのかは不明でした。
カマンベールチーズが認知症予防に寄与する可能性
しかし、キリン株式会社などの研究グループが行ったマウス実験によって、カビ系のカマンベールやブルーチーズに含まれるオレイン酸アミドとデヒドロエルゴステロールという二つの成分が、脳内の免疫細胞(ミクログリア)を活性化してアルツハイマー病の原因とされる老廃物のアミロイドβの沈着を有意に減少させることが分かったのです。
また、株式会社明治が、70歳以上の軽度認知障害(MCI)の女性を対象に、白カビ系のカマンベールチーズを1日2ピースずつ3カ月間摂取してもらったところ、学習や記憶に大きく関係するBDNF(脳由来神経栄養因子)の血中濃度が、カビ発酵していないチーズの摂取群と比較すると有意に高くなりました。カマンベールチーズが認知機能の低下抑制や認知症予防に寄与する可能性が示されたのです。
さらに、キリンホールディングス株式会社の臨床試験によって、カマンベールチーズに含まれるβ−ラクトリンというペプチド成分に、記憶力や注意力といった脳機能を維持する働きがあることが明らかになっています。
「カゼイン」こそが、チーズのチーズたるゆえん
以上のように、認知症予防効果が期待できる白カビ系チーズ以外にも、優れた機能性からとりわけ高齢者の方により多く食べてもらいたいチーズがたくさんあります。以下を読み進めていただければ、その理由がお分かりになると思います。
水分を除くと、チーズの成分はタンパク質と脂質がほぼ半々になります。そして、チーズの主要なタンパク質は「カゼイン」と呼ばれるもので、ヨーグルトでは固まっている部分に相当します。このカゼインこそが、チーズのチーズたるゆえんのひとつです。
一般にタンパク質は熱に弱く、卵も肉も加熱すると硬く熱変性してしまいます。ところがカゼインは、タンパク質の中でも例外的に、110度で10分加熱しても壊れない耐熱性があります。また、チーズを作るときにキモシン(レンネット)という酵素で乳を固めますが、その際にカゼインの分子が集まってカードという網目構造を作ることで、チーズにはピザを食べる時に実感できる「糸引き性」が生まれます。この糸引き性こそが独特の食感とおいしさをもたらし、チーズ特有の味わいを生み出してくれるのです。
サルコペニアを防いでくれる
さらに、このカゼインの中には、体内で作ることができず、食事から摂取するしかない9種類の必須アミノ酸のうちのひとつである「ロイシン」が多く含まれています。必須アミノ酸の中でも筋肉量を増やすために欠かせないのが分岐鎖を持つバリン、ロイシン、イソロイシンという3種類のアミノ酸で、その中でもロイシンは最も筋肉生成に寄与することが分かっています。筋肉はいくつになっても増やせます。チーズはサルコペニア(加齢に伴う筋肉量の減少)を防いでくれる優れた食品なのです。
近年、サルコペニア予防のために、高齢者であってもタンパク質を積極的に取ることが推奨されています。しかし、過剰なタンパク質の摂取には腎臓に負担をかけてしまうリスクもあります。したがって、大量のタンパク質を「取る」のではなく、良質なタンパク質を「選ぶ」ことが求められます。その意味では、筋肉生成に最も効果的なロイシンを多く含むチーズは、素晴らしい「抗サルコペニア食品」に位置付けられるでしょう。
牛乳を10倍濃縮
サルコペニアの先に高齢者を待ち受けているのは、寝たきりなどの要介護につながるフレイル(虚弱)です。フレイルに陥らないためには、日常的に適度に体を動かすことが不可欠です。しかし、ちょっとしたつまずきや転倒によって骨折し、体を動かせなくなってしまうリスクを高齢者は抱えています。そのため、フレイル予防策としては、筋肉増強に加えて骨を丈夫に保つことが求められます。実はこの点においても、チーズは極めて大きな力を発揮します。
大雑把に言うと、チーズとは牛乳を10倍濃縮した食品です。骨の元となるのは何といってもリンとカルシウムですが、チーズに含まれるリン酸カルシウムの濃度も、牛乳の約10倍ということになります。例えば、牛乳を200ミリリットル飲むとそれだけでお腹が膨れますが、チーズはその10分の1の重量で同じだけのリン酸カルシウムを摂取できるわけです。さらに、チーズはカルシウムの吸収を阻害する食物繊維を含んでいないことも特徴に挙げられるでしょう。
いくら健康のことを考えて牛乳を飲もうとしても、お腹を下したりしてしまう乳糖不耐(症)の方がいます。しかし、チーズは製造の過程で、乳糖は液体のホエイ(副産物として生成される乳清)に移行するため、ほとんど残っておらず、たくさん食べてもお腹を下すことはまずありません。この点も、牛乳は苦手で飲めないけれど……という高齢者にもチーズがお勧めの理由です。
このようにあらゆる観点から、骨粗鬆症予防のためのカルシウム摂取源として、チーズは理想的な食品といえるでしょう。
虫歯予防効果は世界の常識
さらに、チーズは虫歯予防にも役立つことをご存知ですか? チーズ中のリン酸カルシウムは傷ついた歯の表面や歯に開いた穴を補修する役割を果たします。チーズはpH(水素イオン濃度)がそれほど低くないので歯を溶かしにくく、カゼインが歯の表面を覆い虫歯菌や歯周病菌の増殖を防ぎます。加えて、硬質チーズをよくかんで食べると、リゾチームを含む唾液の分泌が促進されて抗菌作用が増します。
こうした総合的な作用から、WHO(世界保健機関)は2003年に、硬質チーズの虫歯予防効果を、「可能性あり」のキシリトールよりランクが上の「高い可能性あり」に位置付けています。チーズの虫歯予防効果は世界の常識ですが、日本ではあまり知られていませんね。
体内で燃焼しやすい脂肪
ここまで見てきた通り、認知症予防の効果が期待され、サルコペニアやフレイル対策にも役立つ。さらに、牛乳のようにお腹を下す心配も要らない――。健康寿命が気になる中高年にとって、チーズはまさに最適の食品なのですが、塩分が多い上に太りやすそうというイメージを持っている方も多いようです。しかし、それは誤解です。
まず、最も塩分濃度が高いブルーチーズでも4.5%以下ですから、他の食品と比べて特別に多いわけではありません。
また、チーズは脂肪を多く含みますが、乳脂肪に由来するチーズの脂肪は、動物性脂肪の中でも中鎖脂肪酸を多く含むため、体内で燃焼しやすく蓄積されにくいので、肥満を防止する性質があります。
しかも、チーズに豊富に含まれているビタミンB2は脂肪の体内燃焼を促進し、さらにカルシウムも脂肪蓄積を防いでくれます。従って、実はチーズはダイエット向きの食品でもあるのです。その上、コレステロールの吸収を阻害するペプチドを含んでいることから、メタボリックシンドローム予防にも効果を発揮してくれます。
チーズは低GI食品
生活習慣病の話をすると、ある時、知り合いの病院の先生に、医師として最もなりたくない病気は何ですかと尋ねたことがあります。その先生は「糖尿病」と答えられました。
なぜ糖尿病なのか。糖尿病の恐ろしさは血液中のブドウ糖が過剰に増えることによって、全身の血管が傷ついてしまう点にあります。その結果、目が見えづらくなる糖尿病網膜症、腎臓の機能が低下する糖尿病腎症、神経の働きが損なわれる糖尿病神経障害などにつながり、脳の血管が劣化すれば脳出血も誘発します。
では、糖尿病を避けるにはどうすればいいのか。血糖値の急激な上下動、いわゆる「血糖値スパイク」を防ぐことが大事になります。いきなりご飯やパンなどの炭水化物から食べ始める食習慣が血糖値の急激な上昇につながりますが、最近注目されているのが「低GI(グリセミック・インデックス)食品」です。
GI値の低い食品ほど、摂取時の血糖値の上昇は穏やかになります。チーズのGI値は30〜35と低く、トマトなどと同程度です。GI値55以下が低GI食品とされており、チーズは精白米の84に比べてかなり低く、低GI食品といえます。
食事の前にチーズをひとかけら
血糖値スパイクを防ぐための方法として、まずサラダ等の野菜から食べる「ベジファースト」がよく推奨されます。しかし野菜自体のGI値は低くても、糖や塩分と油を含んだドレッシングをかけたりするので、ベジファーストが必ずしも血糖値スパイクを防ぐとは言い切れません。
ですから私は、食事の15分から20分前にチーズをひとかけら(6Pチーズの1ピース)食べることをお勧めしています。実際、私の知り合いの医師は、それを実践して糖尿病予備軍から抜け出されました。
チーズこそ「最強のアンチエイジング食品」
さまざまな健康効果をもたらす上に、“カゼインの奇跡”による独特の加熱時の糸引き性の食感と熟成チーズ中のうま味成分(グルタミン酸)で食が細った人も食欲をそそられ、かつ歯を失った人でもそしゃくしやすい――。チーズこそ「最強のアンチエイジング食品」と言っても差し支えないでしょう。にもかかわらず、日本ではどうしても「食事」というよりも「おつまみ」の感覚が強く、同じ乳製品であるヨーグルトと比較しても地味で「脇役」の座に甘んじているようです。
これまで繰り返し説明してきたように、チーズはさまざまな優れた機能性が明らかになっている上に、健康に役立つ未知のペプチドがまだ多く存在することも分かっています。
高齢化がますます進む社会において、みなさんがチーズを「主役」にして下さることで、日本人にさらなる健康長寿がもたらされることは間違いありません。
齋藤忠夫(さいとうただお)
東北大学名誉教授。1952年生まれ。東北大学大学院農学研究科博士課程修了。農学博士。日本酪農科学会会長、アジア乳酸菌学会連合会長、日本農芸化学会フェロー等に就く。乳製品に関する研究の第一人者で、著作『チーズの科学』、『ヨーグルトの事典』(共編)等がある。
「週刊新潮」2024年5月16日号 掲載










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN