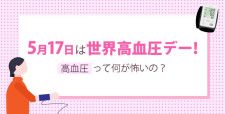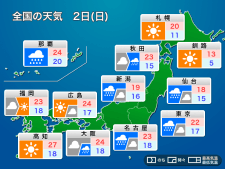今月17日は「高血圧の日」だ。世界高血圧連盟が定めた疾患啓発日に準じたもので、さまざまなイベントが行われる。
高血圧と診断された際、「減塩」を申し渡された人は多いだろう。各国の高血圧治療ガイドラインでの推奨食塩摂取量は、1日当たり6グラム未満。この数値には、科学的な裏付けがある。
日本高血圧学会の推奨量も6グラム未満だが、厚生労働省編の「日本人の食事摂取基準(2020年版)」の摂取目標量は、成人男性が1日9グラム未満、成人女性は1日7.5グラム未満と、基準が緩い。
ただし、来年度改訂予定の2025年版では、成人の目標量をそれぞれ0.5グラム引き下げ、高血圧と慢性腎臓病の重症化予防を目的として、6グラム未満/日という数値を新しく設定するらしい。
実際、厳格な塩分制限は、病院で処方される降圧薬並みの効果を発揮する。
米ヴァンダービルト大学医療センターの研究グループは、米国内の住民(50〜75歳、中央値61歳)を対象に、高塩分食(5.9グラム/日)と低塩分食(1.27グラム/日)の血圧値を比較している。
調査では、高塩分食群と低塩分食群の上の血圧値の変化を観察。
その結果、低塩分食群の平均血圧値が、わずか1週間で8mmHgも低下したのだ。次の週は両群の摂取量を入れ替えてみると、せっかく下がった血圧値が高塩分食で再び上昇してしまった。
ただし、試験を一回り終えた時点での変化量では、参加者の7割以上で血圧が低下しており、その中央値はマイナス4mmHgに及んだ。低塩分食の降圧効果は、年齢、性別、人種、登録時の血圧値や糖尿病など基礎疾患の有無にも影響されなかったのである。
すでに降圧薬を飲んでいる人は解るだろうが、血圧を4〜8mmHg下げるのは至難の業だ。単剤ではらちが明かず、2剤、3剤と薬が増えることも珍しくはない。
しかし、減塩に取り組むだけで降圧薬を飲まずに済む、あるいは減らせる可能性があるわけだ。さすがに1日2グラム未満は厳しいが、「高血圧の日」を機に、1食2グラム未満から始めてみよう。
(取材・構成/医学ライター・井手ゆきえ)










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN