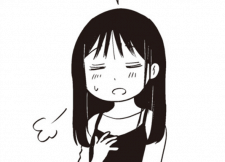作家・北原みのりさんの連載「おんなの話はありがたい」。今回はイギリスの中絶クリニックを視察して考えた、日本との大きな差について。
* * *
ゴールデンウィークに、イギリスの中絶クリニックを視察してきた。
「中絶クリニック」とサラリと書いてはみたが、日本にはそのような病院はない。妊娠すれば産婦人科に行くしかなく、中絶するときも妊婦健診に来た女性たちと同じ待合室で待つ。
……という日本の現実は、激しい形相で「ノォーッ!」と叫ばれるようなことなのだということを、私はイギリスで初めて知った。イギリスの中絶クリニック、そこは日本の現実とあまりに違い、私はこういう世界を「想像すらできない」社会を生きているのだと思い知らされた。ちょっと、打ちのめされている。
ロンドンで助産師として働き、日本では昨年認められた経口中絶薬の情報を発信してきたおざわじゅんこさんの手引きで、サウサンプトンにあるBPAS (British Pregnancy Advisory Service)という、中絶処置を提供する団体を訪ねた。BPASは国内に50カ所以上の拠点があり、予算はイギリスの保険制度でカバーされ、中絶だけでなく、妊娠を迷う女性へのカウンセリングや、避妊の相談、避妊処置(男性に対しても)なども行っている。
イギリスにはNHSと呼ばれる医療制度があり、NHSの医療機関では全ての医療が無料で提供される。当然、妊娠中のケア・出産・中絶も国が負担する。ちなみに日本で出産・中絶は自己負担だ。出産は産んだ後に助成金を申請できるが、10万〜20万円かかる中絶は完全に自費である。日本の皆保険制度は女に冷たい。
制度が冷たければ、情報も薄い。厚生労働省のサイトで「中絶」と検索すると、多くの国で自宅で服用されている経口中絶薬について、「飲んだ女性に健康被害が出ているので個人輸入しないで」という情報が難しい言葉で脅し気味に記されている。一方、イギリスのNHSのサイトでは、「中絶」と検索すると、やさしい英語で簡潔にこう記されていた。「中絶とは妊娠を終わらせるための処置です」「妊娠は、薬または外科的処置で終わります」。
さて、視察である。

私としては、クリニック内を見てBPASスタッフから話を聞く……とイメージをしていたのだが、驚いたのは守秘義務に関する書類にサインした上で、当然のように診察の場を見ていくように提案されたことだった。今日は17人の予約が入っていて大変忙しいのだけど、もし女性たちが了承してくれたら、一緒に診察室に入ってみたら、と。
英語を聞き間違えているのかと思うほどに、衝撃的な提案に私には思えた。センシティブな内容が語られるに違いない、人生の大きな局面であるカウンセリングの場に、全くの第三者が関わっていいはずがないと思ったのだ。そんな私の戸惑いはよそに、「もちろん、患者さん次第だけど、まず聞いてみましょうね!」と話はどんどん進み、最初にカウンセリングに訪れた女性に、代表の女性が立ち話風に「どう?」みたいな感じで声をかけたところ、「あーどうぞー」となり、呼ばれた私が慌ててカウンセリングの部屋に飛び込んだのだった。ここまでものの5分くらいの話である。
心の準備がないまま、私は大きな窓のある明るい部屋に通された。日本と同じようにパソコンを見ながらパチパチと情報を打ち込む医師(かと思ったら助産師)の前に、さっきクリニックに着いたばかりの患者が座っている。30代前半くらいだろうか。やはり30代前半くらいに見える女性の助産師がリラックスした雰囲気で「最後の生理はいつですか?」と聞き、答えを聞くと「妊娠が確定していたら、今日中の処置を希望しているんですよね」と確認をしている。2人の間に一切緊張感はない。笑っているわけではないが和やかであり、「ここは私の声が聞かれる安全な場所」と女性が信じているのがわかる。
「避妊しなかったのか?」「どんな避妊をしたのか?」「結婚しているのか」「夫の了承は同意するのか」「よくよく考えたのか」「後悔しないのか」「どうしても産めないのか」「なぜ産めないのか」「助けてくれる人はいないのか」「1人で判断したのか」「相談できる人はいるのか」「仕事はしていないのか」「経済的に苦しいのか」……そういう類のくだらない質問は一切なく、患者の意思と体調の話だけが語られるのだ。

なにこれ……メモを取るのも忘れ、ボーッと2人の会話を聞いていると、助産師が「じゃ、エコーで確認しましょう」と爽やかな調子で女性を促した。広々とした診察室の片隅に、カーテンに囲まれたベッドがある。慌てて、あ、すみません、エコーの最中私はどこにいれば……とおろおろしていると、「彼女(←私)にも見てもらっていい?」と助産師が女性に確認してくれ、「もちろん、だいじょうぶ」と女性も何でもないよ〜というトーンで伝えてくれ、私は助産師の背後からエコー画面を見ることになった。黒い画面に浮かび動く白い影を見ながら、助産師が手際よく胚のサイズを確認し、データを打ち込み「妊娠6週ですね」と女性に伝えている。それから助産師は女性に向き合って「今日、薬を処方できます」と爽やかな声で明るく伝えるのだった。
妊娠週数によっては薬の種類を変えたり、吸引処置やD&E(頸管拡張及び子宮内容除去術)が必要だったりすることもある。だからこそ、病院にとって必要な情報は、正確な妊娠週数と女性の意思確認であって、彼女の価値観や人生や人間関係ではない。また、見知らぬ者をその場に立たしても良いと患者も助産師も考えるほどに、「今ここで行われていることは当たり前の女性の権利」という意識が根底に力強くあるのであった。
女性の意思が最優先で守られる。その当たり前のことに、私は激しく動揺した。診察室にいたのは10分もない。見知らぬ女性の決断が行われる場。その温かさに激しく動揺し、私は彼女たちにきちんとお礼を言えたのかどうか、、、覚えていない。
BPASから帰って数日後、名古屋で30代の女性が暮らしていた部屋から2人の乳児の遺体が見つかり、女性が逮捕されたというニュースが流れた。彼女がどんな生活をしていたのかはわからない。それでも、と思わずにはいられない。もし彼女が、あの診察室に入れていたのならば。もし、彼女がそこで自分の決断を、優しく聞いてもらえていたのならば。ここが、そんな国だったのならば、と。










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN