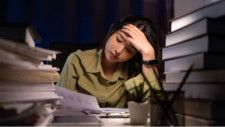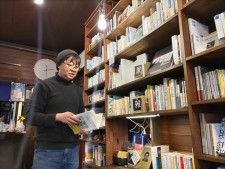読書離れが進むといわれる今どきの子どもたち。本を読んでほしいけれどなかなか定着しないというご家庭に、子どもが読書にハマるオンライン習い事「ヨンデミー」を立ち上げた笹沼颯太さんが、子どもを本好きにする方法をアドバイス。さて、本を読まない子どもには、どうすれば「本は楽しいよ!」ということを伝えられるでしょう? 家庭でできる効果的なアクションを、笹沼さんに教えてもらいました。
■「本っておもしろいんだ!」と実感させるにはどうする?
――ヨンデミーさんに寄せられる「子どもの読書のお悩み」には、どんなことが多いですか?
やはり「うちの子、本を読まないんです」という親御さんからのお悩みは本当に多いです。でも、決して本が嫌いなのではなく、そもそも「本はおもしろい」ということを知らない場合もあるのです。
つい、本を「読ませる」ことばかり考えがちですが、その一歩手前、子どもが「本って、楽しい」と思えるきっかけは、実はとても大切だと思うんです。
たとえば、親がリビングでテレビを見ているとき、子どもが入ってきたとしましょう。子どもは途中から見るのでストーリーもよくわかっていないのですが、親が楽しそうに見ているからなんとなく一緒に見てしまう……。こういう場面は日常でもよくありますよね。
親が楽しそうにしていると、やっぱり子どもはそれに対して興味を抱くと思うのです。これは、読書でも同じことなのです。
――…ということは、やはり親も本を読むことが大切でしょうか。
本を無理やりにすすめたり読ませたりするよりも、親御さんが読書をしている姿を子どもに見せる方が、本の楽しさを伝えるのにはるかに効果的です。
身近にサッカーをしている人がいると、その姿を見て「サッカーって楽しいのかもしれない」と自然に思い描けますよね。これと同じことなのです。その姿を見て「なんだか楽しそうだな」「夢中になっているな」と気持ちが動くのですね。
■「ふり」でも大丈夫。子どもの身近な「読書家」になってみる
――つまり、子どもの身近に「本好き」がいればいいのですね。
そうなのです。でも、これは本当にご家庭によるところが大きい。たとえば親が読書家なら、そばにいる子どもはつねに「本っておもしろいのかもしれない」「おもしろいんだろうな」とあたりまえに感じる状況にあると思うのです。
でも、家族や友達など、身近なところに本を読む人がいない場合はどうでしょう。その子どもには「本はおもしろい」という発想すらないこともあるのです。本は「読まされるもの」だと思っていることが多いくらいです。
とはいえ、親御さんに「だから本を読んでください」と無理強いするつもりはないのです。
そこで、ひとつのテクニックをお伝えします。極端な例ですが、「読んでいるふり」でも、子どもはその楽しさが伝わるのです。
――読んでいるふりでも?
そうなのです。たとえば、子どもと一緒に図書館で児童書や絵本を借りてきたら、実践してみてください。親御さんは、家に帰ってソファに座り、その本のぺージをペラペラとめくって読んでいるふりをしてみるのです。もちろん、本当に読んでもいいですよ!
子どもにその姿を見せられたら、時間は3分……1分でもいいです。そして本を閉じて、キッチンに向かうなどして、その場を離れてみてください。すると子どもは「何を読んでいたんだろう」と、きっとその本に手を伸ばすでしょう。
子どものことをスルーしてでも、本を読んでいるふりをするのです。子どもは「なにがそんなにおもしろいの?」と知りたくなります。そして、これが「本はおもしろいものなのかもしれない」と思うきっかけづくりにつながるのです。
これなら、たとえ本が得意ではない親御さんでも苦にならないはずです。ぜひ試してみてください。










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN