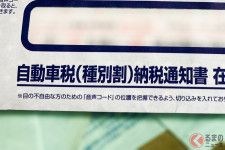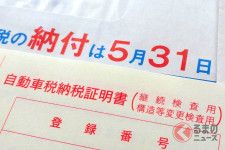走行税とは?
走行税(走行距離課税)とは、走行距離に応じて自動車に課税される税金で、政府が新たに導入を検討している税金の1つです。
ハイブリッド車や電気自動車などの普及、若者を中心とした自動車離れにより、燃料税や自動車税など従来の自動車関連の税収が減少しているため、国の歳入確保を目的に導入が検討されています。
X(旧Twitter)では「1km5円」が課税されるというデマ情報が拡散されましたが、現段階では導入時期や金額について明確な決定はされておらず、政府は導入に向けてあらゆる議論を進めている段階です。
なお、ニュージーランドではRUC(Road user charges)と呼ばれる「道路利用者料(走行税)」を既に導入しており、ディーゼル車と総重量3.5トン以上の大型車両を対象に、1000km=約5000円が徴収される方式です。
日本ではまだ検討段階なので実際には導入されない可能性もありますが、このまま税収が減少していけばいずれは走行税が導入されるだろうという見方が多いため、現在走行税が注目を集めています。
走行税の導入による影響
走行税が導入された場合、走行距離に応じて課税されるため、主に以下3つのような影響が予想されます。
●ガソリン車とエコカーで税収が平等になる
●自動車を保有しやすくなる
●運送や交通業界で値上げが起こる
現在自動車にかかる税金には、排気量に応じて金額が変わる「自動車税」やガソリンなどの燃料にかかる「燃料税」があり、エコカーには減税措置が取られています。
しかし走行税が導入されれば、走行距離に応じて課税されることで排気量別の課税方式ではなくなるため、車種に関係なく平等に課税されることになるでしょう。
また、走行距離に応じた課税方式となることで、日常的に自動車を使用する人の税負担が増える一方、車移動は週末のみなど走行距離が少ない人の税負担が減ることで、車を保有しやすくなることが予想されます。
ただし、公共交通機関や物流、レンタカーなどの走行をなりわいとしている業界では、税負担を補うために利用料や配送料などを値上げすることが予想されるため、結果的に利用者の負担が増える可能性は高いでしょう。
まとめ
走行税とは、走行距離に応じて課税される方式の自動車税で、自動車関連の税収減少による国の歳入確保が厳しくなったことで、財源の確保を目的として政府が検討している税金の1つです。
「1km5円が課税される」というデマ情報が一時期拡散されましたが、現段階では導入時期や金額について明確な決定はされておらず、導入も確定ではありません。
しかし、走行税は自動車を利用する人だけでなく、交通機関や物流を利用する人など、自動車の保有に関係なく多くの人の生活に影響する可能性が高いため、今後の動向に注目しておくと良いでしょう。
執筆者:梅井沙也香
FP2級










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN