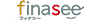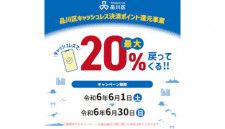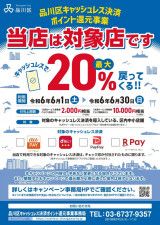「スマホ決済」は、今やクレジットカードに次いでキャッシュレス時代の中心的な役割を果たすようになりました。スマートフォンを用いた決済は今後も増加することが見込まれており、ますます手放せない存在になりそうです。
【モバイル決済の取引額の予測】
しかし2019年7月4日、スマホ決済の推進に冷や水を浴びせる出来事が起こりました。セブン&アイ・ホールディングスの「セブンペイ」が、不正アクセスによって5500万円の被害が生じた可能性があると発表したのです。
導入からわずか1カ月で廃止を決定
セブンペイは、セブン&アイが独自に開発し2019年7月1日に開始したバーコード決済サービスです。決済の最前線である小売り大手が自ら開発し、さらに消費増税に際して実施が決まっていた「キャッシュレス・ポイント還元事業」も相まって、誰もがセブンペイの成功を予想しました。
しかし大方の予想を裏切り、セブンペイは大失敗に終わります。原因は脆弱なセキュリティーにありました。海外からとみられる不正アクセスを大量に受け、サービス開始2日目には利用者から「身に覚えのない取引」が報告されます。3日目に海外IPからのアクセスを遮断し、その翌日には新規登録の停止に追い込まれました。
セブン&アイは監視体制の強化や外部IDによるログインの停止といった対策を講じますが、利用者の不信感を拭うことはできず、8月1日にセブンペイの廃止を決定します。実質的に数日で終了したサービスながら、7月末までの被害額は3860万円に達していました。
後の調査で、セブンペイは複数端末からのログインに対する対策や二段階認証といった基本的なセキュリティーが不十分であり、不正アクセスに対する防御が弱かったことが判明しています。事件の責任を取り、セブンペイの社長は退任し、セブン&アイ経営陣も役員報酬の返上を発表しました。
バーコード決済の覇者「PayPay」が目指す収益化
セブンペイと対照的に、スマートフォン決済で成功しているのが「PayPay」です。登録ユーザーは5000万人を突破し、2022年度の取扱高は7.9兆円に上りました。キャッシュレス推進協議会によると、2022年のバーコード決済利用金額はおよそ10.8兆円ですから、PayPayがいかに大きなシェアを握っているかがうかがえます。ちなみにスマホ決済で失敗したセブン&アイも、「セブン−イレブンアプリ」にPayPayを搭載しています。
PayPayの躍進は大規模なキャンペーンによってもたらされました。サービス開始当初から「100億円あげちゃうキャンペーン」といった高額還元策を相次いで投入し、ユーザーの囲い込みを仕掛けます。またシステム利用料を無料としたことで導入する店舗が急拡大しました。これによりユーザーの認知や利便性が向上し、さらにユーザーが増えるという好循環が生まれたのです。
シェアの確立に成功したPayPayは収益化にステージを進めたとみられています。ユーザー向けのキャンペーンは続けながらも、2021年10月に加盟店が負担するシステム利用料を有料化しました。また、それまで無料で提供していた「ソフトバンク・ワイモバイルまとめて支払い」によるチャージも、2023年8月以降は毎月2回以上の利用で手数料が発生するよう変更されます。
さらにPayPayはグループ連携の強化にも取り組んでいます。従来はその他のクレジットカードをPayPayにひも付けることができましたが、2023年5月に「PayPayカード」に限定すると発表しました(2023年8月以降)。
これらの取り組みにより、PayPayの業績は改善しつつあります。2023年3月期のEBITDA(※)は、119億円の赤字と前期(同432億円の赤字)より大きく縮小しました。
※EBITDA(イービットディーエー):Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortizationの略。主に税引前利益に支払利息と減価償却費が加算されたもの。国際的な比較によく用いられる。
【PayPayの業績】
出所:Zホールディングス 2023年3月期決算説明会資料
日本解禁の「ステーブルコイン」は決済サービスをどう変える?
決済市場を巡っては、国内で「ステーブルコイン」が解禁されたニュースが話題を集めています。改正資金決済法が2023年6月に施行され、ステーブルコインが決済手段として認められることとなりました。
ステーブルコインとは、主に円やドルといった法定通貨を裏付けに持つ暗号資産(仮想通貨)を指します。通常の暗号資産には裏付け資産がないため激しい値動きが生じますが、ステーブルコインの価値は法定通貨に担保されることから、価格変動が抑えられる傾向にあります。
資金決済法の改正で認められるステーブルコインは、1コイン=1円のように、法定通貨の価値と連動するものに限られます。従って、価格変動がないため投機の手段となり得ず、電子マネーのようにあくまで決済手段として利用されるものが想定されています。
暗号資産を支えるブロックチェーン技術には自走型の仕組みがあり、概して中央集権的な大規模なシステムを構築する必要がありません。また処理速度も迅速であることから、低コストかつスピーディーな決済サービスの提供が期待されています。特にコストも時間もかかる国際間の送金問題は、ステーブルコインが解決するかもしれません。
年内にも金融機関などが法令に準拠したステーブルコインを発行するとみられていますが、暗号資産を扱うことから、従来とは異なるプレーヤーが決済市場に参戦する可能性もあるでしょう。これまでにない新しい決済サービスの提供が待たれます。
執筆/若山卓也(わかやまFPサービス)
証券会社で個人向け営業を経験し、その後ファイナンシャルプランナーとして独立。金融商品仲介業(IFA)および保険募集人に登録し、金融商品の販売も行う。2017年から金融系ライターとして活動。AFP、証券外務員一種、プライベートバンキング・コーディネーター。










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN