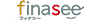この10数年くらいで、投資信託のコスト意識が大きく変わりました。特にこの数年、NISAのつみたて投資枠(旧制度におけるつみたてNISA)でインデックスファンドの本数が急増したのは、そうしなければ、つみたて投資枠を通じて資金を集めるのが、困難になる恐れがあったからです。
ご存じのように、つみたて投資枠の投資対象ファンドは、各投資信託会社が金融庁に、「このファンドをつみたて投資枠で購入できるようにしたい」ということを伝え、金融庁がつみたて投資枠を通じて購入できる投資信託として「適切である」と判断して、初めて対象ファンドになり得ます。
条件は複数ありますが、つみたて投資枠でインデックスファンドが重宝されているのは、対象ファンドの選定基準において、アクティブ型に比べてインデックス型の方が緩やかだからです。
アクティブ型の場合、「純資産総額が50億円以上であること」、「信託設定以降、5年以上経過していること」、「信託の計算期間のうち、資金流入超の回数が3分の2以上であること」といった基準が設けられていますが、これらがインデックス型の選定基準にはありません。
つまり新規設定ファンドであったとしても、金融庁に申請すれば、つみたて投資枠の対象として認められるのです。
その結果、つみたて投資枠の対象ファンドとしてインデックス型が急増したわけですが、もう1点、インデックスファンドが注目されたのは、受益者(投資信託の購入者である、個人投資家のこと)の投資信託の運用コストに対する意識が、大きく変わったからです。
交付目論見書に記載されるようになった「総経費率」とは
では、そもそも投資信託の運用コストとは何を指すのでしょうか。これまで投資信託の運用コストといえば、「信託報酬」を指すのが普通でした。
信託報酬とは、ファンドを運用する投資信託会社、ファンドの信託財産を管理する受託銀行、そして購入・解約資金、ならびに分配金の受渡業務を行う販売金融機関の三者に対して、受益者が信託財産の中から支弁するコストです。
しかし、投資信託の運用コストは、信託報酬だけではありません。この点がクローズアップされ、この4月から交付目論見書における義務付けられたのが、「総経費率」です。
投資信託の運用コストは信託報酬に加えて、たとえば組入資産を売買するに際してかかる売買委託手数料や、ファンドの監査費用、インデックスファンドであれば指数使用料金などが掛かってきます。これら全てを経費として示したのが、総経費率になります。
総経費率を示すメリットは、本当の意味での運用コストが明らかになることです。実際、ファンドによっては信託報酬に対して、総経費率が倍近くまで達しているファンドもあると言われています。
たとえば、信託報酬が年率1%と表示されているのに、総経費率が2%だとしたら、これは全くもって運用コストの実態を反映していないことになります。
そのため、総経費率が交付目論見書に記載されるようになったのは、受益者にとって一段と運用の透明性が高まったことを意味するという点において、非常に喜ばしいことだと思います。
インデックスファンドはコストが低いから…“正しい”?
ただ注意しなければならないのは、運用コストの高低について、ある種の誤解が生じている恐れがあることです。
「運用コストの低さは、リターンの向上につながる」。この点について疑いを持つ人はいないでしょう。
たとえばAファンドの運用コストが年1.5%で、Bファンドのそれが年0.5%だとします。これによって1%のコスト差が生じます。このコスト差を運用能力で跳ね返すのは非常に難しいので、運用コストは低いに越したことはない、ということです。
確かにその通りなのですが、「インデックスファンドはローコストで運用できるから正しい」というのは、果たして本当なのでしょうか。
実際、ここを強調してファンドの販売促進につなげている投資信託会社があります。商品サイトのページにも「信託報酬とは、投資信託の運用や管理にかかる費用となります。この率が低ければ低いほど、一部例外を除き一般的には、低コストで運用ができます」などと書かれているわけですが、この説明書きがされている投資信託は、インデックスファンドです。
信託報酬か総経費率か、について問題にしているのではありません。インデックスファンドで運用コスト差を問題にする意味が、どれだけあるのかを問いたいと思います。
“Slim”のありなしで何が変わる? 「eMAXIS」と「eMAXIS Slim」の成績比較から見えること
インデックスファンドの商品的な付加価値がどこにあるのかというと、それは連動目標とする指数に対して、どれだけ高い連動率を維持できるのか、という点です。
具体的な事例を挙げてみましょう。三菱UFJアセットマネジメントが設定・運用しているeMAXISシリーズです。最近では「オール・カントリー」が人気を集めていることで知られています。何しろ「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」の信託報酬率は年0.05775%で(2024年5月17日時点)、業界最低水準です。ちなみに、同ファンドの運用がスタートした時点の信託報酬率は年0.120%で、純資産総額が増えるのに伴って、段階的に料率の引き下げが行われてきました。
ところでeMAXISシリーズには、他のタイプの「オール・カントリー」もあります。正式名称は「eMAXIS 全世界株式インデックス」です。
Slimが付いているのと、付いていないのとで、何が違うのでしょうか。
まず信託報酬率が違います。「eMAXIS Slim(オール・カントリー)」が年0.120%から段階的に引き下げられて、現在は年0.05775%であるのに対し、「eMAXIS(オール・カントリー)」のそれは年0.66%です(2024年5月17日時点)。
なぜ、このような差が生じるのかというと、販売形態が異なるからです。eMAXIS Slimがこれだけの低コストを実現できているのは、販売をオンライン取引に限定し、目論見書等の交付を店頭での手渡しや郵送ではなく、電子交付に限定するなどコスト削減を行っているからです。対してeMAXISはオンライン取引以外に、対面型の金融機関でも扱っています。つまり管理コストがかかる分だけ、「eMAXIS(オール・カントリー)」の方が、高めの信託報酬を徴収しているわけです。
かたや信託報酬が年0.66%、もう一方が年0.120%から段階的に引き下げられて年0.05775%。これだけ信託報酬が異なれば、運用成績にも差が生じるだろうと考えるのが普通です。
ところが、eMAXISとeMAXIS Slimのオール・カントリーで成績を比べるとどうなるでしょうか。eMAXIS Slimのオール・カントリーが設定された2018年10月31日時点の基準価額の推移を比較すると、信託報酬率が圧倒的に低いeMAXIS Slimと、eMAXISのオール・カントリーの成績差は、ほぼないに等しい結果となりました。
同日の基準価額を100として計算すると、eMAXISが2024年3月末時点で237.65。対してeMAXIS Slimは240.97でした。5年と5カ月の運用期間でわずか3.32の差は、あってないようなものでしょう。
これはある意味、正しいことです。両ファンドにとって大事なことは、連動目標である指数に対して高い連動率を保つことなので、両者の運用成績に差が開かないのは、インデックスファンドとして正しい付加価値を提供していることになります。
だとしたら、わざわざ低コストを全面に打ち出したマーケティングは無意味であると解釈できます。繰り返しになりますが、インデックスファンドにとって最大の付加価値は、連動目標である指数に対して高い連動率を保つことなのです。それが達成されているのであれば、極端な話、年率2%の信託報酬率でも問題ないはずです。
思うのですが、そもそも信託報酬率の低さが運用成績にとってプラスの効果をもたらすのは、インデックスファンドではなく、アクティブファンドで問われるべきなのではないでしょうか。
運用者の銘柄選択眼、トレーディング能力で多少劣後したとしても、運用コストが低ければ、その不利をある程度カバーできる。その意味において、運用コストの低さがメリットになると考えることはできます。
しかし、それをインデックスファンドにも当てはめてマーケティングを行っているところに、今の投資信託市場の不健全さがあるように思えます。










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN