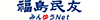大会参加費や宿泊費...財政的な課題も 部活動地域移行2年目
11競技50団体に
「いつも一緒に稽古をしている仲間が近くにいると心強い」。福島市の飯坂柔道スポーツ少年団に所属する鴫原稀琉(きりゅう)さん(13)はスポ少の一員として出場できる大会を心待ちにする。
昨年度から出場が認められた同スポ少には未就学児から中学生まで約40人が在籍する。このうち中学生は11人で、各学校に常設の柔道部がない子がほとんどという。鴫原さんの学校には柔道部はあるが、人数が足りず団体戦に出られないためスポ少で出場する。渡辺弘記代表(46)は「(昨年度は)小学校から切磋琢磨(せっさたくま)してきた仲間と出場できた。子どもたちだけではなく、保護者も喜んでくれた」と出場枠の拡大を歓迎する。
県中体連によると、本年度、県中体など主催大会に出場が認められた団体は昨年度の8競技29団体から11競技50団体に増えた。参加条件が緩和され、一部競技を除いて個人、団体競技いずれもクラブ活動所在支部の予選会からの出場が可能となった。本年度、予選大会から出場する磐梯町で活動するバレーボール「大谷イーグル」の加藤こず恵代表(45)は「昨年度出場できなかった先輩の分も活躍してほしい」と期待を込める。県中体連の田中信次理事長は「『学校に部活動がないから大会に参加できない』という生徒が出ないよう、各市町村の考えを大事にしていく」としている。
負担協議の必要
一方、クラブから出場する生徒の大会参加費や宿泊費はクラブ側の負担となる。財政面が課題となる中、飯坂柔道スポ少は昨年度、OBやOGから寄付を募って対応した。本年度は月謝を増やし、子どもたちの上位大会進出の際に備えており、渡辺代表は「送迎は親の協力を得ている。コーチ陣や親が協力し合って活動を進めたい」と語る。スポーツ社会学を専門とする福島大人間発達文化学類の蓮沼哲哉准教授は「上位大会を目指す場合は、受益者負担はやむを得ない」とした上で「各クラブがどのように自走していくのかを考えるためにも、指導者や保護者らが現場で具体的に協議する必要がある。そこに行政や競技団体などが関わっていくことも大切だ」と指摘する。(熊田紗妃)
部活動の地域移行 公立中学校教員が指導を担う部活動を、地域クラブや民間事業者に委託する改革。中教審は2019年、教員の働き方改革を進めるために部活の在り方を見直すべきだと答申した。国の部活運営に関する指針では「地域の実情に応じて可能な限り早期の実現を目指す」として達成目標を設定せず、23〜25年度を完全移行に向けた「改革推進期間」と位置付けている。










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN