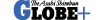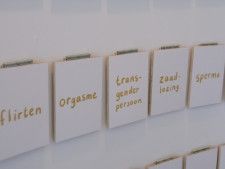2019年にアジアで初めて同性婚を法制化するなど、先進的なジェンダー施策を進めてきた台湾。背景には、2000年代から推進してきた「ジェンダー平等教育」がある。その役割や意義は法律に明記されており、この法律の存在が、保護者の理解を促し、学校で性教育を行う教師の支えにもなっている。現場を取材した。
指導の根拠はジェンダー平等教育法
3月下旬。台湾北部にある新北市の板橋区大観国民小学校4年生の教室で、教師の紀孟均(チー・モンチュン)さんが「デジタル性暴力」をテーマに授業をしていた。子どもたちが理解しやすいよう、キャラクターを使いながら、「親しい人の写真を、その人の同意なく、第三者に送っていいか」を児童同士で話し合い、「同意」について考えた。
台湾では、日本の学習指導要領に似た、「課程綱要」と呼ばれる指針(カリキュラム・ガイドライン)がある。学習段階ごとに学ぶべき内容や目標が示され、それらをもとに教科書も検定される。しかし、この日の授業は、その課程綱要に基づく内容ではない。2004年に制定されたジェンダー平等教育法が根拠となっている。
この法律は、1990年代の女性運動の盛り上がりや、2000年に学校でいじめを受けていた性的少数者の中学生が亡くなった事件などを背景に制定された。法では、小中学校では毎学期4時間以上、性教育を含むジェンダー平等に関する教育を行うことが求められている。紀さんの授業も、その一環だ。
台湾では、日本の保健体育に相当する「健康と体育」で、体の構造や生理現象などを学ぶ。しかし、紀さんたちはそこでは伝えきれない部分を、こうした授業で伝えている。
法律の意義は何か。
紀さんは「もし保護者から反対の声があっても、なぜこうした性教育が必要なのか、根拠をもって説明できる」と語る。「他のアジアの国と同様、台湾の保護者も性のことはあまり子どもと話したがらない。保護者世代は性教育を受けた経験が乏しく、性教育とは何かわかっていない人が多い」
台湾でも性教育への反発は少なくない。2017年には、児童からの質問に答える形で小学3年生の授業でコンドームについて教えた教師が「わいせつ行為だ」などと訴えられた。この教師は、そのクラスの保護者の同意を得て実施していたが、この授業がメディアに取り上げられたことで、それを見た人が検察に告発。しかし、学校や地元の教育局は教師を支持し検察も教師を不起訴にした。
現場の自主性尊重、教える内容や質にばらつきも
学校教員らによる「台湾ジェンダー平等教育協会(TGEEA)」の教育推進マネジャー、姚惠耀(ヤオ・ホイヤオ)さんは「保護者の性教育への反対の声は決して大きくない。だが、一人でも反対すると、その声が大きく聞こえる」と指摘する。だからこそ、「法律があると、もし保護者から反対の声があっても、教師は『文句があるなら政府に言って』と言うことができる」と語る。
ただ、法で定めるものの、ジェンダー平等教育は決まったカリキュラムはない。どのような内容にするかは、学校や教員に任されている。姚は、教員によって内容や質にばらつきが生じる面も否定しない。しかし、「法に基づく教育の内容を一律に決めるよりも、課程綱要に包括的性教育の内容を反映し、充実させていくことが大事だ」と指摘する。
協会が重視するのは、ユネスコ(国連教育科学文化機関)などが作成した「国際セクシュアリティ教育ガイダンス」だ。包括的性教育という考えを前面に打ち出し、項目ごとに各年齢で学ぶべき目標などを系統立てて示している。
協会は昨年、台湾の小学校の実態を調査し、教科書の内容とユネスコなどのガイダンス内容を比較。その結果、ガイダンスが重要な要素として掲げる8項目のうち、「人間関係」や「健康とウェルビーイングのためのスキル」「ジェンダーの理解」などは教科書に高頻度で掲載されていたが、「セクシュアリティーと性的行動」や「性と生殖に関する健康」に関する内容はほとんど触れられておらず、「性を語ることを避けた性教育」と指摘した。
また、ガイダンスが「若者の批判的思考や市民意識の育成」を奨励しているのに対し、現在の台湾の性教育は、「家庭や社会の調和に結びつけることが目標になっている」とみる。
昨年10月に協会が主催した性教育に関するフォーラムに出席した潘文忠(パン・ウェンチョン)教育相は、ユネスコなどが示す包括的性教育について「国際的なコンセンサスを得ている」との認識を示し、それに基づき、課程綱要を改訂していく方針を示した。
一方、課程綱要の策定に携わった、性教育学会の晏涵文(イエン・ハンウェン)名誉理事長はガイダンスの中で示された内容をその年齢で教えることには懐疑的だ。
例えば、ガイダンスでは、5〜8歳で「妊娠は、自然な生物学的プロセスで、計画可能なものである」ということを、9〜12歳でコンドームの正しい使い方などを教えるとしている。
しかし、晏さんによると、これらの項目は台湾では中学段階で教えていると言い、「この年齢でこうした内容を教えることが良いと考えている保護者は台湾では多くない。ユネスコもガイダンスの中で、その国の状況に沿った内容で教育することを否定していない」と主張する。晏さんは現在、保護者がどの年齢でどういった内容を教えるのが良いと考えているかを調査しているという。
「アダルトビデオを親子で見て間違った表現を確認」
台湾の性教育を受けてきた側は、どう感じているのか。
台湾大学の学生で、基隆市出身の葉謹榕(イエ・チーロン)さん(22)は、小学校6年の時に保健室の女性の先生が行った性教育の授業が印象に残っているという。
「先生は、自分の息子とのアダルトビデオを一緒に見て、『その中には間違った表現があることを親子で話した』と教えてくれました。当時は驚きましたが、『そうやって、性をオープンに話していいんだ』と思えるようになりました」
その授業が、ジェンダー平等教育法に基づく性教育だったかはわからない。ただ、当時のクラスの担任の先生は男性で、自分では性教育をうまくできないと思い、保健室の先生に頼んだのではないか、と葉さんはみる。
一方、同じく台湾大学の学生で、台北市出身の羅中聖(ルオ・チョンション)さん(23)は小中学校時代、性教育にあたる内容は「健康」に関する授業で習ったが、「正直、あまり印象に残っていません」と話す。
授業では男女の体の構造の違いや生理現象、それを踏まえた体のバウンダリーなどは学んだが、異性とのつきあいやLGBTQのことについてのきちんとした説明はなかったという。
「いまはインターネットが普及し、ネットには性やLGBTQに関する正しくない情報も多く出回っている。小中学校段階から、正しい知識を伝えるとともに、人に対する基本的な尊重の姿勢を学ぶ必要があると思います」と語る。
2人とも、高校では、健康に関する授業で、コンドームの装着を実際に練習したことがあるという。葉さんは、「実際にやってみると、なかなか難しい。練習をして良かった」と振り返る。しかし、中学校時代には、すでに校内で「生徒が妊娠したかもしれない」などの噂もあったといい、「もっと早い段階でこうしたことを教えた方がいい」。羅さんも「早めに性の知識を知った方が予防できる」と話す。
学校や教員の姿勢がもたらす影響も少なくないという。葉さんによると、「健康」の授業は、数学などの教科と違って、「進学には無駄」と思われがちだといい、「学校によっては専門ではない先生が担当する可能性もある。どういう人が性教育を指導するかも、とても大事な問題だ」と話す。
葉さんや羅さんは現在、ほかの台湾大の学生と共に、「Moonteacha(月月老酥)」という団体を結成し、生理について安心して討論する場所を作る活動を続けている。「月経について、人前で話しにくい」とメンバーたち自身が感じていたことがきっかけとなった。
団体では、交換日記やボードゲームなどを使って、生理についての経験や疑問をシェアする。生理について人と話すことで、生理をポジティブに捉えるようになったり、人に聞けなかった疑問を解消したりするなど、様々な手応えを感じているという。










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN