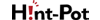親が認知症になったら、どのような問題が起こるのでしょうか。親の預金口座は凍結され、預金口座が凍結され、本人や家族、子どもでも必要時に引き出せなくなることを前編でお伝えしました。後編では、親が認知症になる前にできる対策について、弁護士法人C-ens法律事務所の森崎秀昭弁護士に話を伺いました。
◇ ◇ ◇
認知症になったあとの口座凍結対策は成年後見制度のみ
親が認知症になってしまうと、親の財産を守るために預金口座が凍結されます。凍結されてしまった口座からは、家族でも、本人であっても預金を引き出すことはできません。唯一の解決方法は、成年後見制度を活用することだと前編で触れました。
しかし、手続きに時間がかかるうえ、成年後見人は裁判所によって選定されるため、必ずしも家族がなれるわけではありません。仮に弁護士などの専門家が選出された場合は、親の介護のための費用であっても、成年後見人の許可がなければ、容易に親の財産を使用することができなくなってしまいます。
このように、成年後見制度はあくまでも事後的な対応の解決方法ですが、デメリットが多いことも事実です。そのため、親が認知症になる前に家族で話し合って、事前に対策しておく必要があります。
認知症になる前にできる対策は2つある
事前にできる対策は、主に2つあります。
1. 任意後見制度を活用する
任意後見制度とは、事前に親本人が専門家などと契約をし、裁判所の許可をもらって、専門家に財産管理を依頼する制度です。
これは成年後見制度とは異なり、認知症になる前に後見人を選んでおきます。口座凍結した場合、成年後見制度を活用した場合と比較して、比較的早く預金を使えるようになるのです。ただ、成年後見制度と同様、親の介護費用や財産利用の際には後見人の許可が必要になるため、財産活用の自由度は低くなります。
2. 家族信託を活用する
後見人制度のデメリットの部分を回避できるのが、家族信託。これは、たとえば親が認知症になる前の元気なうちに、親の財産を家族が管理運用処分できるように家族間で契約するイメージです。
もちろん、家族信託にもメリットとデメリットがあります。
家族信託のメリットとは…財産が守られるうえに活用できること
家族信託のメリットには、主に6つあります。
1. 口座凍結に備えることができる
親の認知機能に関係なく、親の預金口座を含む財産を動かすことができるので、仮に親が認知症になったとしても口座凍結を回避することができます。
2. 親の思い通りに財産を継承できる
親との話し合いしだいにはなりますが、内容によっては、親が思い描く財産の継承を行うことが可能になります。
3. 資産を運用し増やすこともできる
後見人制度とは異なり、親の財産を資産運用にも活用可能です。そのため、より柔軟な財産の使い方が可能になります。
4. 遺言の役割も果たして相続がスムーズになりやすい
親の財産の振り分け方を事前に決めておくことになるので、遺言のように活用することも可能です。
5. 不動産がある場合には共有による不利益を回避できる
親の単独名義ではなく、兄弟を含めた共同名義の不動産を持っている場合、口座凍結のように不動産の売却や修繕ができなくなるおそれも。家族信託であれば財産を家族に預けられるので、このような問題も回避することができます。
6. 財産を預かる子が破産しても預けた財産を守ることができる
生きているうちに子どもに財産を分配し、親が介護などを受けている場合、子どもが破産すると財産がなくなってしまい、介護などのサービスを満足に受けられなくなってしまいます。しかし、家族信託であれば預けた財産が守られるため安心です。
このように家族信託は、親が認知症になっても、家族が親のための介護サービスや自宅のリフォーム、資産運用や収益不動産の運用を行うなど、親の財産を活用することができます。そのうえで財産が守られることが最大のメリットです。
メリットだけではない 家族信託にはデメリットも
その一方で、もちろんデメリットもあります。
1. 節税や事後的な争いの回避という視点では設計しだい
信託内容の設計の仕方によっては、家族間において不公平感が生じてしまい、親が認知症になったあとに争いになってしまうケースもあります。また、節税できない設計になることもあるため、弁護士など法律の専門家に相談するのがいいでしょう。
2. 財産管理をする人の負担が大きくなりがち
法律上の義務も発生するため、労力が大きな負担になることがあります。
3. 信託できない財産もある
預金については現金として信託することが可能なので、口座凍結のリスクを回避することができますが、農地、普通預金や定期預金などの預金債権は、残念ながら信託することができません。ただし、預金については現金として引き出して信託することが可能です。
4. 親の代わりに契約ができるわけではない
家族信託は、親の代わりに契約を交わすことができるものではありません。そのため、介護施設やサービスなどが必要な場合は、親の認知機能がしっかりしているうちに契約を行うか、認知症になったあとに成年後見人を選んで依頼する必要があります。
5. 親の理解を得にくいことも
家族信託そのものが少し難しい内容であるため、高齢の親にとっては理解しにくいこともあります。親の理解を得られるように、家族や専門家の協力を仰ぐといいでしょう。
6. 相続時に微妙な争いが発生することも
相続を受ける人は最低限もらえる割合が決まっているので、これを満たさない設計になる場合は、別途お金を支払う必要があります。
親が認知症になるという出来事に直面すると、気持ちの面だけでなく、実務面で困難が待ちかまえています。もしなんの対策もしていないうちに診断されてしまった場合は、成年後見制度を利用することになると思いますので、親の財産を守るためにも早急に手続きを進めることが大切です。
また、まだ時間がある場合は、成年後見制度や家族信託を含めて自分たちのベストな選択について、親と一緒に話をしておくといいでしょう。なにより、心の準備と現実の準備の両方を今のうちから進めておくといいのではないでしょうか。
Hint-Pot編集部・出口 夏奈子










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN