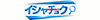エアコン内部のカビが引き起こす「夏型過敏性肺炎」
「エアコンのスイッチを入れてすぐはニオうけど、我慢して使っていたらすぐ分からなくなる」という人もいるでしょう(ヒトの嗅覚は良くも悪くも慣れやすいのです)。でも、その我慢は大間違い。
なぜなら、エアコンから出ているのはカビのニオイだけではありません。内部で繁殖したカビの胞子や死骸が、冷風とともにはき出され、室内を舞います。同時に窓を開けているのでなければ、肺いっぱいに吸い込んでいるに違いありません。
なんだか気持ち悪い、で済めばいいのですが、健康に良くないのは明らか。
特に、「トリコスポロン」という白カビは、「夏型過敏性肺炎」をひき起こします。
初期症状は一般に、咳や息切れとともに微熱や倦怠感が出ます。悪化すると、少し動いただけで息切れしたり、眠れないほど呼吸が苦しくなったりして、最悪の場合は死に至ることもあります。
昨年には、新型コロナの重症入院患者からトリコスポロンの気道感染が見つかったことが、スペインから報告(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7705399/)されました。この方は最終的に亡くなっています。トリコスポロンは身の回りにいるカビですが、免疫力や体力が落ちている人にとっては深刻な影響をもたらすのです。
トリコスポロンの胞子の大きさは約2.5〜3マイクロメートルで、天気予報などでも警戒を呼び掛ける「PM2.5」と同程度で、呼吸によって肺の奥まで到達します。気道〜肺の組織に達した胞子を、体内をパトロールしている免疫細胞が“異物”として認識し、攻撃が始まります。
このとき、過剰な反応によって肺の組織も傷つけられ、炎症が起きてしまいす。これが過敏性肺炎です。
今まさにカビの大繁殖シーズン。湿度管理より大事な対策とは?
その後も繰り返しカビの胞子にさらされることで、慢性的な炎症状態となり、次第に悪化していく人が少なくありません。
胞子は、ちょうど今頃から秋口まで飛散します。長丁場ですが、肝心なのがまさに今、エアコンの使い始めの時期です。
カビの発生条件は、温度20〜35℃、湿度60%以上で、栄養源となるホコリや汚れ(食べかすやダニの死骸などを含む)があることです。
多くの人が「この時期は湿気があるからカビが生えやすい」とあきらめがちですが、大事なのは、もう一つの条件である栄養源を絶つこと。つまり清掃です。
使わない間にエアコンに溜まったホコリや汚れは、カビの胞子と栄養の混合物と言ってよく、カビにとって都合の良い高温多湿環境さえ整えば、一気に繁殖を開始します。
ですから、エアコンを久しぶりに使うときは、必ず事前にしっかり清掃し、試運転して風を通しておくことが、非常に重要なのです。
フィルターは取り外して洗い、よく乾かします。トリコスポロンの大好物であるホコリ、特に人のアカやフケは、眼に見えない塵となって空気中に舞っていて、それを捉えるのがフィルターです。
1ヵ月前に掃除したご家庭でも、頻繁に使っていれば、すぐに汚れは溜まります。週に1度を目安に、できれば曜日を決めて清掃を習慣化するといいでしょう。取り外しの際にホコリを吸い込まないよう、必ずマスクを装着して、窓を開けて換気しながら行ってください。
ただ、エアコンを毎日使っていると、汚れは進んでもフィルター自体にカビが生えることはほぼありません。風が頻繁に通る状態なのでフィルターが湿ることはほとんどなく、また、胞子も小さすぎてそのまま吹き飛ばされてしまうことが多いためです。
課題は、エアコン内部のカビです。
フィルター掃除だけでは不十分…他にどこをきれいにするべき?
残念ながら、内部の汚れがひどい場合は、プロの手に任せるしかありません(ちなみに近年では「自動清掃機能付き」のエアコンも人気があるようですが、どこを清掃してくれるのかと言えば、やはりフィルターのみ。内部まではきれいになりません)。
では、そうなる前に、また、清掃してもらってもすぐにカビだらけにならないように、できるだけエアコン内部を清潔に保つ方法はないものでしょうか?
エアコン内部は構造が複雑で、水の通り道など結露の生じやすい部分もあり、どうしても湿気がこもります。入り込んだ胞子やホコリが湿気でくっつきあって溜まり、そこに含まれる有機物をエサにカビが増殖します。
それを防ぐためにも、まずはやはり、フィルターのこまめな清掃です。目詰まりしていると、スムーズな空気の流れが妨げられ、フィルターのホコリが押し込まれてエアコン内部に広がってしまいます。
フィルター掃除が滞っているけれど、どうしてもエアコンをすぐに使いたい、という場合は、使い始めの10分間は「送風」に設定してカビの胞子などをできるだけ追い出します。その間は必ず、風が通るように部屋の窓を2ヵ所以上開けておきましょう。
さらに、フィルター清掃と同じくらい大事なのが、部屋の掃除と換気です。
エアコンに入っていく空気中のホコリそのものを減らすのです。床はもちろん、インテリアの上のホコリをこまめに取り除き、舞い上がることのないようにします。
そして換気です。朝晩、そして床やインテリアの掃除の後には、しっかり窓を開けて空気中に漂うホコリを追い出しましょう。花粉や黄砂等の時期は無理をせず空気清浄機を使うこともあるかと思います。その場合も、フィルターを常にきれいにしておくことが大前提です。
また、家の中にはエアコン以外に、洗濯機、浴室・脱衣所、押し入れなど、カビの生えやすい所があります。こまめな清掃で汚れをしっかり落としてカビの栄養源を取り去り、水気は逐一ふき取った上で、通気を心がけましょう。発生してしまったカビは塩素系漂白剤等で早めに除去してください。
そのようにしてカビ胞子の放出のもとを断ち切ることも大切です。
これってカビ肺炎? 夏風邪の後の「咳ぜんそく」の場合も
夏型過敏性肺炎は、最初は「夏風邪かな?」と思う患者さんが多く、そのままにしてしまうのが怖いところです。
確かに初期症状は普通の風邪と重なる部分が大きいのですが、もし「家では咳が出て調子が悪いのに、外出中は不思議と症状が軽くなるな」と感じるようであれば、カビの影響を疑ってみても良いかもしれません。
実は、患者さんの中心は30〜50歳の主婦です。家にいる時間が長いためと考えられます。
特効薬はありません。急性症状が強い場合はステロイド薬で一時的に炎症を鎮める場合もありますが、あくまで対症療法です。
実際、夏型過敏性肺炎の入院患者さんは、入院しているだけで勝手に体調が回復する人が多いです。カビ環境から離れて過ごすだけでも、あとは免疫力が上回ってくれるのでしょう。しかしそれで退院するとまた肺炎に逆戻り…。元凶である家や職場のカビ環境を改善しないことには、その繰り返しです。
また、熱などの症状はないけれど咳が止まらず、外出時は症状が収まる、という場合、「咳ぜんそく」の可能性もあります。同じくカビの胞子や死骸を原因とする、ハウスダストアレルギーの一種です。
夏風邪の後や、運動、発声時など、気道の粘膜が過敏になっているところに、カビの胞子・死骸がアレルゲンとして付着し、その刺激でぜんそく症状がひき起こされます。乾いた咳で、出始めると止まらず、多くは夜間から明け方にひどくなります。
いずれにしても、慢性的な咳の症状が2週間を越えて続くようであれば、受診してください。
幸い心当たりなく平穏に過ごしています、というご家庭でも、エアコン24時間フル稼働の暑さとなる前にぜひ、カビ対策を! エアコンだけでなく部屋や水回りの掃除と、こまめな換気を徹底していきましょう。










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN