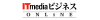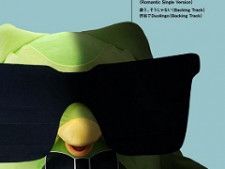この10年、小売店などの中間業者を挟まず、SNSや自社ECを通じて製品を顧客に販売するビジネスモデル「D2C」(Direct To Consumerの略)が活性化し、多数のブランドが乱立した。
前回の記事では、このD2Cのビジネスモデルが、薬事法やステマ規制、価格競争の激化などを背景に市場が厳しくなり、冬の時代を迎えているということをお伝えした。
D2C事業社の多くはこれまで「インフルエンサーマーケティング」での顧客獲得に注力してきた歴史がある。このインフルエンサーマーケティングが今、急激に失速している。
この荒波の時代においても、独自のマーケティング手法を磨き続け、顧客獲得を続けるプロフェッショナル企業になるためには、インフルエンサーマーケティングを取り巻く厳しい状況を正しく理解し、「ファンマーケティング」にアップデートしていく必要がある。
今回の記事では、歴戦のD2C強者たちが実践する、最先端のマーケティング手法「ファンマーケティング」の実態に迫る。
●かつては盛り上がりを見せた「インフルエンサーマーケ」の実態
ファンマーケティングを語る上で、まずは正しくインフルエンサーマーケティングについて理解する必要がある。
インフルエンサーマーケティングとは、インスタグラムやXで多くのフォロワーを持つ芸能人などに自社製品やサービスを使ってもらい、それをPRとして投稿してもらう手法だ。
この手法がマーケティング界隈(かいわい)で市民権を持ち始めたのは、10年ほど前に発売されたBOTANISTというシャンプーがきっかけだろう。
もちろん今までも有名人に自社製品を使ってもらい、プロモーションとするマーケティングは一般的であったが、BOTANISTが特徴的だったのは、“マイクロインフルエンサー”を活用したことである。
マイクロインフルエンサーとは、フォロワーが1万人から10万人程度の、いわゆる「その特定のカテゴリーに詳しく、発信力のある人」だ。
例えば化粧品が好きで、化粧品の投稿にとがって投稿し続け、数万人のフォロワーを持つような人は、その領域における強い影響力を持っている。
よく企業がインフルエンサーに投稿依頼をする場合は、1フォロワー1円換算といわれるが、100万人のフォロワーを持つ有名人1人だけに100万円を払ってプロモーションしてもらうより、数万人のフォロワーを持つマイクロインフルエンサー10〜20人が一斉にその商品をおすすめした方が購買率が上がるという原理だ。
これは読者の皆さんも、普段YouTubeやインスタグラムなどを見る際に体験したことがあるだろう。
このインフルエンサー施策を特に活用してきたのがD2C企業だが、ここ数年、ビジネス系や生活雑貨系など幅広いインフルエンサーが登場し、さまざまなカテゴリーの企業が1つの施策として活用する時代となった。
●なぜ失速? 背景に2つの理由
こうして日本のマーケティングの一手法となったインフルエンサー施策だが、今まさに厳しい状況に追い込まれている。
その背景には以下の2つの理由がある。
(1)インフルエンサーの数は有限であり、消費者にとって飽きがくる
そのカテゴリーにおけるインフルエンサーの数は有限である。
例えば関西で飲食店をチェーン展開している企業があるとしよう。
その企業はまず、食レポを上げて人気を得ているインフルエンサーをリストアップし、DMや代理店を通してアプローチするが、人気なインフルエンサーは漏れなく他社のPRも引き受けている。
つまり、そのインフルエンサーをフォローしている人たちからすると、複数の飲食店のプロモーションを度々見ることになり、「この人昔は面白かったけど、最近は案件ばっかりだからなんか嫌だな」となる。
抜けがちな観点だが、このようにインフルエンサーの数はどの領域においても有限であり、「いくらでも簡単にインフルエンサーにPRしてもらえる」ことはないのだ。
(2)インフルエンサーが案件を選ぶようになる
企業からのPR案件を受けまくり、マネタイズだけを優先したインフルエンサーの投稿は「#PR」ばかりとなり、消費者からすぐに飽きられる。
特に近年はステマ規制がかなり厳しくなったため、本当は企業からお金を受け取ってPRしているのに、あたかも“自ら投稿している”ように見せかけてプロモーションすることもできなくなった。
結果、1日にPRできる数にも制限が発生し、「PR枠の在庫数」という概念が生まれた。
つまり、これまでは「インフルエンサーのPR枠>企業からの案件数」だったのが逆転し、企業がインフルエンサーのPR枠を奪い合う構図へと大局観が変化したのだ。
これらを背景に、10年前の「とにかくSNSでフォロワーの多い人にPRしてもらう」という時代から、「本当に影響力のあるインフルエンサーに、自社製品を本当に気に入ってもらう」時代へと変化したのだ。
●「真のインフルエンサー」を探せ これからは「熱量」の時代に
では、影響力のあるインフルエンサーに、自社製品を本当に気に入ってもらい、素晴らしいプロモーションにつなげるにはどうすればよいのだろう。
インフルエンサーマーケティングという概念自体はもはや新しくないが、それを自社の戦略としてうまく活用し、事業を伸ばしている会社はまだそこまで多くないだろう。うまく活用できている会社とそうではない会社を分ける戦略の分岐点は何なのか?
この答えはずばり、「インフルエンサーのインフルエンサーにファンになってもらうこと」だ。
インフルエンサーの人数は有限とはいえ、一企業が全てのインフルエンサーにリーチするのは不可能だろう。また、インフルエンサーの多くはトラブル回避などを理由に、直接企業とやりとりせず、広告代理店を通してしか発注を受けない人も多い。
そんな中で、この手の施策をうまく実施し、成功している企業が注力しているのは、インフルエンサーに影響力を持つインフルエンサー、つまり影響力の根源となるような人物に自社のファンになってもらうことだ。
読者の皆さんは「インフルエンサーのインフルエンサー? どういうこと?」と思うかもしれない。
当たり前だが、インフルエンサーはわれわれ以上に、競合となるインフルエンサーをSNSでしっかりサーチしている。
そんな中で、消費者からの強い支持を持ち、企業案件を受けてもフォロワー数を減らさずアカウントを運用しているお手本のようなインフルエンサーは、その界隈でも強い発言力がある。
このような強いインフルエンサーが紹介する製品やサービスは本当に信頼できると、インフルエンサー界隈ですぐに情報がキャッチアップされる。
すると、これまではその製品やサービスをSNSで紹介することに抵抗を持っていたインフルエンサーも扉を開けてくれるようになる。他社よりも円滑にインフルエンサーによるPRが広がっていくのだ。
このような戦略を取るためには、結局は強い影響力を持ったインフルエンサーに、ただの企業案件としてではなく、一製品・サービスとして本当にその良さを理解してもらう必要がある。「自分の大切なフォロワーにもPRとして紹介したい」という強い熱量を持ってもらうこと、すなわち“ファン”になってもらうことが一番の成功への近道なのだ。
一見、きれいごとのように聞こえるかもしれない。しかし、情報があふれるこの時代において、マーケティングもその原点である「WHO(ターゲット顧客)に正しいWHAT(製品便益)を理解してもらうこと」が、顧客にも、インフルエンサーに対しても重要である。
マーケティングエクセレントカンパニーと呼ばれる会社は、このような弛(たゆ)まぬ努力を続けることで他社よりも素晴らしいパフォーマンスを残しているということだ。
筆者プロフィール:小林幸平
京都大学大学院医学研究科卒業後、 日本ロレアル株式会社に入社。新規ヘアケア製品ノーシャンプーのプロダクトマネジャーとして新製品の開発および販売戦略立案を担当し、同製品は楽天市場総合ランキング1位を獲得。その後デジタル・イーコマースにおけるマーケティング責任者として事業拡大戦略の立案と推進に取り組んだのち、2019年8月よりメイベリンニューヨークのアジアヘッドクォーターにてリージョナルマーケティングマネジャーとしてビジネス統轄を担う。その後、2021年2月よりノバセル株式会社の執行役員として同社事業を牽引。
合同会社スモールミディアムCEOとして、D2Cブランドの経営も行う。










 プロバイダならOCN
プロバイダならOCN